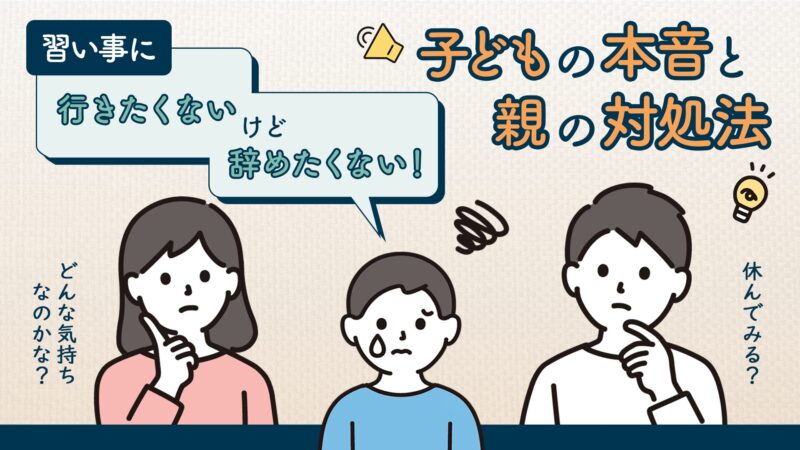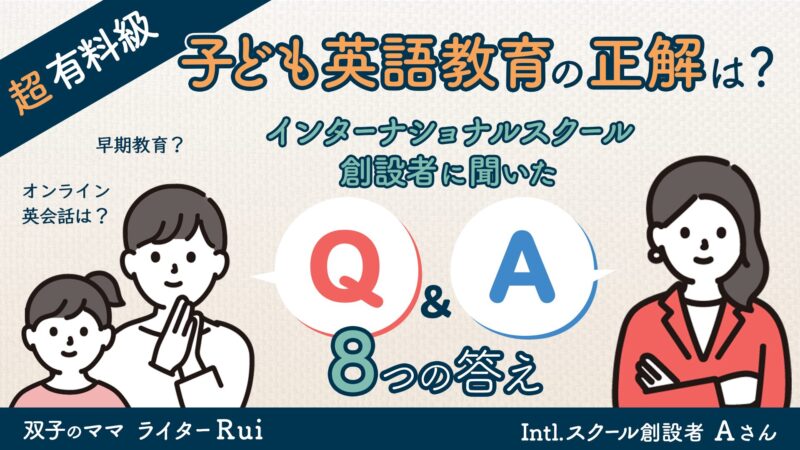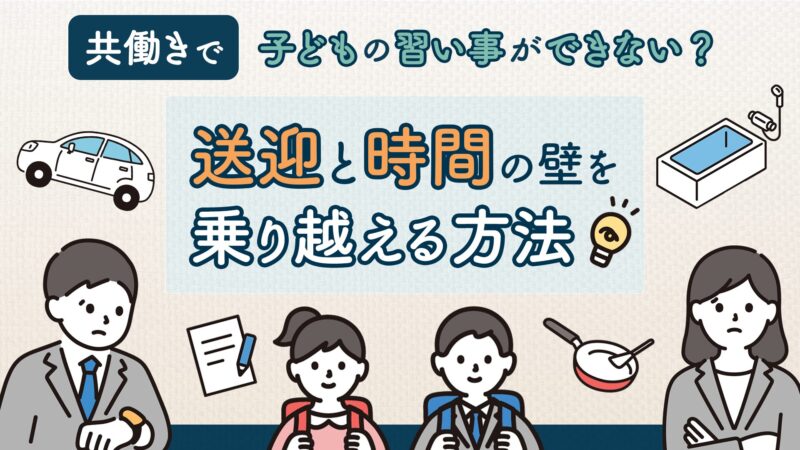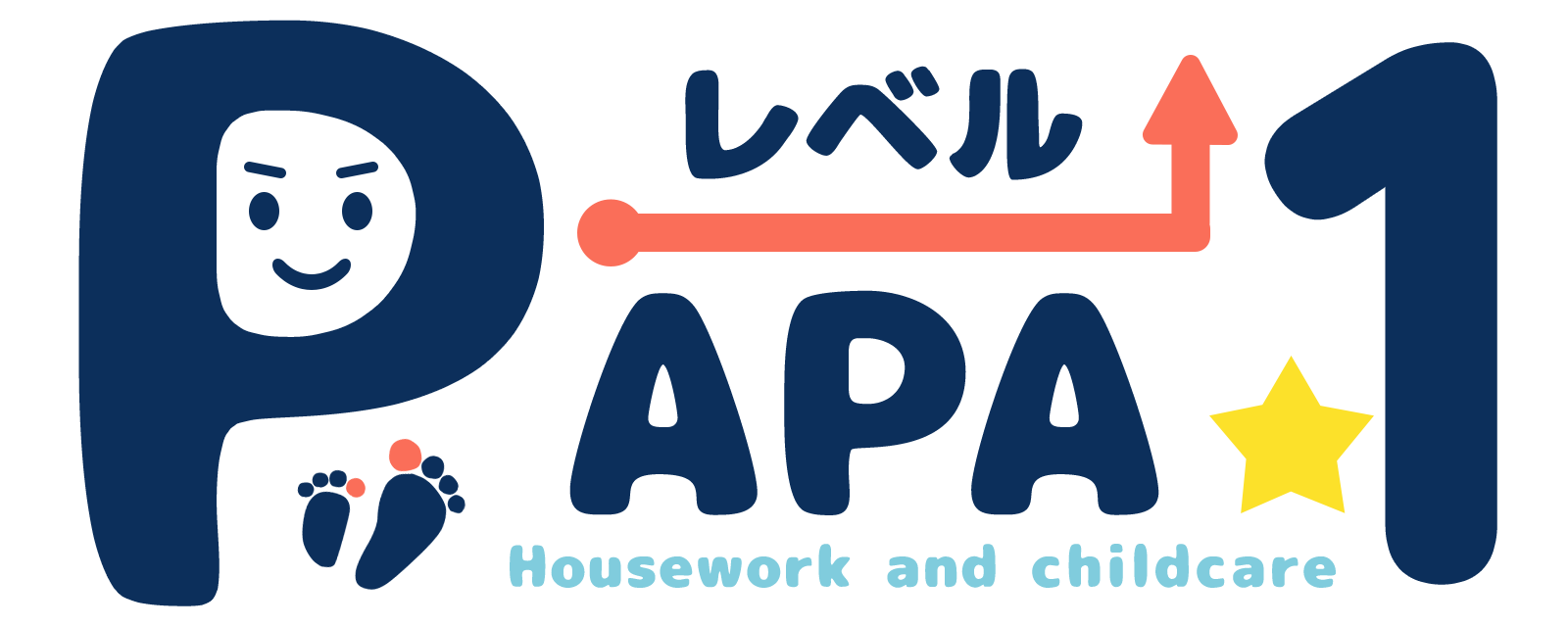習い事に行きたくないけど辞めたくない!子どもの本音と親の対処法
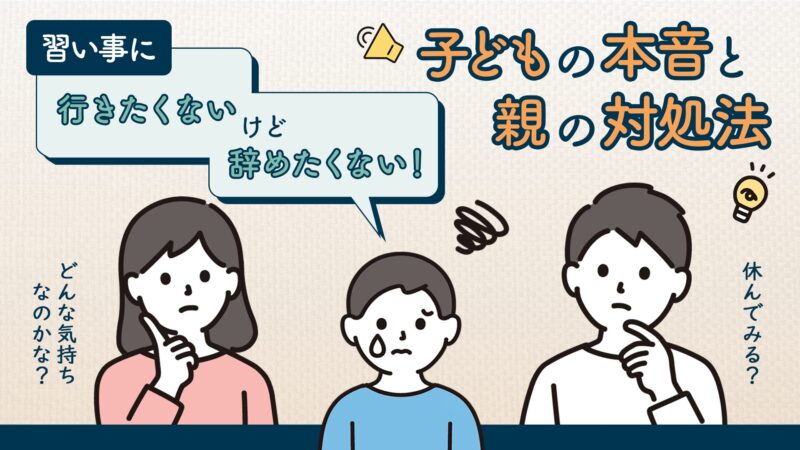
ある日突然、子どもから「今日、習い事に行きたくない」と言われると、戸惑ってしまいますよね。
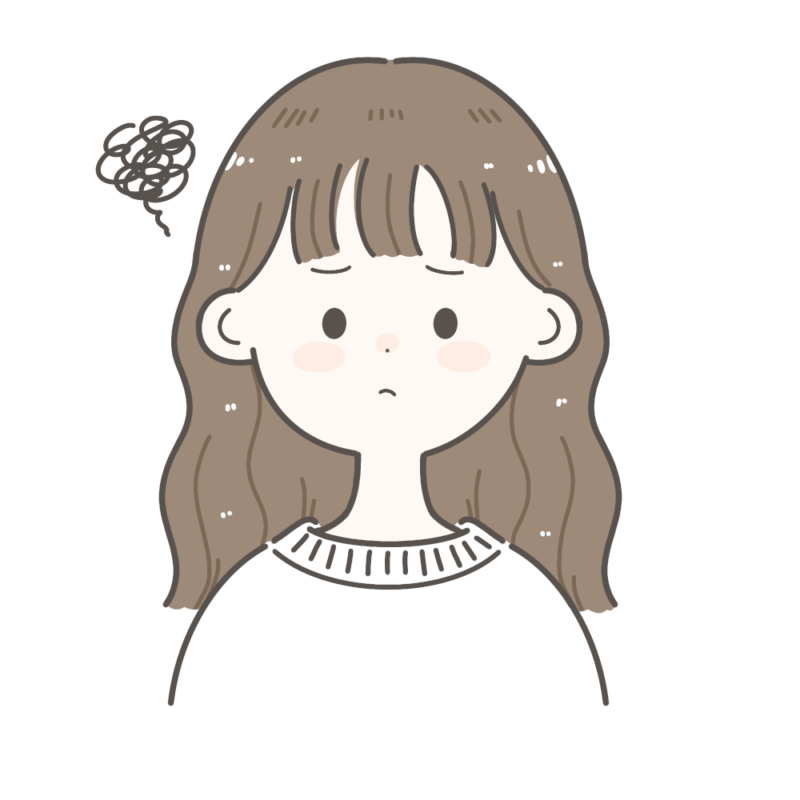
もう興味がなくなったのかな?無理に続けさせるのはかわいそうだけど…
このように、いろいろな思いが頭をよぎるかもしれません。
ところが、「じゃあ辞める?」と聞くと、「それはイヤ!」と返ってくる…。
そんなとき、どうすればいいのか悩む方も多いのではないでしょうか。
でも実は、この「行きたくないけど辞めたくない」という気持ちは、子どもによくある自然なものなんです。
- 習い事に行きたくないけど辞めたくないと感じる子どもの深層心理
- 習い事に行きたくないけど辞めたくないと言われたときの対応方法
- 習い事「継続」或いは「見直し」の判断基準
この記事では、子どもがなぜそんなふうに感じるのか、どんな気持ちが隠れているのかをいっしょに見ていきましょう。

mizuno(Webライター)
公立・大学図書館で8年間勤務した元司書。
育児歴10年の経験を活かし、完璧を目指さない「楽しむ子育て」を発信中です。
「習い事に行きたくない、でも辞めたくない」とは?
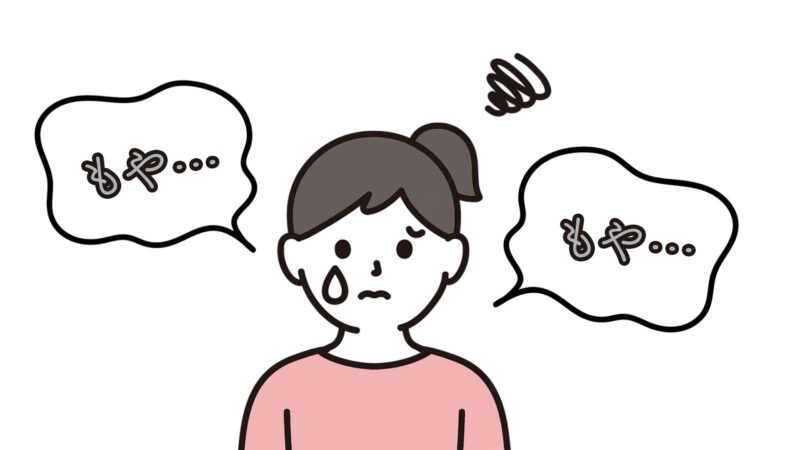
子どもが感じているモヤモヤの正体
子どもが「行きたくない」と言うと、つい「もうイヤなのかな?」「飽きたのかな?」と考えてしまいがちですが、それは少し早とちりかもしれません。
大人でも「今日は仕事行きたくないな〜…でも辞めるほどではないんだよな…」なんて日、ありますよね。とくに子どもの場合は、言葉にして気持ちを整理するのが難しいぶん、本人も戸惑っていることが多いもの。
子ども自身も、自分の中の気持ちに混乱していることがあります。
疲れていたり、不安を感じていたり、なんとなく気が進まなかったり。
そんな「なんとなく」のモヤモヤをうまく言葉にできず、「行きたくない」という一言にしてしまっているだけのことも多いのです。
たとえば、こんな理由が考えられます。
- 学校や他の習い事で疲れている
- 練習についていけず、自信をなくしている
- お友だちとの関係で気になることがある
- 今日は気分が乗らないだけ、でも習い事は好き
大切なのは、「行きたくない=嫌い」とすぐに決めつけないこと。
「なんで行きたくないのかな?」
「なにかイヤなことがあったのかな?」
と、やさしく気持ちを聞いてみることが、子どもの安心感につながります。
行きたくない=嫌いではない?心理の矛盾を解説
「好きだけど、ちょっと気が重い」
「やりたいけど、不安」
など、子どもは相反する気持ちを同時に抱えることがあります。これはごく自然なことです。大人でもよくあることですよね。
- ピアノは好きだけど、発表会が近くて緊張している
- サッカーが楽しいけど、最近うまくできなくて悔しい
- 英語の先生は好きだけど、今日は眠くて集中できなさそう
「楽しい」と「しんどい」
「好き」と「不安」
こんなふうに、複雑な気持ちが混ざり合って「行きたくない」という言葉になってしまうのです。
それでも「辞めたくない」と言うのは、子どもなりに「続けたい」という気持ちがちゃんとあるから。この気持ちを尊重してあげることで、子どもは「ちゃんとわかってもらえた」と感じ、また一歩前に進むことができます。
習い事に「行きたくないけど辞めたくない」理由7選

「習い事、行きたくない…」と言いつつ、「でも辞めたくない!」とも言う子ども。
その矛盾するような気持ちには、実はよくある「理由」があります。
子ども自身も言葉にできずにモヤモヤしていることが多いからこそ、親がその背景を知っておくことが大切です。
ここでは、そんな「行きたくないけど辞めたくない」子どもの本音を、7つの視点から解説します。
理由① 友だち関係でのストレス
習い事の中でも、人間関係は大きな要素。
- 仲のいい友だちとケンカしてしまった
- グループから外されたように感じている
- 先輩・後輩などの上下関係に気を使う
大人にとってはささいなことでも、子どもにとってはとても大きなストレスになります。
「嫌いになったわけじゃないけど、今日はちょっと行きたくない…」そんな気持ちになってしまうのも無理はありません。
理由② 仲良しの子や先生に会えなくなるのが寂しい
習い事に対する興味は薄れてきているけれど、友達や先生に会えなくなるのが寂しくて「辞めたくない」と感じている子どもは少なくありません。
たとえば友達であれば、一度連絡先を交換しておけば、習い事を辞めた後でも一緒に遊ぶことはできます。
しかし先生の場合、その習い事の場でしか会えないケースが多く、子どもにとっては「辞める=もう会えない」という不安につながることもあります。
「友達や先生に会いたい」という気持ちがモチベーションとしてプラスに働いているうちは問題ありませんが、もし習い事そのものに対するやる気がなくなってきている場合は、「行きたくない」という気持ちのほうが強くなってしまうこともあります。
理由③ 先生の教え方や雰囲気が合わない
どんなに習い事自体が好きでも、先生の教え方や雰囲気が合わないと、「行きたくないな…」という気持ちになりやすくなります。
- 厳しすぎて緊張してしまう
- 怖くて気軽に質問できない
- 逆にゆるすぎてつまらなさを感じる
こうした相性の問題は、子ども自身では言葉にしにくいものです。
「どうして行きたくないのか」に寄り添って聞いてあげると、少しずつ本音が出てくることもあります。
理由④ 成績・競争へのプレッシャー
習い事によっては、発表会や大会、検定試験などの「成果を求められる場面」があります。それ自体が悪いわけではありませんが、子どもにとっては大きなプレッシャー。
「失敗したらどうしよう」
「期待に応えたいけど自信がない」
そんな不安から「今日はちょっと気が重い…」という気持ちになることがあります。
特にまじめな子ほど、強く感じやすい傾向があります。
理由⑤ 習い事と学校の両立で疲れている
毎日学校に通って、そのあと習い事に行く。それだけでも子どもにとっては十分ハードです。最近は小学生でもスケジュールがびっしり、ということも珍しくありません。
「好きなんだけど、体がついていかない…」
「やりたいけど、今日は疲れすぎてムリ…」
そんなふうに、気持ちと体力のギャップが「行きたくない」に表れることも多いのです。
理由⑥ 練習が嫌い、でも成果は手放したくない
「試合に出たい」
「発表会でほめられたい」
「みんなの前でかっこよく見せたい」
そんな思いがある一方で、「そのための練習は正直しんどい…」と感じる子も少なくありません。
努力は大変だけど、やめてしまうと今まで積み上げたものがなくなるような気がして、それもイヤ。そんな「面倒くささ」と「もったいなさ」の間で揺れているのが、まさにこのパターンです。
理由⑦ やめた後の「損した感」が怖い
これは少し大人びた感情ですが
「ここまで頑張ったのに、やめたら意味がない気がする」
「辞めたら損しそう」
という「損失回避」の気持ちも、意外と多くの子どもが持っています。
習い事で得た技術や経験は、目に見える成果として残るだけに、やめる=すべてを失うように感じてしまうことも。「やめたい」よりも「やめるのが怖い」という心情が強く出るケースです。
習い事に行きたくないと言われたときの親の対応法

子どもから突然、「もう習い事に行きたくない」と言われたら、親としては驚いたり、戸惑ったりするものです。

せっかく今まで続けてきたのに…
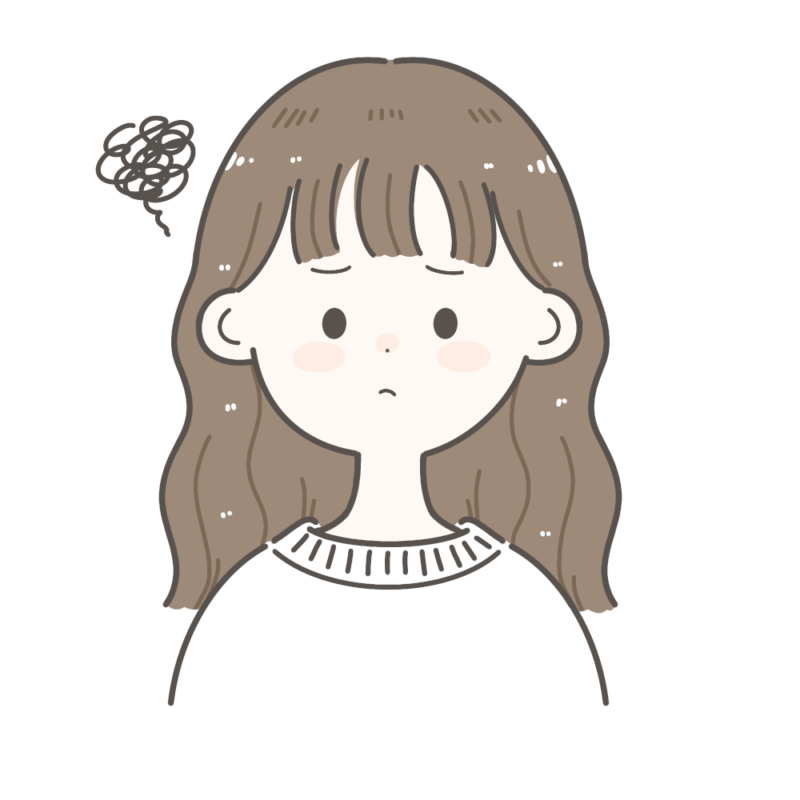
言うとおりにやめさせたら、わがままになってしまうかも…?
と、不安になる方も多いでしょう。
でも、そんなときこそ大切なのは「どうリアクションするか」です。
ここからは、子どもの気持ちに寄り添いつつ、冷静に判断するための基本的な対応法を紹介します。
怒らず受け止め、まずは話を聞く
まず大前提として、「行きたくない」と言われたときに 怒ったり否定したりしないことが何より大切です。
子どもは、理由がはっきりしていないまま「なんとなく行きたくない」と感じることもよくあります。
そんなときに「なんでよ!」「そんなのダメでしょ!」と頭ごなしに否定されてしまうと、本音を話せなくなってしまいます。
「そうなんだ。どうしてそう思ったのか、少し教えてくれる?」
「疲れてるのかな?何かあった?」
こんなふうに、まずは「話を聞く姿勢」を見せるだけで、子どもは安心して自分の気持ちに向き合えるようになります。
一時的に休ませて様子を見るのもアリ
「辞めたい」と言われたとき、すぐに結論を出す必要はありません。
状況によっては、「ちょっとお休みしてみようか」と提案してみるのも一つの方法です。
とくに、体力的に疲れていたり、学校行事などで忙しかったりする時期は、一時的に「習い事に行きたくない」と感じやすいもの。そんなときは、少し間を置くだけで「また行きたくなってきた」と気持ちが戻ることもあります。
親としても、「やめる」か「続ける」かの二択ではなく、「休む」という選択肢があると気が楽になりますね。
子どもの「頑張りすぎ」に気づく視点
子どもが「行きたくない」と言い出したとき、それは「もう限界」のサインかもしれません。習い事に真面目に取り組んでいる子ほど、自分から「つらい」と言い出せないことも多いです。
「うちの子、ちょっと頑張りすぎてたのかも」
「知らないうちに、親の期待がプレッシャーになってたかも」
そんなふうに、大人の側が一歩引いて見直す視点も大切です。
無理に続けさせるより、「よく頑張ってたね」「ちょっと休んでも大丈夫だよ」と声をかけることで、子どもも安心できます。
習い事の目的を再確認する声かけ例
習い事をする目的は、子どもや家庭によってさまざまです。
「楽しいから」
「上手になりたいから」
「将来の夢のために」
でも、続けているうちにその目的を忘れてしまい、「なんのためにやってるんだっけ?」と感じることもあります。
そんなときは、こんな声かけをしてみましょう。
- 「〇〇を始めたとき、どんな気持ちだった?」
- 「あのとき、すごく楽しそうにしてたよね」
- 「これからどうなったら嬉しいって思う?」
子どもと一緒に原点を思い出すことで、「じゃあもう少し頑張ってみようかな」と思えることもあります。
逆に、目的が変わったり、興味が移ったと感じたら、無理に続けなくてもよいかもしれません。
子どもが「行きたくない」と言ったときは、成長の節目であり、親子で見直すチャンスでもあります。あわてて判断するのではなく、気持ちに寄り添いながら、ゆっくり方向性を探っていきましょう。
【状況別】行きたくないけど辞めたくない子どもへの対処法
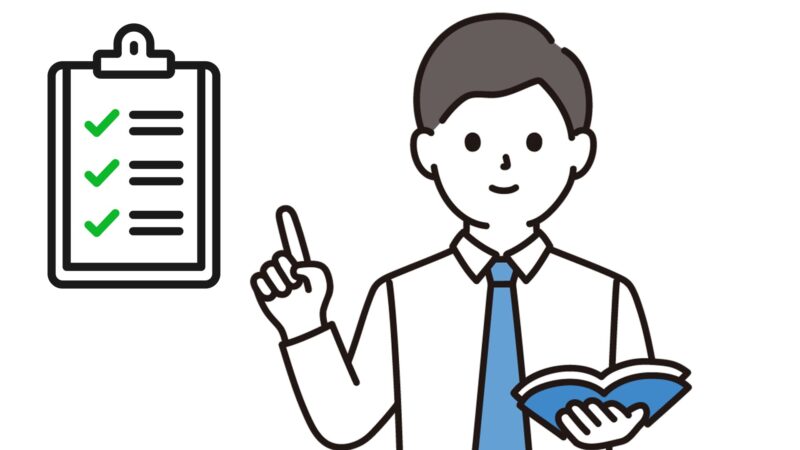
子どもが「行きたくない」と言いながらも「辞めたくない」と感じているとき、その背景にはさまざまな理由が隠れています。
一人ひとり違う事情があるからこそ、状況に応じた対応が大切です。
ここでは、よくあるケースをもとに、親ができる具体的なサポート方法を紹介します。
先生や友人が原因で気が進まない場合
習い事の内容そのものではなく、「先生が怖い」「友達とケンカした」など、人間関係が理由で行きたくなくなることはよくあります。
この場合は、無理に慣れさせようとせず、環境を少し変えてみることが有効です。
- 同じ教室でも曜日を変えてみる(先生やメンバーが変わることも)
- グループではなく個別指導に切り替える
- いったん距離を置き、他の子と接点が少ないタイミングを選ぶ
「やめる」のではなく「ちょっとずらす」ことで、子どもの負担がぐっと減ることもあります。
習い事自体は好きだが練習は苦手な場合
「〇〇は好きだけど、練習がめんどくさい」
「結果は出したいけど、努力するのはしんどい」
そんな「子どもあるある」の気持ちには、練習のハードルを下げる工夫がおすすめです。
- 短時間に区切る(例:10分だけ練習→休憩)
- 遊び感覚を取り入れる(例:タイムアタックやごほうびシール)
- 一緒にやってみる(親子でチャレンジしてみる)
「頑張りなさい!」より、「ちょっとだけやってみる?」と声をかける方が、子どもは前向きになりやすいです。
体調・気分の不調からくる一時的な拒否の場合
疲れがたまっていたり、体調が万全でなかったりすると、子どもは自然とやる気が出なくなります。特に、小学校中学年〜高学年以降は、思春期に入る影響で気分が不安定になることもあります。
この場合は、まず生活リズムを見直すことが大切です。
- 睡眠時間が足りているか
- 食事が偏っていないか
- 学校生活が忙しすぎないか
子どもが「疲れた」「なんか行きたくない」と言ったときは、甘えではなく体のサインかもしれません。休ませることで回復するケースも多いので、気になるときは早めに休養を取らせましょう。
理由がはっきりしないけど様子がおかしい場合
「なんとなく元気がないけど、理由は言いたがらない」
「話しかけても黙ってしまう」
そんなときは、無理に聞き出そうとせず、間接的に気持ちを表現できる方法を試してみましょう。
たとえば…
- 「今の気持ち」を話すのではなく紙に絵で書いてもらう
- 気持ちの温度を「10段階スケール」で表してもらう(例:「今日はやる気3くらい」)
- お気に入りの先生や第三者(スクールカウンセラーなど)に相談してもらう
子どもが自分の気持ちを言葉にするのが難しいとき、「話す以外の方法」で気持ちを整理することが大切です。
子どもが「行きたくない」と言う理由は、一つに絞れないことが多いものです。
でも、親が状況に応じた柔軟な対応をすることで、子ども自身も気持ちを整理しやすくなります。
「この子にとって何が一番良い形だろう?」と考えながら、無理なく続けられる方法を一緒に見つけていきましょう。
子どもの「辞めたくない」は本心?見極めポイント

子どもが「もう行きたくない」と言いつつ、「でも辞めたくない」と言い張るとき、親としてはその言葉をどう受け止めるべきか迷いますよね。
この「辞めたくない」という言葉、本当に子どもの本心でしょうか?
もしかすると、親の期待や周囲の目を気にして出た言葉かもしれません。
ここでは、「子どもの本音を見極めるための視点」について、具体的に解説します。
自分の意思なのか、親への気遣いなのか
一見、前向きなように聞こえる「辞めたくない」という言葉ですが、その裏に親への気遣いが隠れているケースは少なくありません。
- 「お父さんが頑張ってお金払ってるから…」
- 「お母さんが応援してくれてるから…」
- 「やめたら怒られるかも…」
子どもなりに親の期待や苦労を感じ取り、本当は辞めたいけど、言えずに我慢していることがあります。
こんなときは、
「やめても、お父さんは怒らないよ」
「本音を話してくれるだけでうれしいよ」
といった安心できる言葉を先に伝えることが大切です。
「やめたら後悔するかも」の心理とは
子どもが辞めることに迷いを感じている場合、
「やめたら損するかも」
「後悔するかも」
という不安が根っこにあることもあります。
- 「ここまで続けたのにもったいない」
- 「また始めるのが大変そう」
- 「ほかの子に遅れたくない」
これは大人にもある「損失回避」で「今あるものを手放すのが怖い」という気持ちです。
そんなときは、
「やめたって大丈夫」
「続けるより、やめることで見えることもあるよ」
と、辞めても安心と思える選択肢を提示してあげることが効果的です。
子どもが「辞めたくない」と言ったとき、そのまま鵜呑みにせず、「それって本当にやりたいから? それとも誰かのために我慢してるの?」とやさしく気持ちを探ってあげることが大切です。
子どもの言葉の奥を、信頼関係のなかで少しずつ見つけていきましょう。
習い事は「継続」か「見直し」か?判断の分かれ道
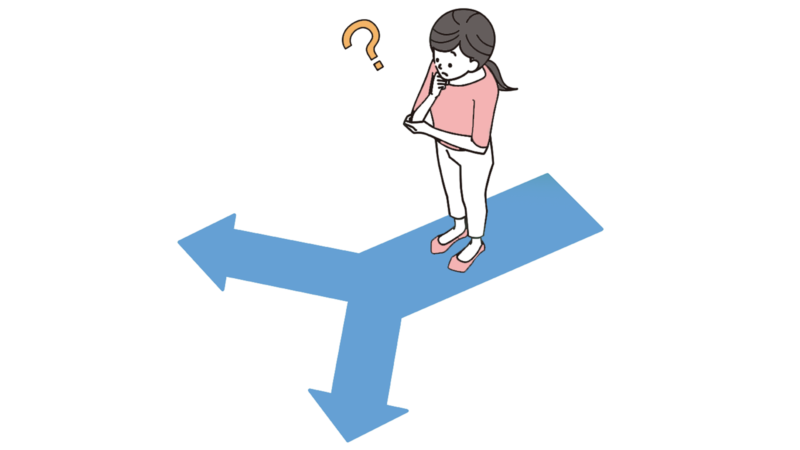
子どもが「行きたくない」「でも辞めたくない」と言ったとき、親として悩むのが「このまま続けさせるべき?それともやめさせる?」という判断です。
一度始めたことをやめるのは、なんとなく
「もったいない」
「逃げグセがつくのでは」
と心配になるかもしれません。
でも、続けるにせよ辞めるにせよ、子どもと親が納得したうえでの選択であれば、それはどちらでも前向きな経験になります。
ここでは、辞めるか続けるかを判断するうえで知っておきたいポイントを紹介します。
辞めたあとに得られるもの・失うもの
まず前提として、「やめる=失敗」ではありません。
もちろん、これまでの努力やお金、時間などが無駄になったように思えることもあるでしょう。
でも、やめたことで初めて気づけることや、心が軽くなる感覚もあるのです。
たとえば…
- 「やめてみたら、実はそんなに好きじゃなかったと気づいた」
- 「放課後に余裕ができて、他のことを楽しめるようになった」
- 「別の習い事に興味が出てきた」
このように、辞めたあとに新しい道が開けることもよくある話です。
だからこそ、「辞める=マイナス」と決めつけず、プラスの側面にも目を向けましょう。
続けさせるより「納得させる」選択を
「せっかく始めたから」と親が無理に続けさせようとしても、本人の気持ちが追いついていなければ意味がありません。
たとえ続けても、イヤイヤ通うだけでは得られるものは少なく、自己肯定感も育ちません。
それよりも大事なのは、子ども自身が「自分で選んだ」と納得していること。
- 「やめてもいいよ」と言われて、「やっぱり続けたい」と思う
- 「一度休んでみて、やっぱり行きたくなった」と戻る
こうした体験は、子どもにとって自己決定の練習になります。
親は「続けるかどうか」ではなく、「納得して選べたかどうか」に目を向けてみてください。
習い事の「やめどき」とはいつ?判断基準を持とう
「やめたほうがいいのかな…」と迷ったときは、いくつかのポイントをチェックしてみましょう。
やめどき判断のための視点
- 本人の意志:本音で「もうやりたくない」と感じていないか?
- 成長や変化:以前は楽しんでいたのに、最近は様子が違っていないか?
- 伸び悩み:明らかに成長が止まっている or ストレスが強い
- 他に興味が出てきた:新しいことに意欲を持ち始めている
- 生活リズムが崩れている:疲れや不機嫌が目立つようになった
これらを総合的に見て、子どもにとって今の習い事が「必要」か「負担」かを見極めていきましょう。
習い事の継続・見直しは、正解がない分、親にとっても難しい選択です。
でも、「どっちを選んでも大丈夫」と思えるように、親子で納得できる話し合いを重ねることが何より大切です。
次の一歩を、子どもと一緒にゆっくり決めていきましょう。
まとめ:子どもの気持ちに寄り添った柔軟な対応を
子どもが「習い事に行きたくない、でも辞めたくない」と感じるのは、心の中にいろんな感情が同時にあるからです。
大人でも、仕事をする上で嫌なことがある日もあれば、楽しい日もありますよね。
やめたい気持ちと続けたい気持ちが、揺れ動いているのは自然なことです。
だからこそ、親は「どうしたいの?」と正解を急がせるのではなく、「どんな気持ちなのかな?」と寄り添う姿勢が大切です。
そして、続ける・辞めるのどちらを選ぶにしても、子ども自身が納得できるプロセスを一緒に考えていくことが、成長の土台になります。
親自身も「こうあるべき」と思い込みすぎず、柔軟な心で子どもの声に耳を傾けていきましょう。
子どもの迷いに寄り添う経験は、親にとっても育児の学びとなるはずです。焦らず、ゆっくり、親子で歩んでいきましょう。