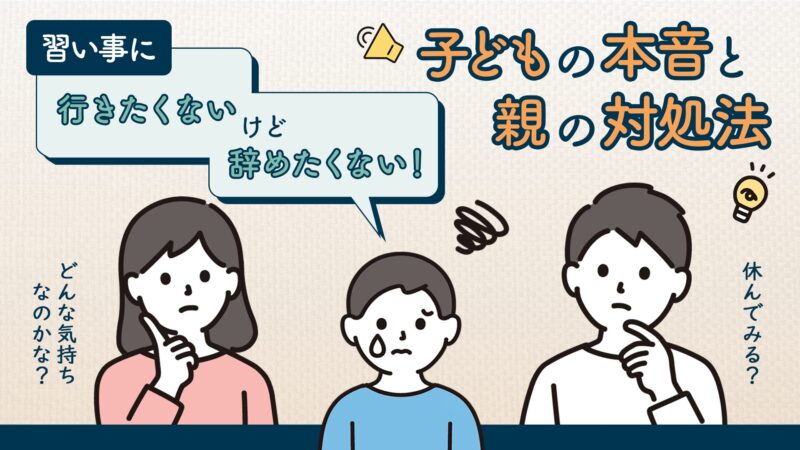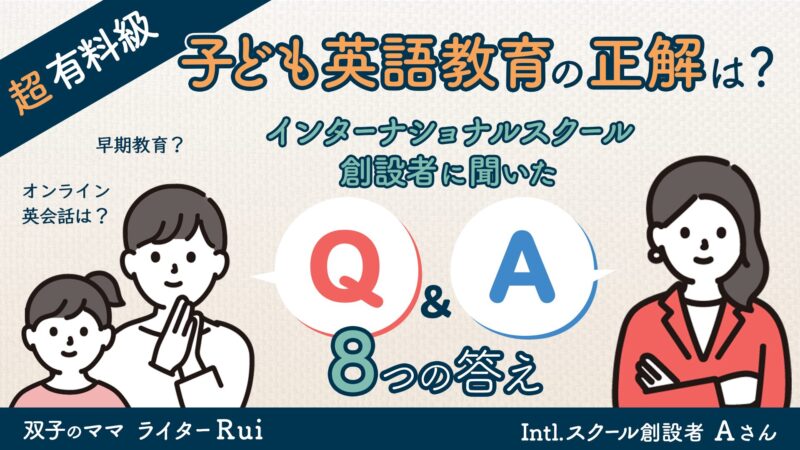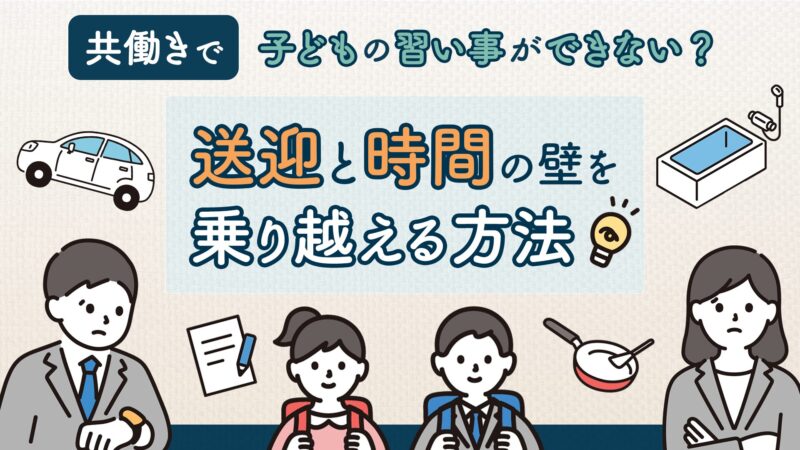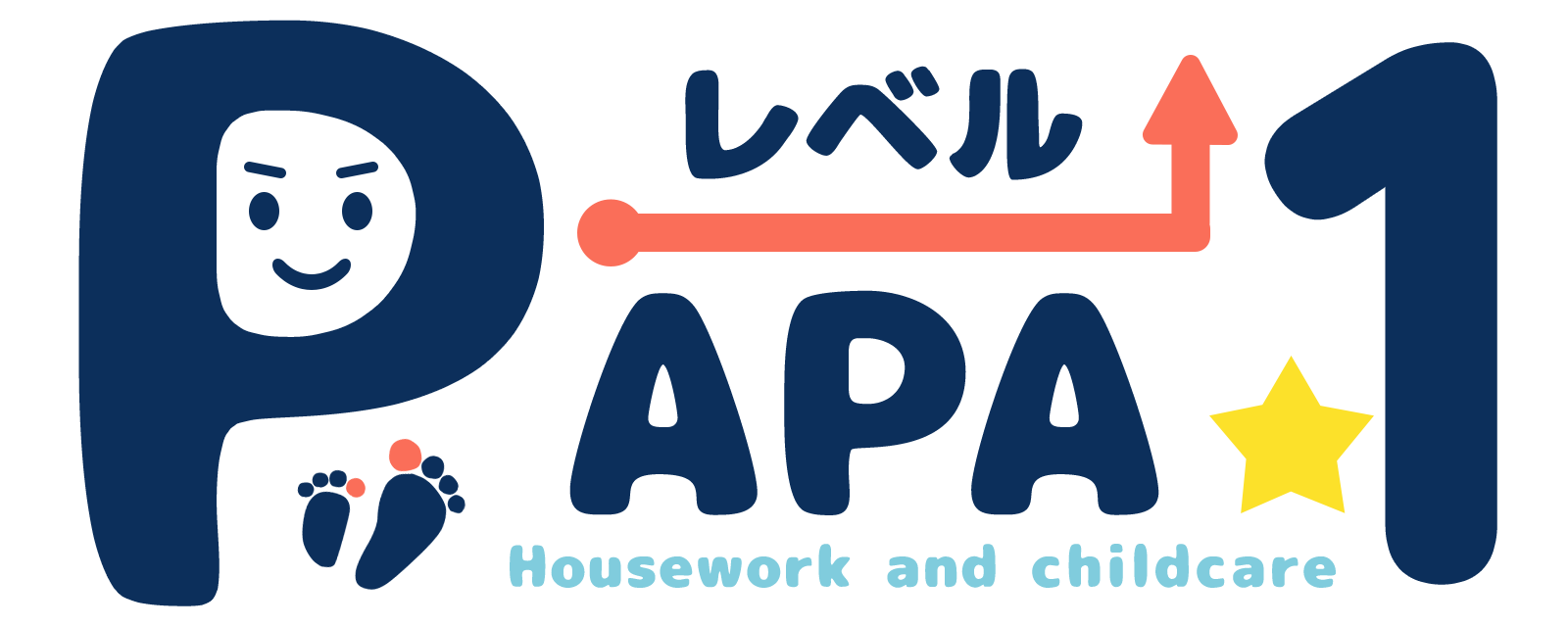共働きで子どもの習い事ができない?送迎・時間の壁を乗り越える方法
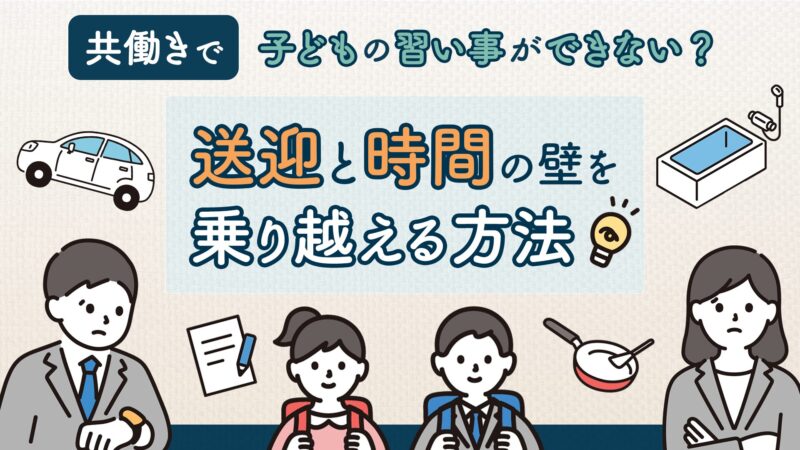
「子どものために、何か習い事をさせてあげたい」けど、いざ夫婦共働きの現実と向き合うと、「うちには無理かも…」と感じてしまうこと、ありませんか?
- 仕事が終わる頃には教室が閉まっている
- 送迎の時間を確保するのが難しい
- 普段の練習や準備に寄り添う時間がない
「本当はやらせてあげたいのに、できていない」そんなもどかしさや罪悪感を抱えているパパママも少なくありません。
でも実は、ちょっとした工夫と環境づくり次第で、共働きでも無理なく習い事を続けられる方法はあります。忙しい共働きだからこそ知っておきたい、「効率的な習い事の始め方」を一緒に考えてみましょう。
- 共働き家庭が習い事を諦める理由は?
- 共働き家庭で習い事をするにはどんな工夫が必要?
- 共働きでもできる習い事はある?
子どもの習い事の選び方については、こちらでまとめていますので、あわせてご覧ください。
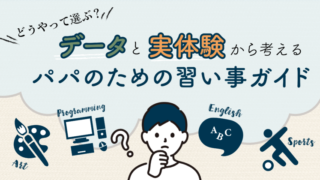

mizuno(Webライター)
公立・大学図書館で8年間勤務した元司書。
育児歴10年の経験を活かし、完璧を目指さない「楽しむ子育て」を発信中です。
共働き家庭が習い事を「できない」と感じる主な理由
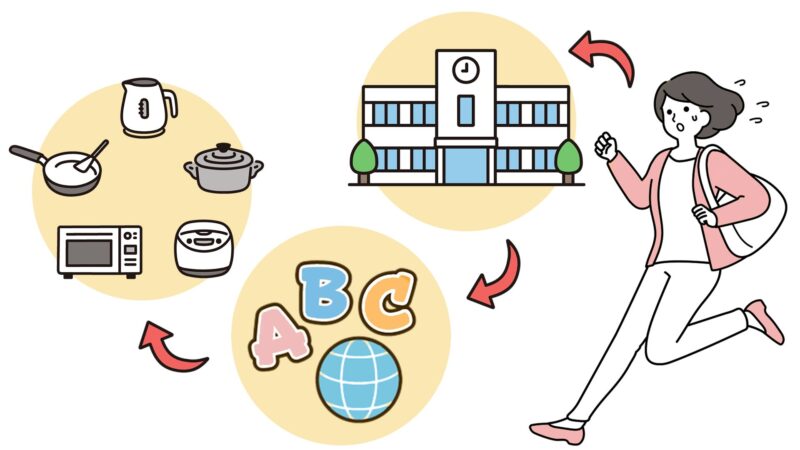
1. 送り迎えができない―平日も週末も、時間が足りない
共働き家庭にとって、「送迎の壁」はかなり高いものです。
平日は朝から夕方まで仕事。やっと仕事を終えて帰宅する合間に、子どもを学童から迎えて、さらに習い事の教室まで連れて行く…という流れは、現実的にかなりハードです。
移動にかかる時間や天候、下の子の世話なども考えると、「とてもじゃないけど無理!」と感じるのも仕方がありません。
「じゃあ土日ならどうか」と思っても、休日は休日でスケジュールがいっぱいになりがち。
- 平日にできなかった掃除や買い出し
- 家族で楽しくお出かけ
- 自分の休息やリフレッシュ時間
気がつけば1週間のうち、習い事にあてられる時間がない…ということもよくあります。
2. 親の時間・体力・気力が足りない ― やらせたい気持ちと現実のギャップ
習い事をさせたい気持ちはある。子どもの可能性を広げてあげたい…でも、余裕がない。
そんな「気持ち」と「現実」のギャップに悩んでいる親御さんも少なくありません。
仕事を終えて家に帰れば、そこからすぐに夕飯の準備、お風呂、宿題の声かけ、寝かしつけ…。自分の時間なんてほとんどなく、一日を走りきるだけで精一杯。
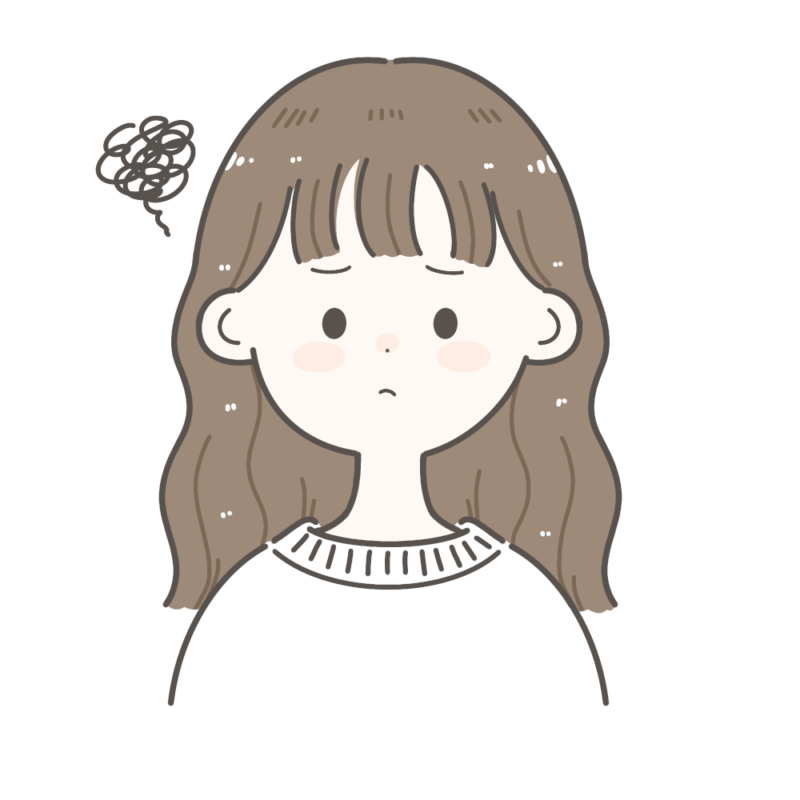
やらせてあげたい気持ちはあるけど、正直そこまで余裕がない…
というのが正直な本音ではないでしょうか。
育児初心者のパパにとっては、慣れない家事・育児と仕事の両立だけでも大変。
その上で「習い事の送迎や準備」まで背負うのは、なかなかのハードです。
3. 子どものスケジュールが詰まっている
意外と見落としがちなのが、子ども自身の忙しさです。
放課後は学童に行き、家に帰ったら宿題、その後はご飯、お風呂、寝る準備…と、子どもの一日も大人顔負けのスケジュール。
「習い事」まで加えるとなると、かなりハードな日々になってしまいます。
楽しく学んでもらいたくて始めた習い事も、子どもが疲れていたり気持ちに余裕がなければ、「行きたくない」「なんかつまんない…」と感じてしまうことも。
せっかく習い始めたのに、疲れやストレスで逆効果になってしまうのは、親としても避けたいところですよね。
4. 習い事を続けられるか不安
「興味があるって言ってたから習わせたのに、数回で『もうやめたい』って言い出した…」
こんな経験、意外と多いものです。
習い事には費用も時間もかかりますし、「続かなかったらどうしよう」という不安は誰にでもあります。
「せっかく頑張って調べたのに…」「無駄になるのは避けたい…」という気持ちが強く、最初の一歩がなかなか踏み出せないこともあります。
また、子どもが「やめたい」と言ったときにどう対応するかも、悩みどころ。
「甘やかしになるのでは?」「でも無理に続けさせても逆効果かも…」と、判断に迷う瞬間も出てきます。
共働き家庭の習い事の悩み

発表会や大会への参加が負担になる
習い事には、「発表会」や「大会」といったイベントがつきものです。
- バレエは、年に1回の大きな舞台発表
- ピアノは、ホールで演奏会やコンクール
- サッカーや水泳などのスポーツ系は、週末に行われる対戦試合
など、「がんばる目標がある」のはとても良いこと。でも、その裏で支える保護者の負担も決して小さくありません。
イベント前には、衣装の準備や必要な道具の買い出し、時には衣装の手作りをお願いされることもあります。
大会や発表会が遠方で開催される場合、仕事の休みを確保して、当日の送迎や付き添いを調整する必要も出てきます。
また、参加費や交通費、衣装代など、通常の月謝とは別に出費が増えることも珍しくありません。

本人が頑張っているから応援したいけど、働きながらだと正直かなりきつい…
という声も多く、特に共働き家庭にとっては「がんばるチャンス」が「続けにくさの壁」になってしまうケースもあるのです。
練習の付き添いや当番制があると、仕事の調整が難しい
チームスポーツや団体活動系の習い事では、保護者に「当番制」や「練習の付き添い」が求められることがあります。たとえば、
- 「〇月〇日は保護者見守り当番をお願いします」
- 「練習時の引率係を交代で担当してください」
- 「試合の際は、車を出して移動の協力を…」
といった形で、保護者同士の助け合いが求められる仕組みです。
もちろん、地域やチームによってルールは異なりますが、当番や付き添いが必須の場合、共働きの家庭ではかなり大きな負担になります。
仕事のスケジュールを調整して平日に時間を空けるのは簡単ではありませんし、「どうしても参加できない」となれば、気まずい思いをすることも。
「仕事で無理なのに、断るたびに申し訳なさそうな空気になる…」というストレスを抱える方も多いのが実情です。
他の保護者との関わりも、気軽ではないと感じる
「習い事そのもの」よりも、「他の保護者との関わり」が心理的な負担になるケースもあります。たとえば、
- 送迎の場で、他の保護者同士が仲良さそうに話しているのを見て気後れしてしまう
- あいさつをしても反応が薄く、「ここにいていいのかな…」と不安になる
- 子ども同士は仲が良いのに、親同士の関係がぎくしゃくしている気がする
など、「保護者の輪に入りづらい」と感じてしまうと、それだけで通わせるのが憂うつになることもあります。
特に付き添いや当番で関わる機会が少ないパパママは、「どうふるまえばいいのかわからない」と戸惑ってしまいがちです。
また、チームスポーツのように「保護者同士の協力」が前提になっている習い事では、その関わり自体が精神的な負担に感じてしまう人も少なくありません。
共働きでも習い事はできる!現実的な工夫と環境づくり

ここまでの内容を読んで、「うちは共働きだし、やっぱり習い事は難しいのかも……」と不安になったパパママもいるかもしれません。
たしかに、共働き家庭にとって習い事は決して気軽な選択肢ではありません。でも、やり方次第で無理なく取り入れることは十分可能です。
忙しい日常の中で「できる工夫」や「頼れる手段」を取り入れれば、習い事は家庭の負担にならず、子どもの成長を応援できる素敵な時間になります。
ここでは、現実的に続けやすくなる方法や環境づくりの工夫をご紹介します。
1. 「宿題が終わってから習い事」を基本ルールに
共働き家庭で大切なのは、子どもが自分で動ける習慣を早めに育てておくこと。
その第一歩が、「宿題が終わったら習い事」というルールです。
とくに小学校低学年のうちは、放課後の流れが毎日同じになるようにしておくと安心です。
① 学校(学童)
↓
② 帰宅
↓
③ 宿題
↓
④ おやつ・休憩
↓
⑤ 習い事
↓
⑥ 夕食・入浴
↓
⑦ 就寝
このようにリズムを決めておけば、子ども自身も何をすべきかわかりやすく、親も「夕方にバタバタするかも…」という心配が減ります。
また、「宿題を終えたら楽しいことが待っている」という流れを繰り返すことで、自然と自主性も育まれます。
2. ご飯の作り置きや時短家事で「夕方の余裕」をつくる
共働き家庭の夕方は、まさに戦場のように忙しい時間帯。
仕事から帰ってきて、夕食の準備、洗濯、片付け、子どもの対応…すべてを完璧にやるのは本当に大変です。
だからこそ、「がんばりすぎない工夫」が習い事の継続を支えるカギになります。
- 週末に冷凍おかずや作り置きをしておく
- 炊飯+メイン1品+汁物だけを定番化する
- レトルトやミールキット、宅食サービスを使う日に決める
- 掃除・洗濯は最小限でOKと割り切る
など、手を抜くところは遠慮なく抜いていきましょう。
「少しでも夕方に余裕があると、子どもとゆったり向き合える」それが結果的に、子どもにとっても良い時間になります。
3. パートナーや家族と協力して送迎・準備を分担する
送迎や準備を一人で抱え込まないことも、とても大切なポイントです。
つい「自分がやらなきゃ」と思ってしまいがちですが、夫婦や家族で役割分担すれば、グッと現実的になります。
- 「平日はママ、週末はパパが送迎」と曜日で分担する
- 「朝のうちに荷物を準備しておいて、夜はすぐ出発できるようにする」
- 「祖父母に送迎をお願いする代わりに、習い事の様子をビデオで共有する」
など、ちょっとした協力と工夫で、負担が半分以下になることも。
特に初心者パパにとっては、「送迎をやってみる」「準備を一緒にやる」ことで、子どもの習い事に主体的に関わるチャンスにもなります。
家庭のチーム力がぐっと高まり、良い循環が生まれるはずです。
パパが習い事に参加することのメリットについて、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
4. 地域のファミリーサポートや民間送迎サービスを使う手も
「どうしても送迎が難しい」「親のどちらも動けない日がある」というときは、外部のサポートを利用するのも賢い方法です。
- 自治体が運営する「ファミリーサポート(ファミサポ)」では、子育て支援者が送り迎えや一時預かりを有料で行ってくれます。
- 民間の子ども向け送迎サービスでは、スタッフが自宅から習い事まで安全に送り迎えをしてくれるサービスも増えています。
「人に頼るのは申し訳ない…」と思う必要はありません。頼れる仕組みを活用するのは、家庭をまわすための前向きな選択です。
子どもにとっても、毎日忙しく疲れている親の姿よりも、「頼れる大人たちに囲まれて安心できる環境」のほうが、よほど安心できることもあります。
ママ友と送迎を分担するのはアリ?共働き家庭が気をつけたいポイント

習い事の送迎が難しいときに「ママ友と送迎を分担する」という選択をする人もいます。
たしかに、お互い助け合えば負担が減るようにも思えますが、実はちょっとしたきっかけで人間関係がぎくしゃくしたり、思わぬトラブルにつながったりすることも。
ママ友と送迎を分担するメリット
ママ友と協力して送迎をすることで得られるメリットもたしかにあります。
- 平日の送迎回数を減らせる
- 自分が忙しい日は代わってもらえる
- 友達と一緒に通えるので楽しめる
ですが、こうした助け合いは、うまくいっているときこそ気づきにくい落とし穴もあります。
実はトラブルも多い?ママ友送迎のデメリットと注意点
1. 負担の偏りで不満がたまりやすい
送迎の回数や手間に偏りが出ると、「私ばっかり…」と感じるように。相手が言い出さないだけで、不満がたまっていることもあります。
2. 急な予定変更に対応しづらい
仕事の残業や子どもの体調不良など、予期せぬ予定変更はつきもの。そのたびに「今日はお願いできる?」と頼むのは気が引けますし、断る側も気まずさを感じがちです。
3. 子ども同士の関係に気を遣う
子ども同士がケンカをしてしまったり、どちらかが習い事を辞めたくなったときなど、送り迎えを通じて親も影響を受けることがあります。
4. 万が一のトラブル時、責任の所在があいまい
送迎中にけがをした場合や事故に巻き込まれたとき、誰に責任があるのかは非常にデリケートな問題です。事前に取り決めをしていても、感情的なトラブルに発展するケースもあります。
ママ友との送迎分担をおすすめしない理由
こうした背景から、ママ友との送迎分担は「気軽に始めるべきではない」といえます。
家庭ごとに生活リズムや価値観が異なる中で、「助け合い」がいつしか「押し付け合い」に変わってしまうことも。
うまくいけば助け合いになりますが、一度関係がこじれると回復が難しい側面もあります。特に、日常的・長期間にわたって続けるのはおすすめできません。
親子のために始めた習い事が、いつしかストレスの元になってしまっては本末転倒です。
「自分たちの家庭にとって無理なく続けられる形は何か?」を考え、ファミリーサポートセンターの利用や、オンラインの習い事を検討するなど、安心して取り組める方法を選びましょう。
習い事をあきらめない!共働きでもできる選び方とは?

習い事をあきらめてしまいそうになる場面でも、視点を変えたり環境を少し整えたりすることで、ぐっと現実的になることも。
ここからは、共働きでも取り入れやすい習い事の例を見ていきましょう。
1. 土日や夕方遅めの時間帯を狙おう
共働き家庭にとって、平日の夕方は一番忙しい時間帯。仕事を終えて帰宅し、ご飯の支度やお風呂、宿題チェックなど…めまぐるしいですよね。
そんな中で習い事を入れるのは正直きついものです。そこでおすすめなのが、「土日」や「夕方18時以降」に開講しているレッスンです。
- 土曜の午前中に体操教室
- 日曜の日中にスイミング
- 平日でも19時開始のオンライン教室
といったように、家族のスケジュールに合わせてフレキシブルに対応できるレッスンを選ぶと、無理なく続けられます。
休日であればパパとママで交代制にするなど、送迎の負担を分担しやすくなるのもポイントです。
2. 自宅や学童の近くで、送迎の手間を減らす
「通うだけで片道30分以上かかる…」となると、親の負担はかなりのものに。
そこで大事なのが、「場所選びの工夫」です。
- 自宅や学校、学童の近く
- おじいちゃん・おばあちゃんの家の近所
- 通勤ルートの途中にある施設
など、日常の移動範囲内で完結できる場所を選ぶと、送迎や見守りの負担がグッと減ります。
慣れてくれば子ども一人で通えるようになる可能性もあり、少しずつ「自立心」も育っていきます。
3. オンライン習い事なら送迎ゼロでOK!
移動の手間を完全にゼロにしたい方にとって、今やオンラインレッスンは強い味方。
自宅にいながらZoomなどのツールで先生とつながり、リアルタイムでレッスンが受けられます。
- 英語・プログラミング・ピアノ・そろばん など、ジャンルも多彩
- 親がそばにいられる安心感がある
- 費用を抑え、短時間で集中して取り組める
「送迎できないから無理」と感じていたご家庭でも、オンラインなら親のサポート範囲で完結できるのが魅力。
子どもの性格との相性により、ハマると毎日でもやりたがる子も少なくありません。
4. 短時間で終わるレッスンを選ぶのもコツ
習い事=週1〜2回、毎回90分以上…というイメージがあるかもしれませんが、最近は短時間・高効率なレッスンも増えています。
- 30〜60分で終わる個別指導
- 幼児〜小学生向けに集中力を考慮した短時間レッスン
- オンラインで30分だけのミニ英会話
など、子どもの集中力が続きやすい時間設定のものもたくさんあります。
短時間だからこそ、気軽に始められて、スケジュールの中に無理なく組み込みやすいのがメリットです。
5. 家まで来てくれる「出張型」も検討を
送迎が難しい家庭にとって、「先生が来てくれる」という出張型レッスンは非常に助かる選択肢です。
- ピアノやバイオリンなどの音楽教室
- 英語や家庭教師のような学習サポート
- リトミックやアートなど
家でレッスンを受けられるので、下の子がいるご家庭や、寒冷地・悪天候が多い地域でも安心です。普段の環境の中で学べることで、子どももリラックスしてレッスンに取り組めます。
6. 民間学童や保育園の「習い事つき」サービスを活用
近年、放課後や保育時間中に習い事ができる民間の学童や保育園が急増しています。共働き家庭にとって、これはまさに「預かり+習い事」のいいとこ取り。
送り迎えやスケジュール調整の手間を省きつつ、子どもの学びの機会をしっかり確保できるということで、非常に注目されています。
放課後の時間を有効活用!「習い事つき」民間学童の魅力
例えば2024年には、大阪メトロ(Osaka Metro)子育て支援事業として、「習いごとができる学童保育」をスタートさせ、大きな話題となりました。
【参考】えすこーとOsaka Metro 都島駅前校 | 民間学童保育のえすこーと
この学童では、放課後の時間にただ子どもを預かるだけでなく、「英語・プログラミング・書道・絵画・算数」などの習い事を学童の中で受けられる仕組みになっています。
つまり、子どもが学童にいる時間にそのまま習い事も完結するため、親が仕事終わりに別の場所へ送り迎えする必要がなくなります。
忙しいパパママにとっては、時間と労力を大幅に節約できるとともに、「今日は習い事があるからお迎え時間が早くなる」といったスケジュール管理のストレスも軽減されます。
保育園でも「おけいこ保育」の拡大傾向
また、学童だけでなく、未就学児を対象とした保育園でも「習い事つき」のサービスが増えています。
いわゆる「おけいこ保育」と呼ばれる取り組みで、保育の一環として次のような習い事を取り入れる園が増えています。
- リトミック(音楽+運動)
- 英語あそび
- 体育教室(マット運動や体操など)
- 絵画・工作
- そろばんや数字遊び
子どもの好奇心を育てながら、家庭ではなかなか難しい専門的な体験を日常的に提供してくれるのが魅力です。
こちらも保護者にとっては、「仕事で忙しい中でも、子どもにいろいろな体験をさせられる」という安心感があります。
全国的に広がる「習い事付き」保育園・学童
こうした取り組みは、首都圏だけでなく、全国の民間学童や保育施設で少しずつ導入が進んでいます。
特に都市部では共働き家庭のニーズが高く、「夕方にもうひとつ予定を入れるのは難しい」「送迎がないと続けられない」といった現実的な声を背景に、習い事は預かり時間に済ませたいという家庭が増加。
- 教育系企業が運営する民間学童(例:英語学童、プログラミング特化型学童)
- 習い事教室と提携した保育園
など、さまざまなスタイルのサービスが登場しています。
共働き家庭におすすめ!「毎週通わない」習い事
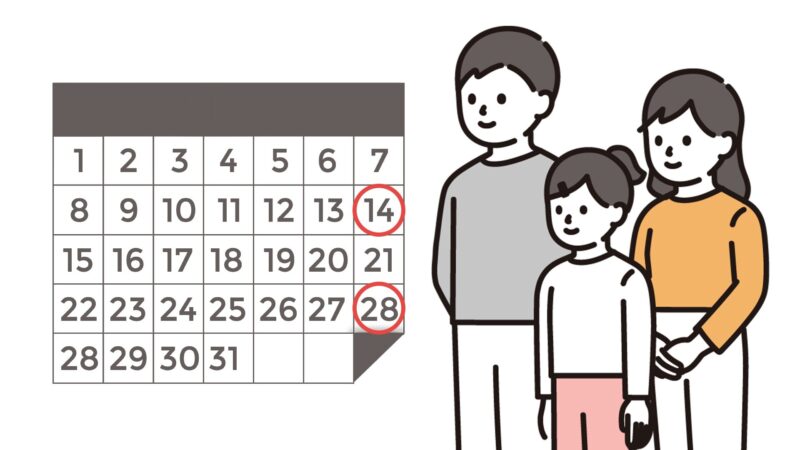
習い事と聞くと、「毎週決まった時間に教室へ通う」「親が送迎するのが当たり前」というイメージが強いですよね。
いまどきは、そんな固定観念にとらわれなくてもいいんです。
最近では、共働き家庭でも続けやすい「通わない習い事」や柔軟に参加できるスタイルが増えています。
ここでは、忙しい家庭でも取り入れやすい、「毎週通わなくてOK」な習い事のスタイルをご紹介します。
1. 自宅でできるオンライン習い事を選ぶ
まずおすすめなのが、オンラインで完結する習い事。必要なのは、インターネット環境とパソコンやタブレットだけ。Zoomなどのビデオ通話ツールを使って、自宅にいながらリアルタイムのレッスンを受けられます。
- 英会話
- プログラミング
- ピアノやギター
- そろばんや作文指導 など
30分〜60分程度の短時間レッスンが主流なので、夕食前のスキマ時間や土日の空き時間にぴったり。子どもが一人で受けられる年齢であれば、パパママのサポートも最小限で済みます。
「今日は無理そうだな」というときも、振替や録画受講ができるサービスがあると安心です。忙しい日々の中でも、習い事を生活の一部に取り入れやすいのが大きな魅力です。
2. 土日だけ or スポット参加できる教室を探す
「毎週通うのは難しいけれど、月に1〜2回なら行けそう」というご家庭には、スポット参加型の教室がおすすめです。
- 土日限定の短期クラス
- 予約制の1回完結レッスン
- 休日のイベント型ワークショップ
など、家庭の予定に合わせて自由に参加できるスタイルなら、仕事や行事に左右されずに済みます。
特に、芸術系(アート、工作、音楽)、スポーツ体験、科学実験、アウトドア教室などでは、非日常感も楽しめる習い事として人気です。
「今日は家族でお出かけしたい」「来月は忙しいからお休みしたい」といった希望にも柔軟に対応できるため、「続けなきゃ」「来週もいかなきゃ」というプレッシャーが少ないのも大きなメリットです。
3. 短時間でも集中できるプログラムを選ぶのがコツ
通う頻度が少なくても、内容がしっかりしていれば十分に効果を感じられます。
そこで大切なのは、短時間でも密度の濃いレッスン内容を選ぶこと。
- 1回30〜60分で達成感が得られる内容か?
- 子どもの集中力や性格に合っているか?
- 「楽しい!」と思える工夫がされているか?
などをチェックしてみてください。
また、先生との相性や教材の工夫も大切なポイント。初回無料体験やお試しレッスンなどを活用し、「またやりたい!」という気持ちが自然に湧くかどうかを見てみましょう。
オンラインでできる!共働き家庭におすすめの習い事

「送迎がいらない」「時間を選べる」「自宅でできる」――オンラインでできる習い事は、共働き家庭にとってとても便利で、家事や仕事と両立しやすい選択肢です。
忙しい日々でも、子どもの学びをサポートできるオンライン習い事の魅力を、人気のジャンルとともに紹介します。
1. オンライン英会話
現在、英語教育の重要性が高まる中で、多くの共働き家庭に人気があるのがオンライン英会話です。
特に、小学校で英語の授業が本格的に始まる前に、英会話に親しませたいというパパママにおすすめです。
- レッスン時間:1回25分〜の短時間で、夕食前や寝る前などのスキマ時間にぴったりです。
- 講師の選択肢:外国人講師や日本人講師が選べるため、子どもの英語レベルに合わせて安心してスタートできます。
レッスンを受けるたびに「英語って楽しい!」と感じることで、自然に英語への興味が深まります。
オンライン英会話に興味がある方は、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
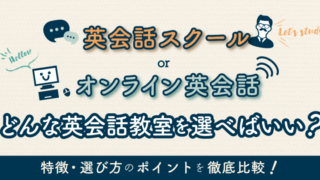
2. オンラインプログラミング
昨今、プログラミング学習は非常に注目を浴びています。
特に、小学生向けのプログラミング学習は、子どもたちが楽しみながら未来のITスキルを身につけられる絶好の機会です。
- ゲームと連動:マイクラ(Minecraft)やロブロックスといった人気のゲームを使ったコースがあり、ゲーム感覚で学ぶことができます。
- 学びの楽しさ:パズル感覚で学べる教材が多く、子どもが夢中になって取り組むことが特徴です。
- 保護者の負担が少ない:オンラインで完結するので、親のサポートは最小限で済みます。
プログラミングを学ぶことで、創造力や論理的思考を養うことができ、今後の成長に大きな力になります。
オンラインプログラミングに興味がある方は、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
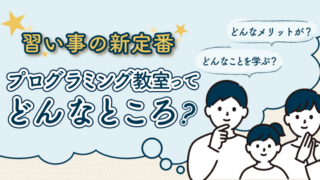
3. その他のおすすめオンライン習い事
オンラインそろばん
暗算力や集中力を高めるのに効果的なオンラインそろばんは、カメラ越しで先生から個別に指導を受けることができ、家庭でじっくり学べます。
オンラインピアノ・楽器レッスン
ピアノや他の楽器を自宅で楽しめるオンラインレッスンもあります。自宅にある楽器を使って、マンツーマンでレッスンを受けられるため、送迎不要で続けやすいと好評です。
オンラインアート・図工
工作や絵画などをオンラインで学べるアート・図工もおすすめです。
材料キットが送られてくるサービスも多いため、準備の手間が少なく、すぐに始められます。手を動かしながら創造力を育てることができます。
オンラインでの習い事は、時間・場所・内容の自由度が高く、「忙しいけれど学びの機会を持たせてあげたい」という家庭にとって、非常に便利で続けやすい方法です。自宅でできるため、子どもの学びを支えつつも、家事や仕事との両立がしやすく、家族みんなの負担を軽減します。
実際どう?共働き家庭の体験談:習い事を続けられる理由
ここでは、実際にSNSで語られている各年代におけるパパ・ママの意見を紹介します。
「オンラインの習い事で送迎のストレスなし」
平日は仕事が終わるのが遅く、教室への送迎は現実的に無理でした。でもオンラインなら家にいながら習い事ができるので、親の負担が激減。子どもが自分でPCを立ち上げて始めてくれるので、準備もスムーズです。
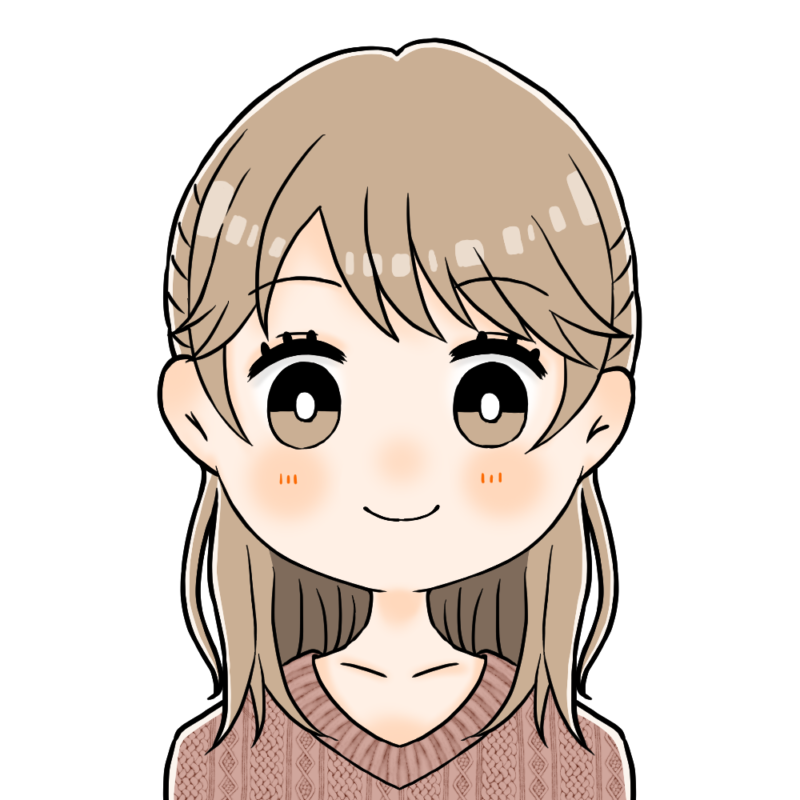
「送り迎えの時間は夫婦でシフト制に」
小2の娘がピアノと英語を習っています。送迎がネックでしたが、平日のピアノは妻、土曜の英語は私というふうにスケジュールを組んでなんとか続けられています。Googleカレンダーで家族間共有しておくと、抜け漏れも防げて便利です!

「学童のあとにそのまま通える教室を選択」
共働きで時間が限られているので、学童の近くにある英語教室を選びました。学童からそのまま歩いて行ける距離なので、移動の手間が少なくて助かっています。教室側も慣れていて、学童から来る子が多いようです。
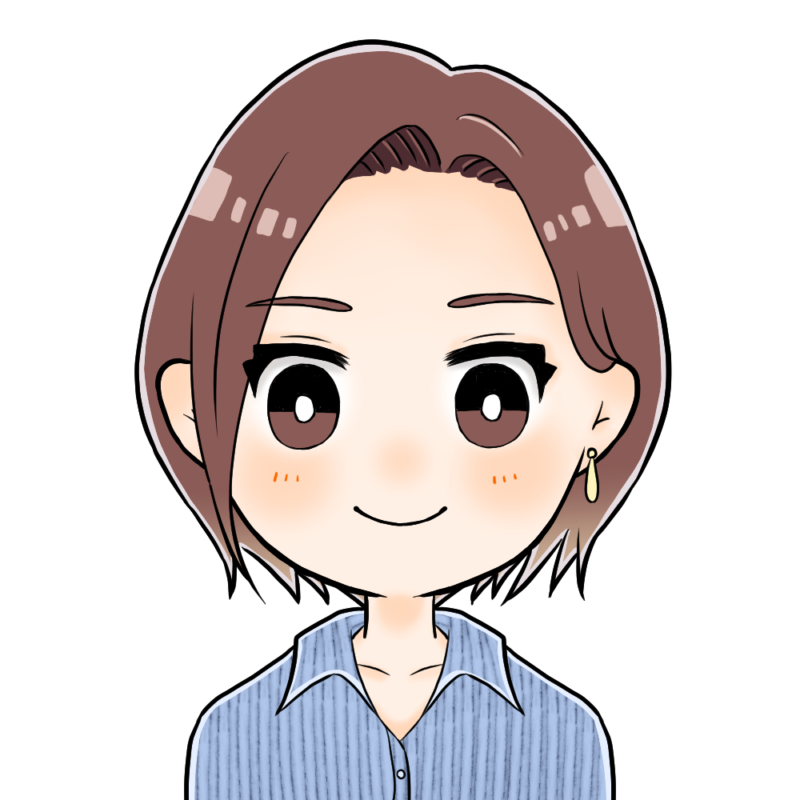
「土日だけの教室を選んだことで負担が減少」
平日は送迎できないため、土日限定で通えるダンス教室を選びました。毎週ではなく、月2回コースにして無理なく通っています。発表会も希望制で、無理せず参加できるのが我が家には合っていました。

自治体サービス、選択する習い事の特徴、お仕事のスケジュールにより、各ご家庭の状況は多岐に渡りますが、時代背景の変化やIT技術の発展により、取り得る手段もまた拡大しています。
時間がないことを理由に後ろ向きになるのではなく、子どもの将来のために「何かうまくできることはないか?」を考えてみましょう。
共働きでも習い事はできる!環境と工夫で「できない」が「できる」に
共働き家庭が子どもの習い事を続けるには、まず「生活リズムを整えることが土台」になります。宿題を習慣化し、時短家事や家族の協力で親の負担を減らすことが、習い事の時間と心の余裕を生み出します。
送迎や時間の壁を乗り越える方法はさまざま。無理のない範囲で、家庭に合ったスタイルを選んで「できる形」で習い事を取り入れていきましょう。