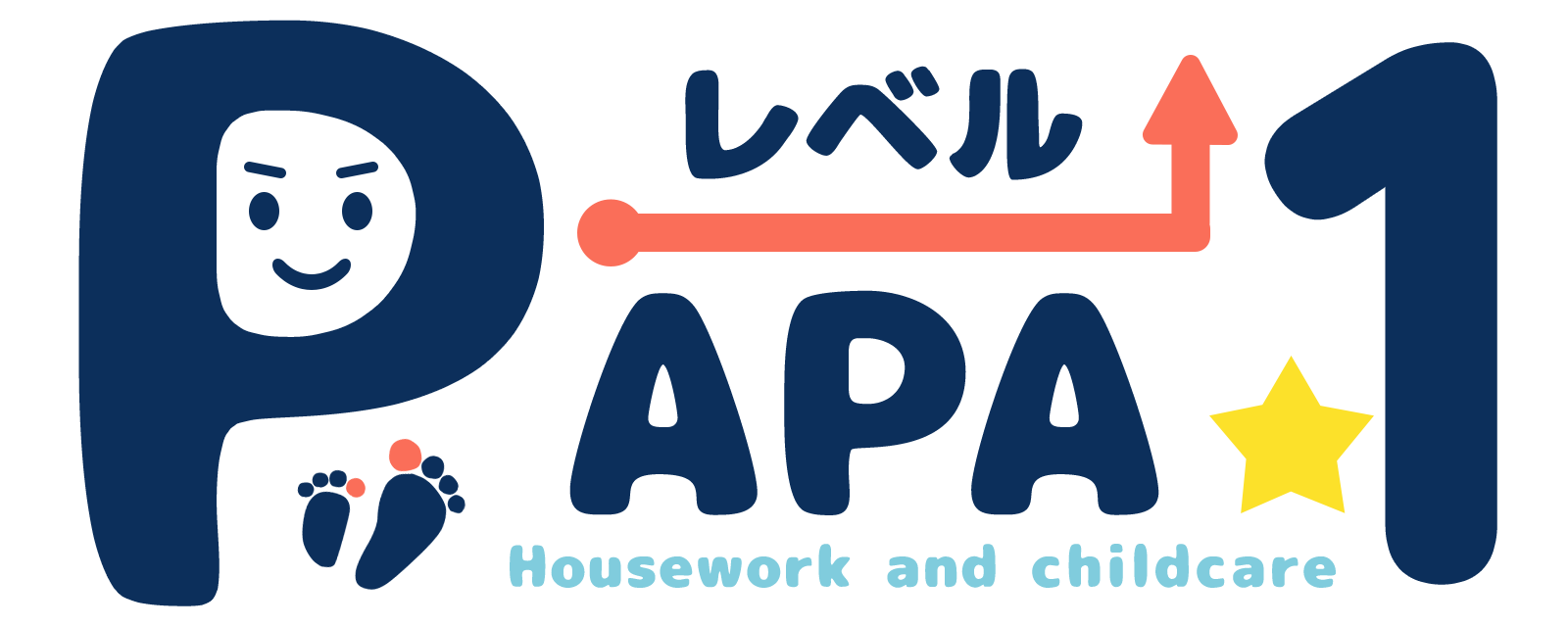【助産師解説】SIDSを心配しすぎて寝れない|知っておきたい知識と5つの予防策
赤ちゃんが寝ているとき、「ちゃんと息しているかな…」と気になって、つい何度も確かめてしまう。
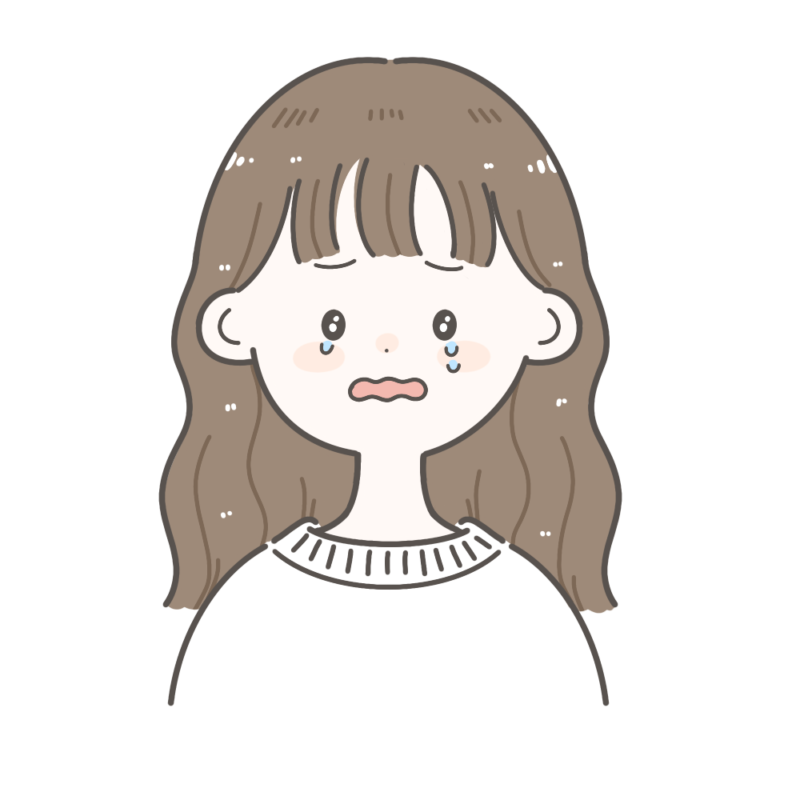
寝たい。でも、心配で眠れない…
そんなふうに悩んでいませんか?
赤ちゃんの突然死症候群(SIDS)は、誰にとっても不安に感じるものです。
大切なわが子を思うからこそ、「目を離してはいけないのでは」と感じて眠れなくなってしまう…。
これは決して珍しいことではありません。
私も助産師として12年間、多くのご家族と向き合ってきましたが、「SIDSが怖くて眠れない」という声は本当にたくさん聞いてきました。
そして実は、私自身も第一子のときは同じ気持ちで、夜が怖くて眠れず、何度も赤ちゃんの胸の上下を確認してはようやく安心する…そんな日々を過ごしていました。
だからこそお伝えしたいのは、不安を感じるのはあなただけではないということ。
正しい知識やできる対策を知ることで、その不安を少しずつ和らげていくことができます。
この内容が、パパやママの気持ちを軽くし、赤ちゃんとの毎日を少しでも安心して過ごせる助けになればうれしいです。

助産師りず
助産師・12年以上の病院勤務経験をもつ3児の母。
4歳と2歳と0歳の子育て経験と助産師での経験を活かし、初心者パパの育児を全力でサポートします。
SIDS(乳児突然死症候群)とは?

SIDS(乳幼児突然死症候群)とは、元気に見えていた赤ちゃんが、眠っている間に突然亡くなってしまう現象のことをいいます。
発症するのは主に生後1年未満。
とくに生後6か月までの赤ちゃんに多く、その中でも3か月前後が最も多いとされています。
実際に、SIDSで亡くなった赤ちゃんの約6割が、風邪や軽い気管支炎にかかっていたという報告もあります。(参照:京都大学医学部 SIDS)
厚生労働省の統計によると、SIDSで亡くなる確率は0.1%ほど(2021年データ)。
つまり、めったに起こることではありません。
(参照:厚生労働省 人口動態統計)
それでも、「もし我が子に起きてしまったら…」と考えると、不安になってしまいますよね。
令和4年には47名の乳幼児がSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因の第4位となっています。
(参照:子ども家庭庁 SIDS)
残念ながら、現在の医学ではSIDSの原因はまだ特定されていません。
だからこそ、「絶対に防ぐ」ことは難しくても、リスクを下げるための予防策をとることがとても大切になります。
ここからは、SIDSのリスクや予防につながる具体的なポイントについて、わかりやすくご説明していきます。
SIDSを予防するためにできること|5つのポイント

SIDSは原因がはっきりしていません。
しかし、これまでの研究から「発症リスクを下げる行動や環境づくり」がわかってきています。
ここでは、今日からできる5つの予防ポイントを紹介します。
知っておくことで過度に心配せず、安心して赤ちゃんとの時間を過ごせるようになりますよ。
1.環境を整える(寝かせ方・寝具・服装)
仰向けで寝かせる
最も大切なのは、赤ちゃんを必ず仰向けで寝かせることです。
うつ伏せは呼吸がしにくく、気道がふさがって窒息の危険が高まります。
特に首がすわる前の赤ちゃんは自分で体勢を変えられないため、必ず仰向けで寝かせましょう。
窒息を防ぐ寝具の工夫
- 枕やぬいぐるみ、柔らかいおもちゃは置かない
顔を覆って窒息する可能性があります。ベビーベッドは赤ちゃんだけのスペースに。余計なものは一切置かないようにしましょう。 - ベッド柵は必ず上げる
柵が下がっていると隙間に挟まったり転落する危険があります。
寝返りをしない時期でも、足を動かして思わぬ位置に移動することがあるので注意が必要です。 - 固いマットレスを使う
柔らかい布団は顔が沈み込み、窒息のリスクが高まります。
ベビー用の固めマットレスを選ぶと安心です。
ベビー布団の選び方については、こちらで詳しく解説しています。
服装の工夫(温めすぎない)
赤ちゃんを冷やしたくない!とつい厚着をさせたり布団をかけたりしがちですが、温めすぎは逆にSIDSのリスクを高める要因になります。
室温は大人が快適に感じる温度に保つのが目安。
特に寝返り前は背中に熱がこもりやすいので注意しましょう。
寒い季節は掛け布団の代わりにスリーパーを使うと、顔に布団がかからず安心です。
2. できるだけ母乳で育てる
母乳には、SIDSのリスクを下げる効果があるといわれています。
- 眠りが浅くなりやすい
→母乳育児の赤ちゃんは眠りが浅く、呼吸が乱れたり異常があったときに目を覚ましやすいと言われています。 - 免疫成分が含まれている
→感染症を防ぐ力があるため、体調の悪化を防ぎ、結果的にSIDS予防にもつながります。
ただし、母乳育児が難しい場合もあります。
そのときは「できる範囲で取り入れれば十分」。
ミルク育児でも、他の予防策を守ることでリスクは減らせますので安心してください。
(参照:母乳育児とSIDS)
3. タバコをやめる(受動喫煙も含めて)
タバコは、SIDSの最大のリスク要因のひとつです。
赤ちゃんが苦しくても起きられなかったり、呼吸を立て直せなかったりすることが、SIDSのリスクにつながります。
さらに、ニコチンの影響で軽い風邪でも悪化しやすくなるとされており、風邪がSIDSの引き金になる可能性もあります。
たとえママが吸っていなくても、パパや家族の喫煙によって部屋や衣服に残った煙(三次喫煙)でも赤ちゃんは影響を受けます。
ある研究では、両親ともに喫煙する家庭ではSIDSリスクが約5.77倍になると報告されています。
(参照:産後の両親の喫煙)
4. 起きているときの工夫(タミータイム)
首や体の発達を促す
タミータイム(Tummy Time)とは、赤ちゃんが起きているときにうつ伏せで過ごす時間のこと。
いつから?どのくらいやればいい?
赤ちゃんによっては、最初うつ伏せを嫌がることもあります。
でも、少しずつ慣れると視界が広がり、興味を持って遊ぶようになります。
絵本を見せたり、おもちゃで誘ったり、笑顔で声をかけたりして、遊び感覚で楽しい時間にしてあげましょう。
タミータイムは、日中の運動習慣と夜の安心した睡眠リズムづくりにもつながります。
安全に配慮しながら、親子で楽しく取り入れてみてください。
(参照:Tummy Time for a Healthy Baby、Back to Sleep,Tummy to Play
5. 補助アイテム(無呼吸アラーム)の活用
赤ちゃんのSIDSが心配で「夜も眠れない…」と不安になるパパ・ママも少なくありません。
そんなときに検討されるのが、市販の「無呼吸アラーム(ベビーモニター)」です。
無呼吸アラームとは?
無呼吸アラームは、赤ちゃんの呼吸や体の動きを感知し、一定時間(例:20秒以上)反応がないとアラームで知らせてくれる機器です。
赤ちゃんの呼吸状態を監視し、万が一の事態にいち早く気づくための「補助アイテム」として使われます。
- マットレスタイプ
ベッドの下に敷き、体動を感知する - 装着タイプ
赤ちゃんの体に直接センサーをつけ、呼吸や動きをモニタリングする
いずれも「異変に気づくための補助ツール」であり、SIDSを完全に防ぐものではありません。
メリットとデメリット
無呼吸アラームは、SIDS予防の補助的な役割であり、「切り札」ではないということを理解しておくことが大切です。
購入を迷ったときの判断ポイント
無呼吸アラームは必須ではありません。
検討するときは、以下のような「不安の強さ」を目安にしてみましょう。
- 夜中に何度も確認してしまい、ほとんど眠れない
- 赤ちゃんと離れて寝ることに強い不安がある
こうした場合は、導入で気持ちが軽くなる可能性があります。
一方で、すでにSIDS予防策(仰向け寝・寝具管理・禁煙など)を徹底していれば、必ずしも必要ではありません。
アメリカ小児科学会(AAP)は「市販機器がSIDSを減らすというデータはない」と明言しています。
(参照:Sleep-Related Infant Deaths)
私自身も3人子育てをしましたが、メリット・デメリットを比較して購入は見送りました。
「少しでも安心したい」という気持ちが強い方には選択肢になりえますが、過度に期待せず「安心材料の一つ」として活用してください。
家庭の状況や価値観に合わせて、無理のない範囲で判断することが大切です。
SIDSに関するよくある質問

ここでは、パパ・ママから特によく聞かれる3つの質問に、わかりやすく答えます。
Q1:添い寝は絶対にダメ?
A. 添い寝そのものがSIDSの直接の原因ではありません。
ただし、窒息や体温上昇などのリスクが高まるため注意が必要です。
厚生労働省も「原則として赤ちゃんはベビーベッドで寝かせること」を推奨しています。
特に疲れて深く眠るときは添い寝は避けましょう。
Q2:赤ちゃんが寝返りできるようになったら?
A. 赤ちゃんが自分で寝返りできるようになると、仰向けに寝かせても自然にうつ伏せになることがあります。
この場合、無理に仰向けに戻す必要はありません。
大切なのは 「寝返りしても安全な環境を整えておくこと」 です。
- 顔が埋もれないよう、硬めのマットレスを使用する
- 枕・ぬいぐるみ・大きな布団などは置かない
つまり、環境が整っていれば赤ちゃんは自分で安全に眠ることができます。
(参照:SIDS予防)
Q3:「心配しすぎて夜眠れない」のですが…?
A. SIDSを心配して眠れないのは、決してあなただけではありません。
不安を感じるのは、赤ちゃんを大切に思っている証拠です。
ただし、強い不安が続くとパパ・ママ自身の心身に負担がかかります。
- 正しい知識を確認する
すでに予防策を実践できていることを自分にしっかり伝える。 - 不安を声に出す
パートナーや信頼できる人に話すことで気持ちが軽くなる。 - 専門家に相談する
小児科医・助産師・保健師に相談して正しい情報を得る。 - 完璧を目指さない
できる範囲の予防策を行ったら、赤ちゃんの生命力を信じる。
赤ちゃんの安全を守りたいと願う気持ちは、とても尊いものです。
「私は今できることをやっている」と、自分をねぎらうことも忘れないでくださいね。
まとめ

SIDS(乳児突然死症候群)への不安は、多くのパパやママが感じる自然な気持ちです。
ただ、正しい知識を持ち、できる予防策を取り入れることで、その不安はぐっと軽くなります。
特に「睡眠環境を整える」「生活習慣を見直す」といった工夫は、今日からでも始められる実践的な方法です。
もちろん、すべてを完璧にこなす必要はありません。
大切なのは「できることから少しずつ取り入れること」です。
少しずつでも実践することで、赤ちゃんだけでなく、パパやママ自身にも安心が生まれます。
赤ちゃんのことを思い、夜も眠れないほど心配してしまうのは、それだけ真剣に育児に向き合っている証拠。
その気持ちは必ず赤ちゃんに伝わり、何よりの愛情となっています。
どうか一人で抱え込まず、専門家や信頼できる人に相談しながら、赤ちゃんとの毎日を安心して過ごしてくださいね。