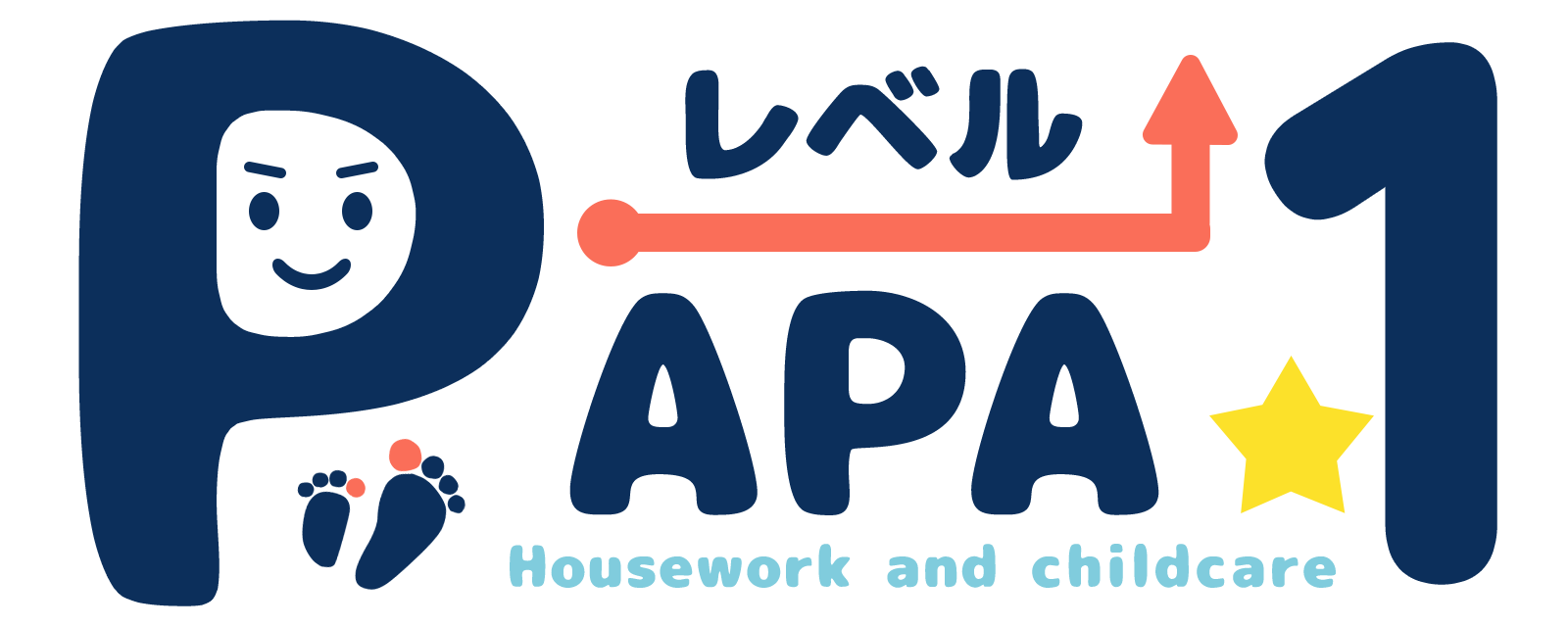【助産師解説】友達がいなくて子育てに孤独を感じる|乗り越えるための6つの方法
無事に出産を終え、ようやく待ち望んだ赤ちゃんとの生活が始まりました。
ほっとひと息つけたのも束の間、これからはいよいよ育児のスタート。
楽しみな気持ちと同時に、不安も押し寄せてきます。
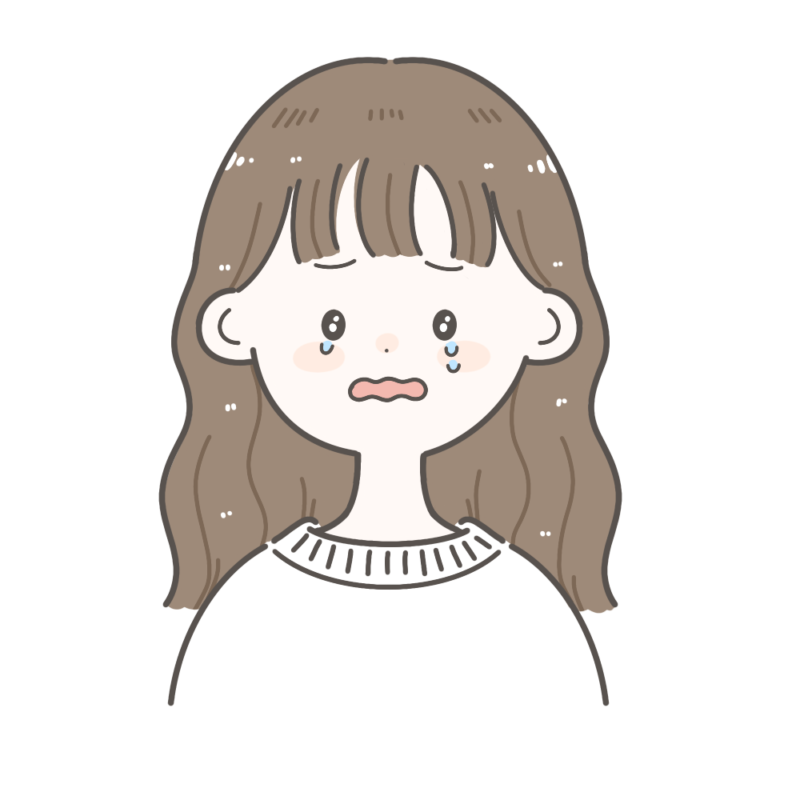
自分のつらさを誰もわかってくれない…
気軽に話せる相手がいない…
そんなふうに感じて、社会から切り離されてしまったような孤独感に苦しんでいませんか?
この記事では、育児中に感じやすい“孤独”を和らげるための具体的な方法をご紹介します。
育児の中で本当に大切なのは、ママやパパ自身の心が満たされていること。
心が落ち着き、安心して過ごせると、自然と余裕が生まれ、赤ちゃんとの時間をもっと楽しめるようになります。
悩みを一人で抱え込まずに、あなたらしい子育てを少しずつ見つけていきましょう。

助産師りず
助産師・12年以上の病院勤務経験をもつ3児の母。
4歳と2歳と0歳の子育て経験と助産師での経験を活かし、初心者パパの育児を全力でサポートします。
育休中に感じやすい「孤独感」とは?

育休中のママが抱える「孤独感」には、いくつもの要因が重なっています。
出産後は赤ちゃんと家で過ごす時間がどうしても長くなり、職場や社会とのつながりが薄れてしまいます。
大人同士の会話が減ることで、心のバランスを崩しやすくなるのです。
さらに、ホルモンバランスの変化や生活リズムの乱れも重なり、精神的な負担が大きくなります。
話し相手がいなくなるつらさ
育休に入ると、これまで毎日顔を合わせていた同僚や友人とのコミュニケーションが少なくなります。
家族以外と話す機会が減ると、社会とのつながりを感じられず、心に大きな影響を与えます。
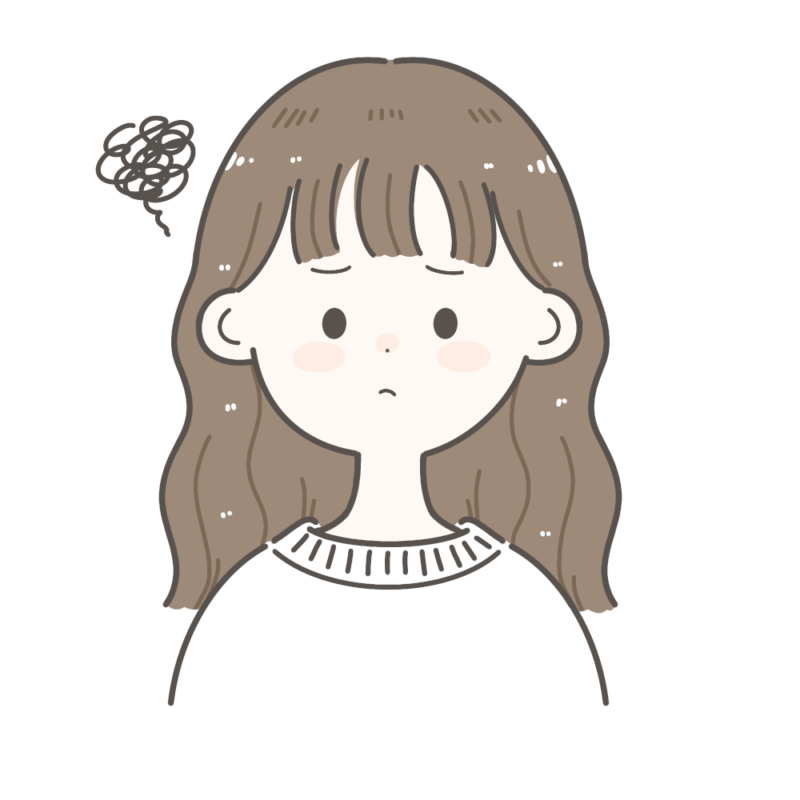
同僚は今も職場で働いているし、自分が抜けた分の負担を抱えているかもしれない…。
そんなふうに思うと、育児の悩みを気軽に相談しづらく感じてしまいます。
また、学生時代の友人も独身で仕事に忙しく、だんだん温度差を感じて連絡が遠のくことも。
結果、赤ちゃんと2人きりの時間が増え、大人同士のやりとりが極端に少なくなってしまいます。
私自身もワンオペ育児の時期があり、夫の帰りが遅い日は「大人と話すのが一言二言だけ」という日が続き、とてもつらい思いをしました。
研究では、専業主婦や若いママの方が、社会とのつながりが薄くなることで孤独を感じやすいと指摘されています。(参照:育児ストレス構造の研究)
外出すらハードルに…赤ちゃんとふたりきりの生活
赤ちゃんを連れての外出は、想像以上に大変です。
荷物の準備や天候の確認、授乳室の有無など気を配ることが多く、出かけるだけでも一苦労です。
「外出先で泣いたらどうしよう…」という不安もあり、気軽に友達とお茶に行くことも難しくなります。
結果、家にこもりがちになり、大人と話す機会が減ってしまいます。
産後ホルモンの影響と気持ちの揺れ
出産後はホルモンバランスの急激な変化で気分が落ち込みやすくなります。
特に性ホルモンの急減は、情緒不安定の大きな要因といわれています。(参考:出産前後の性ホルモン変化と「産後うつ」との関連)
この心の揺れに育児の不安や疲れが重なると、孤独感が一層強まることもあります。
大切なのは「自分を責めないこと」。
まずは「今はそういう時期なんだ」と受け止めることです。
昼夜逆転の生活リズムによる疲労
赤ちゃんのお世話は昼夜を問わず続きます。
夜間授乳やオムツ替えで眠りが細切れになり、慢性的な睡眠不足に陥りやすいです。
疲れがたまると、ちょっとしたことでも大きなストレスに感じ、孤独感を強めてしまいます。
ある研究では、体調に余裕が出てくるとママの気持ちが安定し、赤ちゃんにも穏やかに接しやすくなると報告されています。(参照:産後の疲労感)
「ママ友がいない=ダメ」ではない理由

「ママ友がいない」と感じると、どこか劣等感や不安を抱くことがあります。
SNSで楽しそうな様子を見ると、つい比べてしまうこともあるでしょう。
でも、実際はママ友がいなくても問題なく子育てしている人がたくさんいます。
無理に交友を広げようとして、かえってストレスになるケースも少なくありません。
ここでは「ママ友がいない=ダメ」という思い込みを手放し、育児の孤独期を少しでも前向きに過ごすヒントをお伝えします。
ママ友がいなくても、子どもに悪影響はない
「ママ友がいないと子どもが寂しいのでは…」と心配する方がいますが、基本的には心配いりません。
子どもは保育園・幼稚園・公園などで自然に友達を作っていきます。
むしろ大事なのは、ママが穏やかに過ごせること。
それが子どもの安心感につながります。
ママ友の多さにとらわれず、まずは自分と子どもの時間を大切にしましょう。
孤独な育児は「少数派」ではない
育児で孤独を感じるのは特別なことではありません。
実際、日常の中で「話し相手がいない」「頼れる人がいない」と感じている人は多いです。
SNSには楽しそうな投稿が目立ちますが、現実はもっと複雑です。
ある調査では、子育て中の約67.1%の方が孤独感を感じているという結果もあります。(参考:子育て女性の7割超が孤立感)
この事実を知るだけで「自分だけじゃない」と気持ちが楽になることがあります。
ママ友が少ないことのメリット
ママ友が少ないことには、意外とメリットもあります。
人間関係は気を使うことが多く、無理な付き合いはかえってストレスになります。
育児中は心身の余裕が少ないため、交友関係を広げるよりも、自分のペースで子どもと向き合う時間を持つ方が穏やかな育児につながります。
ママ友がいなくても頼れる支援・サービス
現代は核家族が多く、昔のように近所や親戚が自然に支えてくれる環境が少なくなっています。
厚生労働省の「令和6年度雇用均等基本調査」によると、令和6年度に子どもが生まれた女性のうち、育休を取得した人の割合は86.6%でした。これに対し、パパが育休を取得した人の割合は、40.5%です。
パパの育休取得率は徐々に増えているものの、パパ以外のサポートがあまり見込めない現代において、まだまだ少数といえます。(参照:令和6年度雇用均等基本調査)
そのため、自治体や地域のサービス、オンライン相談窓口など、公的・民間の支援を活用することが重要です。ひとりで抱え込まず、利用できる社会資源を味方につけましょう。
子育て支援センター・保健センターを味方に
各自治体の子育て支援センターや保健センターは、育児相談や発達チェック、親子イベントを行っています。
専門スタッフがいて、授乳やおむつ替えのスペースもあることが多いので、気軽に立ち寄れる外出先になります。
同じ立場のママと自然に出会える場でもあるので、無理なく交流のきっかけを作れます。
ファミサポや一時預かりでリフレッシュ
自治体の「ファミリー・サポート・センター(ファミサポ)」や一時預かりを利用すると、短時間子どもを預けて自分の時間を持てます。
美容院に行く、友だちとお茶をする、買い物をする、そうした時間が心身の余裕を取り戻す助けになります。
地域で制度は異なりますが、利用のハードルは高くないことが多いので、一度調べてみましょう。
急な用事や、体調不良の時にも役立ちますよ。
LINEや電話で相談できる窓口もある
外出が難しい日や誰にも会いたくない日には、LINEや電話で相談できる窓口が便利です。
自治体や支援団体が無料で提供するオンライン相談を利用すると、ちょっとした不安でも気軽に言葉にできます。
家族や友人に言いづらいことも、第三者なら話しやすいことがあります。
匿名で相談できる電話サービスもあり、「こんなことで相談していいのかな…?」という遠慮は不要です。家にいながら頼れる手段の一つとしてぜひ活用してください。
孤独を感じるときにできる6つの工夫

育児の中でふとした瞬間に感じる孤独感。
実は、ちょっとした工夫や行動で和らげることができます。
人とつながるきっかけを持ったり、自分の時間を確保したりすることは、心を落ち着かせる大切なポイントです。
ここでは、気軽に試せる6つの方法をご紹介します。
1.公園で自然に出会いをつくる
子どもと一緒に公園へ行くことは、外の空気を吸ってリフレッシュできるだけでなく、自然にママやパパと出会えるチャンスにもなります。
何度か足を運ぶうちに顔見知りが増え、あいさつやちょっとした会話から交流が広がることも。
「何ヶ月ですか?」「可愛いですね」といった一言から、気楽に始めてみましょう。
また、公園や散歩などの軽い運動は“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンを分泌させ、気分を安定させる効果があるともいわれています。
モヤモヤした気分も、体を動かすだけで少しずつ晴れていきますよ。(参照:運動と不安)
2.子ども向けイベントに参加する
自治体や保育園、民間の子育て施設では、親子で楽しめるイベントが定期的に開かれています。
- ベビーマッサージ
- 離乳食教室
- 読み聞かせ会
このように、内容もさまざま。
季節の行事も多く、初めてでも参加しやすいのが魅力です。
同じイベントに参加する親子は、子育てへの関心が近いことが多いため、自然と会話が生まれやすいもの。
「自分だけじゃないんだ」と思えるだけで、気持ちが軽くなることもあります。(参照:子育てグループにおける母親の子育てに関する意識や態度の変化)
3.SNSやオンライン相談を活用する
外出が難しいときや、直接人と会うのに気が重いときは、オンラインでのつながりがおすすめです。
- 育児コミュニティやオンラインサロン
- 匿名で利用できる掲示板やアプリ
- 助産師・医師へのチャット相談
など、安心して使えるサービスが増えています。
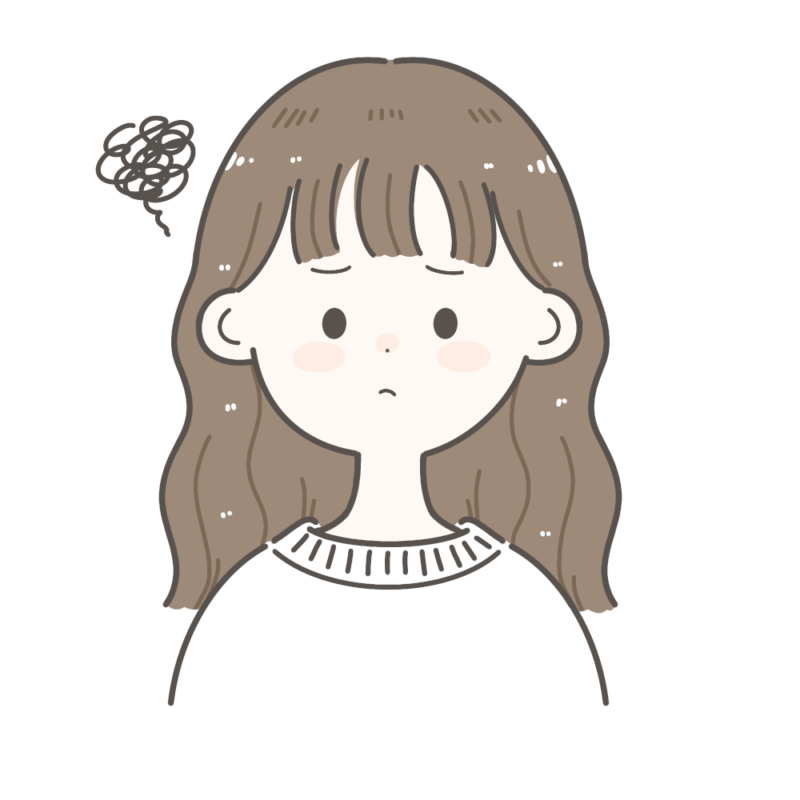
他人に愚痴をこぼすのは気が引けるな…
相手にどう思われるか気になるし…
こんなときには、ChatGPTのようなAIへ気軽に悩みを話す人もいます。
「正確な答え」ではなくても、気持ちを整理するきっかけになることがありますよ。
4.夫婦で気持ちを共有する
育児の孤独感を和らげるうえで、パートナーとのコミュニケーションは欠かせません。
「今日はこんなことがあったよ」「これに困っているんだ」
そんな日々のやり取りが大切です。
パパはママより赤ちゃんと過ごす時間が少なくなりがちですが、ママから「今日の赤ちゃん」を伝えてもらうことで、少しずつ父性が育ち、関わり方も変わってきます。
夫婦の会話が、孤独を支える大きな力になります。
5.不安を整理してみる
育児の不安を頭の中だけで抱えていると、どんどん大きくなってしまいます。
まずは紙に書き出して「自分は何に不安を感じているのか」を整理してみましょう。
また、保健師や助産師、子育て支援センターなどの専門家に相談すると、意外な解決のヒントが見つかることもあります。
私は助産師として育児の専門知識はあるはずなのに、いざ自分のこととなると、不安になることがあり、ネットで何日も検索を続けて苦しんでいたことがあります。
そんな中、子育て支援センターに遊びに行きました。
直接、専門の方に「大丈夫だよ」と直接声をかけてもらえたとき、やっと心が軽くなった…という経験があります。
ネット検索だけでは不安が膨らんでしまうことも多いので、「直接相談する」という選択肢を持つことが安心につながります。
ぜひ専門機関を活用して、不安を一つでも解消してください。
6.早めの職場復帰を選ぶのも一つ
「育児に専念しなきゃ」と思うあまり、かえって苦しくなってしまう場合もあります。
そんなときは、早めの職場復帰を選ぶのも方法のひとつです。
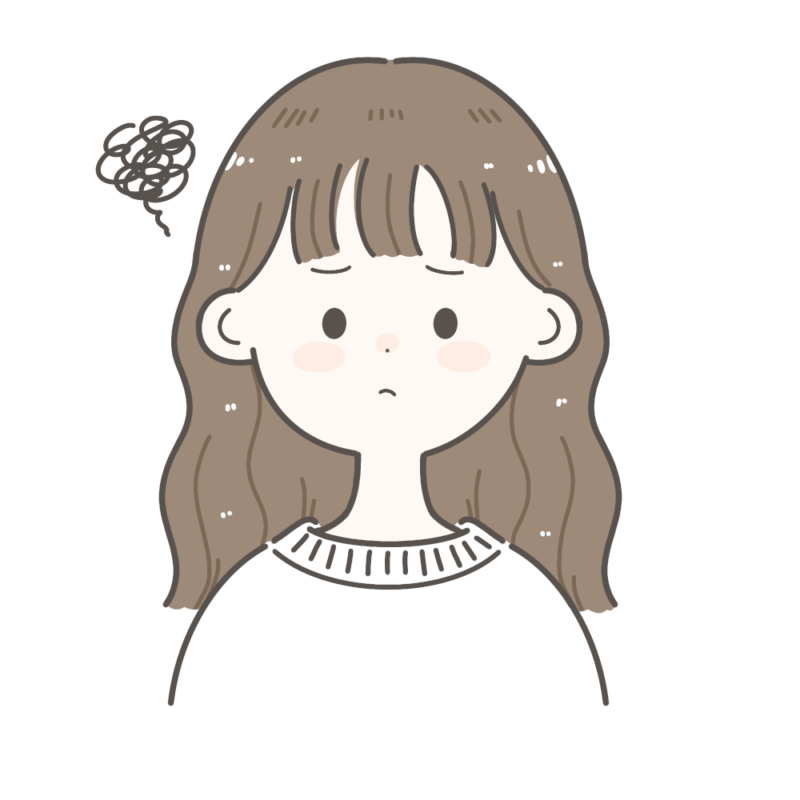
育休中は、働いているときよりもしんどかった…
社会とのつながりを取り戻すことで気持ちが前向きになり、生活にもメリハリが出る人もいます。
保育園や家族の協力を得ながら、自分のペースで復職を考えることは、ママやパパ自身の心の健康にもつながります。
焦る必要はありません。
「育児と仕事のバランス」は、人それぞれで良いのです。
孤独がつらいときに知っておきたい「心のサイン」

育児中の孤独感が長く続いたり、気持ちが強く落ち込んでしまうとき、それは「心からのSOS」のサインかもしれません。
特に産後は赤ちゃんのお世話で余裕がなく、自分の心の不調に気づきにくいものです。
だからこそ、早めにサインに目を向けることが大切です。
ここでは、産後うつの兆候と、無理のない子育てを続けるための心構えについてお伝えします。
産後うつかもしれないサイン
産後うつは、誰にでも起こりうる心の病気です。
次のような症状が2週間以上続いているときは、注意が必要です。
これは性格の弱さではなく、ホルモンの変化や環境の影響によるものです。
特に、完璧主義の方やサポートが少ない方、過去に心の病気を経験したことがある方は、産後うつになりやすいと言われています。
産後うつは「気持ちの問題」ではなく、適切な治療で改善できる病気です。
少しでも当てはまると感じたら、一人で抱え込まずに医師に相談してください。
ママ友づくりを無理しない勇気
「ママ友をつくらなきゃダメ」「みんなのようにできない自分はダメ」
そんな風に自分を責める必要はありません。
ママ友づくりは“必要だと思ったときに”自然に始めれば大丈夫。
子育てに正解はありません。
一人で過ごす時間が心地よいなら、それも立派な選択です。
大切なのは、今の自分にとって必要なつながりだけを選び、自分らしい子育てをしていくこと。
その姿こそ、赤ちゃんにとっても安心できる環境につながります。
まとめ
子育て中に孤独を感じるのは、とても自然なことです。
多くのママ・パパが経験する感情なので、「私だけが…」と思わなくて大丈夫。
たとえ近くに話せる友達がいなくても、小さな行動やちょっとした支援を受けることで、少しずつ気持ちは軽くなっていきます。
大切なのは、「ちゃんとしなきゃ」「頑張らなきゃ」と自分を追い詰めすぎないこと。
完璧なお母さん・お父さんになろうとする必要なんてありません。
「今日も赤ちゃんが元気でいてくれた」
それだけで、あなたは十分すぎるほど頑張っています。
私自身も、初めての0歳児とのワンオペ育児のとき、宅配サービスのおばちゃんとのちょっとした会話が心の支えになったことがあります。
ほんの少しでも人と話すだけで、気持ちが軽くなることは本当にあるんです。
つらいときは、無理に一人で抱え込まなくて大丈夫。
家族や友人、助産師さんや保健師さんなど、あなたを支えてくれる人は必ずいます。
「イクメン」という言葉が流行語になったのは2010年。
少しずつ育児を取り巻く環境は変わってきましたが、まだまだママに負担が集中しがちなのが現実です。
だからこそ、しんどいときには夫婦で助け合ったり、専門家の力を早めに借りたりすることが大切。
悩みを深刻化させる前に、気軽に相談してみましょう。
子育ては毎日が続く長い道のりです。
今がつらくても、必ず楽になる日がやってきます。
焦らず、自分のペースで、一歩ずつ進んでいきましょう。