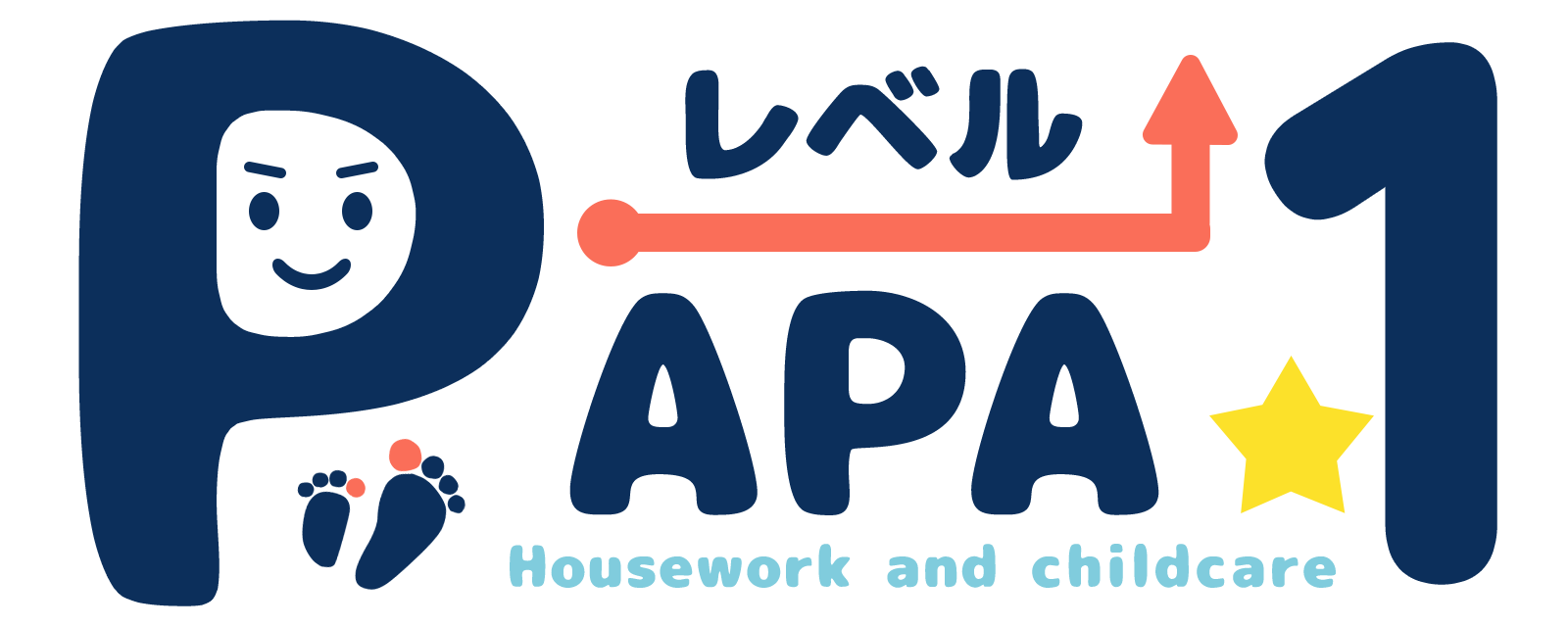【助産師解説】パパが抱っこすると赤ちゃんが泣く?嫌がる理由と信頼関係の築き方
パパが抱っこすると、急に赤ちゃんが泣き出す――
そんな経験、ありませんか?
胸がギュッと痛むようなあの瞬間。
育児に前向きなパパほど、落ち込んでしまうこともあります。

ママのときは泣かないのに、どうして自分のときだけ?
もしかして嫌われてるのかな?
赤ちゃんが泣くのにはちゃんと理由があって、決して「パパが嫌い」だからではないんです。
筆者は、3児の母であり、助産師として多くのご家庭に寄り添ってきました。
赤ちゃんの“泣き”には、成長のサインや、家族との関係づくりが大きく関わっていることがわかっています。
この記事を読み終えるころには、「泣かれたらどうしよう…」という不安が、
「大丈夫。できることから始めてみよう」に変わるはずです。
赤ちゃんとの絆を深めたいすべてのパパに、ぜひ読んでいただきたい内容です。

助産師りず
助産師・12年以上の病院勤務経験をもつ3児の母。
4歳と2歳と0歳の子育て経験と助産師での経験を活かし、初心者パパの育児を全力でサポートします。
抱っこ(横抱き・縦抱き)の基本については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
パパが抱っこすると泣くのはなぜ?よくある悩みとその理由

ママだと泣かないのに…なんでパパだけ?
赤ちゃんを抱っこしたら、急に泣き出した…
そんな経験、ありませんか?
ママのときはニコニコしてたのに、自分が抱っこしたらギャン泣き…。
パパとしてはちょっとショックですよね。
でも実はこれ、とてもよくあることなんです。
パパとママでは、抱き方や声のトーン、体の大きさなど、赤ちゃんから見るといろんな違いがあります。
その違いが、赤ちゃんにとっては「いつもと違う=ちょっと不安」と感じてしまう原因になることもあるんです。
赤ちゃんにとってママは“安心の存在”
赤ちゃんは、お腹の中にいたときからママとずっと一緒に過ごしています。
ママの体温、声、匂いなど、これら全部が「安心できるもの」としてインプットされているんです。
一方でパパは、赤ちゃんにとってはまだちょっと“新しい存在”。
声はうっすら聞いたことがあっても、ママほど近くで関わる時間が少ないと、赤ちゃんは「この人だれだろう?」と戸惑ってしまうことも。
「嫌われてるのかな…?」と思う前に知ってほしいこと
抱っこして泣かれると、つい「自分のことが嫌いなのかも…」と落ち込んでしまうかもしれません。
でも、それは違います!
赤ちゃんはまだ「好き・嫌い」ではなく、安心できるかどうかで反応しているんです。
泣くのは、不安や不快を伝えるサイン。
そして、そのサインがたまたまパパの抱っこのときに出るだけ。
決して「パパが嫌い」だから泣いているわけではありません。
むしろ、泣くことで
「ちょっと怖いよ」「どうしていいか分からないよ」
と、パパに気持ちを伝えようとしているんです。
「パパ見知り」ってなに?始まる時期とその“理由”を解説

パパ見知り、いつから始まる?

最近、赤ちゃんが自分の顔を見て泣くようになった…
そんなとき、もしかするとそれは「パパ見知り」かもしれません。
パパ見知りとは、赤ちゃんがパパに対して人見知りのような反応をすること。
だいたい生後5〜7ヶ月ごろから始まり、8ヶ月ごろに強くなることもあります。
ちょうどこの時期の赤ちゃんは、「いつも一緒にいる人」と「たまに会う人」の違いがわかるようになる頃です。
ママと一緒に過ごす時間が長い家庭では、パパのことを“たまに現れる人”と感じてしまうこともあります。
その結果、「この人、誰だっけ?」と不安になって泣いてしまうのです。
泣かれるのは“成長している証”!
赤ちゃんが人の顔を見分けたり、「この人、ちょっと知らないかも…」と感じられるようになったのは、大きな成長のサインです。
パパ見知りは、赤ちゃんが「人との距離感」を学び始めた証拠でもあります。
だからこそ、泣かれても落ち込む必要はありません。
むしろ「ここから仲良くなっていくチャンスだ!」と前向きに受け止めて、少しずつ関わる時間を増やしていきましょう。
「泣かれる=嫌われた」ではありません
赤ちゃんに泣かれると、どうしても「自分が嫌われているのかな…」と心が沈んでしまうかもしれません。
でも、赤ちゃんの泣きには“拒否”や“嫌悪”の感情はほとんどありません。
泣くのはあくまでも、「なんだか不安」「ちょっと怖い」「よく分からない」という違和感や戸惑いのサイン。
特に人見知りが始まる時期は、いつもと違う相手や環境に対してとても敏感になります。
だからパパの抱っこで泣くのも、ごく自然なことなんです。
パパの存在に赤ちゃんが少しずつ慣れていけば、自然と泣かなくなることがほとんどです。
泣く=“本能”としての防御反応
実は、「パパ見知り」は赤ちゃんにとっての生きる力とも言えます。
知らない人にすぐなつかない、警戒するという行動は、自分を守るために進化の過程で備わった本能的な反応なんです。
これは「生存戦略」のひとつ。
赤ちゃんが「この人、安全かな?」と見極めているんです。
パパと過ごす時間が短かったり、接する機会が少なかったりすると、赤ちゃんは自然と“見慣れない人”と判断して警戒してしまうのです。
でもこれは、赤ちゃんがちゃんと成長している証拠。
泣かれた=拒絶された、ととらえるのではなく、「泣く=今はまだ距離があるというサイン」と受け止めてみてください。
パパが抱っこして泣かれたときの対処法

赤ちゃんが泣くのは、こんなとき
まず大前提として、赤ちゃんは「泣くのが仕事」と言われるくらい、ちょっとした不快感も全部“泣く”で表現します。
たとえば、こんなときに泣きます。
- お腹がすいた
- 眠くてグズグズ
- オムツが気持ち悪い
- 暑い or 寒い
- なんとなく不快(服のチクチク、音や光など)
そして、パパの抱っこで泣いてしまうときは、こうした不快感に加えて「なんとなく知らない感じ」「ちょっと緊張する」といった“慣れ”の問題が関係していることもあります。
泣き止まなくてもOK。まずは落ち着いて対応しよう

赤ちゃんが泣いちゃった!
早く泣き止ませなきゃ!
そう思えば思うほど、うまくいかないもの。
イライラや焦りって、赤ちゃんにも不思議と伝わるんですよね。
まずは深呼吸して、
「どうした〜?大丈夫だよ〜、パパここにいるよ〜」
と、赤ちゃんにやさしく声をかけてみましょう。
そして、「泣いている原因があるかも?」と一つずつチェック。
それでも理由がわからないときは、無理に泣き止ませようとしなくても大丈夫。
「そばにいるよ」「気持ちは受け止めてるよ」という気持ちを、声や抱っこでそっと伝えてあげるだけでOKなんです。
泣きやませるための工夫
赤ちゃんが安心できるような、ちょっとした工夫も効果的です。
- 抱っこしながら部屋をゆっくり歩く
- 背中をやさしくトントンする
- 小さな声で歌ってあげる
- 外の空気を感じさせる(ベランダや窓辺で風にあたる)
- やさしい音楽を流す、抱っこで散歩に出る
こうした工夫は、赤ちゃんだけでなくパパ自身のリフレッシュにもつながりますよ。
泣かれても大丈夫。「受け止める姿勢」が赤ちゃんの安心につながる
パパにとって、赤ちゃんに泣かれるのはツラいもの。
「自分がダメだから?」「抱っこの仕方が悪かったのかな?」
と不安になることもありますよね。
でも、赤ちゃんは、誰が抱っこしても泣くことがあるのです。
実は、出産直後のママも同じように悩んでいます。
筆者も「助産師さんの抱っこでは泣き止むのに、自分が抱くとまた泣くんです…」
と、入院中のママたちから相談されることも少なくありません。
でも、1ヶ月もすれば、赤ちゃんはママの抱っこがいちばん落ち着くようになっていきます。
その変化の理由は、「慣れ」と「信頼」が少しずつ育っていくから。
パパが毎日少しずつ関わることで、
- パパの声や匂いに赤ちゃんが安心するようになる
- 抱っこの仕方に慣れ、赤ちゃんも心地よく感じるようになる
- 「一緒にいる」という時間の積み重ねが、信頼に変わっていく
といった変化が、ゆっくり起きていきます。
赤ちゃんにとって大切なのは、「泣かせないこと」ではなく、泣いてもそばにいてくれる人がいること。
泣き止まなくても、焦らずに落ち着いて寄り添ってあげてください。
今日からできる!パパ見知りを解消する6つのコツ

① 声かけとスキンシップで“安心できる存在”に
赤ちゃんは、パパの声や表情、ぬくもりから安心感を感じ取ります。
- おむつ替えや着替えのときに「きれいにしようね~」と声かけ
- 抱っこしながら優しくトントン
- 小さな手を握る、ほっぺにそっと触れる
こうしたスキンシップ+声かけが、赤ちゃんとの信頼関係の第一歩です。
そして、赤ちゃんに話しかけるときは「マザリーズ(赤ちゃん語調)」が効果的!
赤ちゃんはこの“話し方”が大好きです!
【参考:0歳児におけるマザリーズの効果に関する一考察】
「今日は暑いね~」
「さっき泣いてたね、どうしたの?」
「パパ、今からお仕事行ってくるよ~応援してね!」
赤ちゃんは言葉の意味はわからなくても、声のトーンや表情で“やさしさ”を感じ取っています。
② 魔の時間帯を避けて「ごきげんタイム」にアプローチ!
赤ちゃんにも、“機嫌の良い時間”と“悪くなりがちな時間”があります。
機嫌が悪くなりやすい時間帯はこんなとき。
これらを避けて、「ごきげんタイム」に関わるだけで、泣かれにくくなります!
赤ちゃんがリラックスしているタイミングを狙って関わることで、パパとのポジティブな時間を積み重ねやすくなります。
③ 「パパの時間」を習慣化!ルーティンで距離を縮めよう
赤ちゃんは“決まった流れ”に安心を感じる生きもの。
だからこそ、毎日繰り返すルーティンは信頼関係づくりにとても効果的です。
- 朝の着替えはパパ担当
- お風呂あがりの保湿やお世話
- 寝る前にパパと絵本タイム
「この時間になるとパパが来てくれる!」
そんな体験の積み重ねが、赤ちゃんにとっての「安心できる習慣」になります。
④ パパの“役割”を決めて、育児の主力メンバーに!
パパが育児の中で“自分の担当”を持つことは、とても大切です。

パパにお願いしてよかった!
これで安心して任せられる!
パパに役割があることで、家庭の育児バランスもよくなり、赤ちゃんとの距離もぐっと近づいていきますよ。
⑤「当たり前にいる存在」になることで、パパ見知りはなくなる
赤ちゃんにとって、「いつもそこにいる人」という安心感はとても大きいもの。
- 朝の5分、一緒に着替え
- 帰宅後の10分、抱っこでスキンシップ
- 寝る前にちょっと絵本を読む
平日は仕事で忙しくても、こんな小さな積み重ねが、赤ちゃんにとっての“パパとの日常”になります。
「特別なこと」より「毎日の少し」が、愛着形成のポイントです。
⑥「愛着形成(アタッチメント)」って?
赤ちゃんが「この人なら安心できる」と思える関係のことを愛着形成といいます。
この安心感があるからこそ…
- 感情が安定しやすくなる
- 人との関わりが好きになる
- 自分に自信が持てるようになる
など、その子の“生きる力”の土台が育っていきます。
パパの毎日の関わりが、赤ちゃんの将来にとって大きな贈り物になるんです。
パパ見知りを悪化させるNG行動とは?
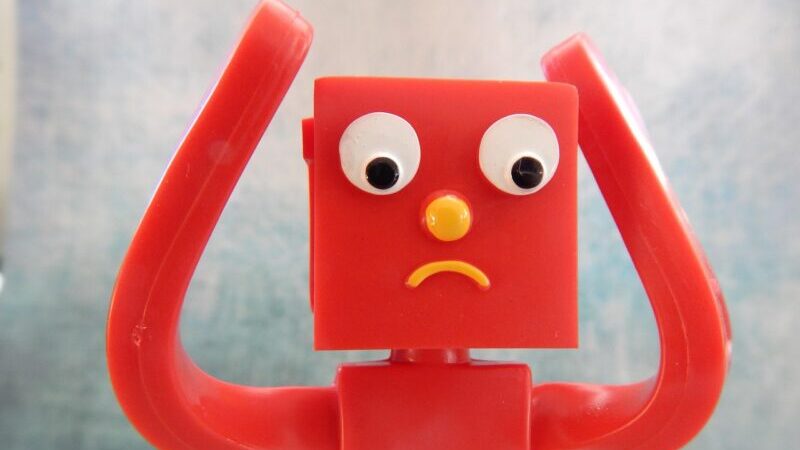
知らずにやっているかも…その習慣、ちょっとストップ!
赤ちゃんに泣かれてしまうと、「やっぱりママじゃないとダメなんだ…」と落ち込んでしまうパパも多いと思います。
でも、そのときの反応次第で、パパ見知りが“悪化”してしまうこともあるんです。
ここでは、赤ちゃんとの関係を築くために避けたい3つのNG行動をご紹介します。
① 泣かれたからといって、すぐにママに交代する
赤ちゃんに泣かれると、「やっぱりママがいいんだな」と思って、すぐにママにバトンタッチしていませんか?
実はこれ、赤ちゃんにとって「泣けばママが戻ってくる」という学習につながってしまいます。
さらにパパ自身も「やっぱり自分には無理かも…」と感じて、関わる意欲が下がってしまうことも。
このパターンが続くと、パパが関わるチャンスがどんどん減ってしまい、赤ちゃんとの距離が縮まらなくなってしまいます。
② 泣かれるのが怖くて、関わる時間を減らす
泣かれるたびに落ち込んでしまって、「もう抱っこするのはやめようかな…」と思っていませんか?
でも実は、赤ちゃんにとって「どれだけ触れ合っているか」=安心感につながるんです。
関わる時間が少なくなればなるほど、赤ちゃんにとってパパは「知らない人」に近づいてしまいます。
泣かれることが続くのは、自然なこと。
でも、赤ちゃんは毎日少しずつ“慣れていく”生きものです。
③ 泣き止まないのを「わがまま」と思ってしまう

なんでこんなに泣くんだろう…
うちの赤ちゃん、わがままなのかな?
そんなふうに感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、赤ちゃんにはまだ“わがまま”という考えはありません。
泣くことは、赤ちゃんにとって唯一の自己表現なんです。
お腹がすいた、眠たい、不安、暑い、寂しい…
言葉にできないぶん、全部「泣く」という形で伝えてきます。
「困らせようとしてるんじゃない。何か伝えようとしてるんだ」
そう思って接するだけで、赤ちゃんへの関わり方がやさしく変わっていきます。
脱パパ見知り!「パパ抱っこ」成功エピソード
「ママじゃないと泣いちゃう…」
そんな“パパ見知り”に悩むご家庭、多いのではないでしょうか。
わが家もそうでした。
でもある日、ちょっとした工夫と偶然で、赤ちゃんの表情がふわっとやわらかくなったんです。
お風呂中に響く「ギャーーー!」の声…

ある土曜日。
私は赤ちゃんが寝ている間に、お風呂タイムをもらうことに。
平日はワンオペでバタバタですが、土曜は夫が在宅。
赤ちゃんをお願いして、久しぶりにゆっくり湯船へ。

ふ〜。やっと一息つけた〜…
…と思ったのも束の間。
「ぎゃああああ!!」
そう、赤ちゃんの泣き声です。
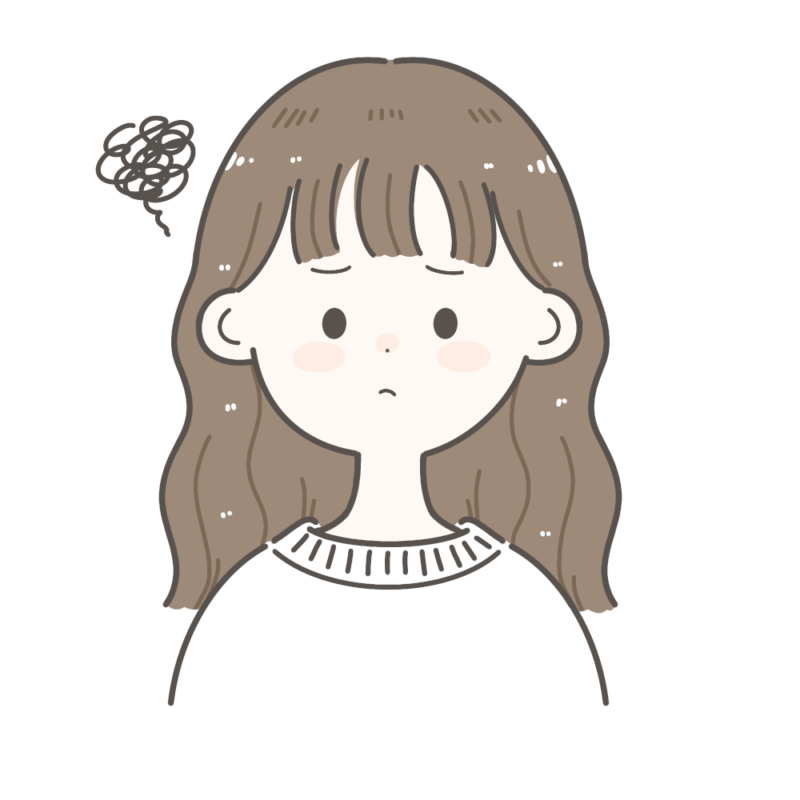
あ〜、起きちゃったか…
急いで頭を洗ってシャワーを済ませ、そそくさと体を拭いていたその時。
ふと、泣き声がピタッと止まったんです。
パパの「アニメソング」で赤ちゃんがご機嫌に!
急いでリビングをのぞいてみると…
そこには、赤ちゃんを抱っこしながらアニメソングを熱唱する夫の姿が!
歌っていたのは、赤ちゃん向けの童謡…ではなく、夫が子どもの頃から大好きな“あのアニメ”の主題歌。
でも不思議なことに、赤ちゃんはじーっとパパを見つめて、いつの間にか泣きやんでいました。
夫も、歌うことで緊張がほぐれ、自然な笑顔になっていたようです。
声・リズム・表情がつなぐ親子の信頼
赤ちゃんは、言葉の意味はわからなくても、
- パパの声のリズム
- 表情のやさしさ
- パパ自身の「楽しい気持ち」
こういった空気感を敏感に感じ取っています。
このときの赤ちゃんも、「なんだか楽しそう」「この声、なんか安心する」といった感覚で、心を落ち着かせていたのかもしれません。
「パパならではの方法」は、きっと見つかる
私たちママは、つい“正解の育児”を求めがち。
でも、パパだからこそできる関わり方って、実はたくさんあるんです。
たとえ泣かれても、あきらめずに向き合うことで、少しずつ“うちの子に合ったパパ流の方法”が見つかっていきます。

パパが赤ちゃんをあやしてくれると、本当に心強い!
赤ちゃんの笑顔が見られたあの日から、夫も「もっと関わりたい」と前向きに。
パパと赤ちゃんの距離も、ぐっと縮まりました。
泣かれても大丈夫!パパの一歩が、家族の絆を深める
この記事では、
- パパの抱っこで赤ちゃんが泣いてしまう理由
- 「パパ見知り」の背景
- 今日からできる具体的な工夫や声かけのコツ
などを、わかりやすく紹介してきました。
「抱っこしたら泣かれた…」
そんな時、「自分が嫌われてるのかな?」と感じてしまうこと、ありますよね。
でも、赤ちゃんが泣くのはパパに慣れていないだけ。
決して「イヤだから」ではありません。
ポイントは、「少しずつ慣れていくこと」。
- 声をかける
- 抱っこしてみる
- 決まった時間に関わる(ルーティン)
そんな小さな行動の積み重ねが、赤ちゃんにとっての安心感につながっていきます。
赤ちゃんとパパの関係も、最初はみんなゼロからのスタート。
うまくいかない日もあるけれど、焦らなくてOKです。
「パパだからできること」も、きっと見つかります。
その関わりは、赤ちゃんにとっての宝物になり、ママにとっても大きな支えになるはずです。
ぜひ今日から、一歩ずつ。パパとしての「できた」を、一緒に増やしていきましょう!
あなたの関わりが、家族みんなの笑顔につながっていきます。