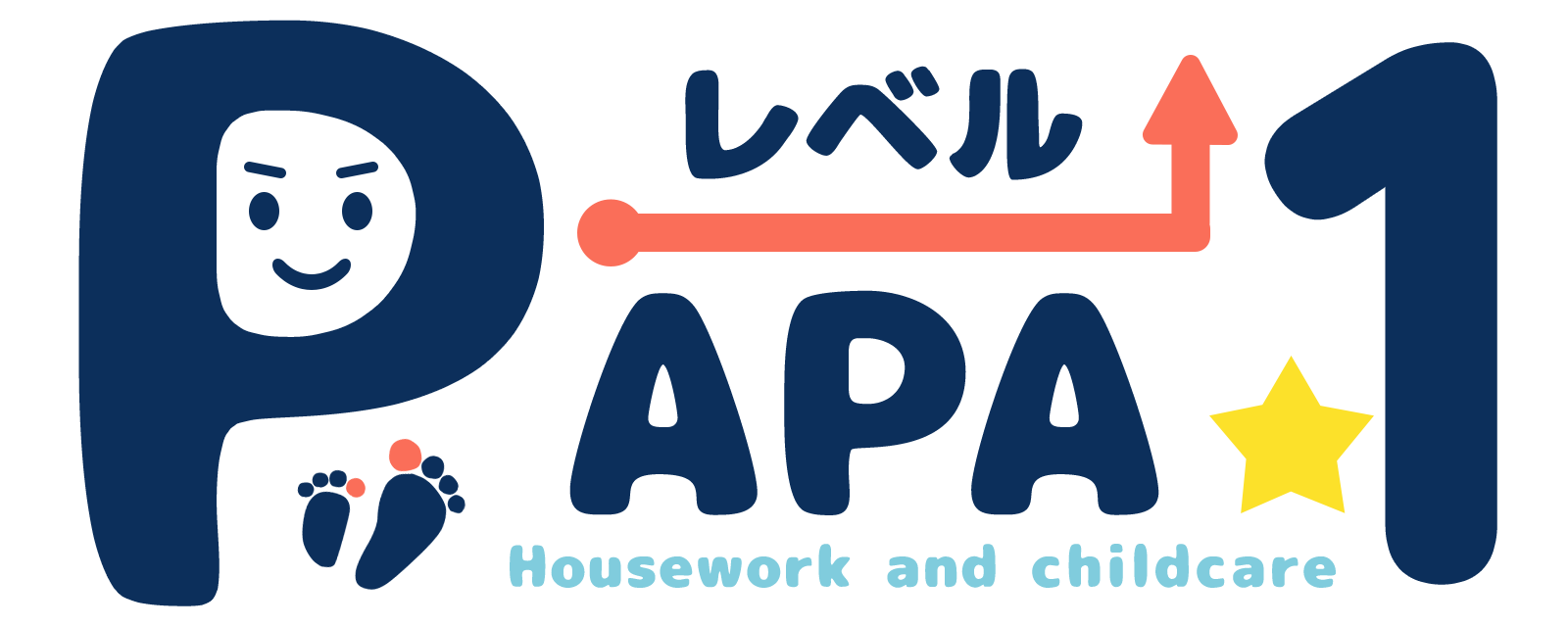【助産師解説】予防接種前後の離乳食はどうする?初めての食材はいつから安全?
生後5〜6ヶ月ごろになると、寝返りをしたり、体を動かしたりと成長がぐんと進みます。
同じ時期に「離乳食のスタート」と「予防接種のスケジュール」が重なることも多く、不安を感じやすい時期です。

離乳食は楽しみだけど、もしアレルギーが出たらどうしよう…。
予防接種もあるし、同じ時期に始めて大丈夫かな?
赤ちゃんの体調に敏感になるこの時期。
「これで合っているのかな?」と迷ってしまうパパやママは少なくありません。
特に予防接種のあと、赤ちゃんがぐったりしたり熱を出したりすると、
「こんなとき離乳食はどうすればいいの?」と心配になりますよね。
でも、いくつかの基本ルールを知っておけば、赤ちゃんの安全を守りながら安心して離乳食を進められます。
「食事」は、お子さんにとって大切な時間です。
パパも一緒に知識を持つことで、家族みんなで楽しく食卓を囲めるようになりますよ。
予防接種と離乳食が重なる時期の不安や疑問を、助産師の視点からわかりやすく解説します。
最後まで読めば、「安心して離乳食を進めるためのポイント」がきっと見えてきますよ。

助産師りず
助産師・12年以上の病院勤務経験をもつ3児の母。
4歳と2歳と0歳の子育て経験と助産師での経験を活かし、初心者パパの育児を全力でサポートします。
予防接種と離乳食の基本ルール

予防接種後の赤ちゃんは、体調が変化しやすいもの。
「離乳食はどうしたらいいの?」と迷うパパ・ママも少なくありません。
基本的には、体調が普段どおりなら食事はOKです。
ただし、注意点を知っておくことで、より安心して進められます。
特に大切なのは「新しい食材を試すかどうか」。
ここは慎重に判断しましょう。
予防接種と離乳食を両立させるための基本ルールを解説します。
当日・翌日の離乳食はOK?
予防接種の当日や翌日でも、赤ちゃんが普段どおり元気であれば、食べ慣れた離乳食を与えて構いません。
食欲が落ちているときは、母乳やミルクを少し多めにして、水分と栄養を補いましょう。
基本の10倍粥や野菜ペーストは大丈夫?
すでに食べ慣れている10倍粥や野菜ペーストであれば、予防接種のあとでも安心して与えられます。
消化にやさしく、アレルギーのリスクも低いため、体調に合わせて少しずつ与えてみましょう。
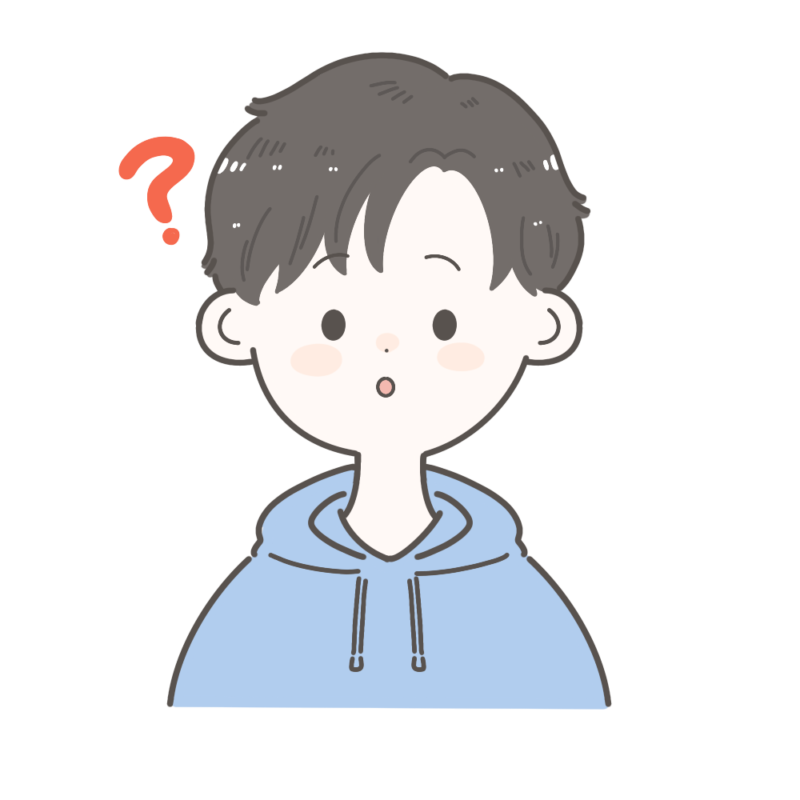
予防接種のあとは、体がだるそうにすることもあるんだよね。
副反応で熱やぐったりが見られることもあります。
「離乳食を進めること」より「赤ちゃんの体調を整えること」を優先しましょう。
新しい食材を避けるべき理由
予防接種の前後に新しい食材を試すのは避けましょう。
もし症状が出た場合に、「予防接種の副反応?」「食材によるアレルギー?」の原因を区別できなくなるためです。
新しい食材は、赤ちゃんの体調が安定している日に、1種類ずつ・少量から与えることが基本です。
副反応とアレルギー反応の違いは?

予防接種後に赤ちゃんの体調が変わると、
「これは副反応?それともアレルギー?」と迷ってしまうことがあります。
どちらも体に起こる反応ですが、症状や対応は異なります。
ここでは、副反応とアレルギー反応の違い、見分け方のポイントを整理していきます。
副反応:ワクチンによる一時的な体の反応
予防接種を受けたあとに見られる一時的な反応が「副反応」です。
多くは1〜2日で自然に落ち着きます。
アレルギー反応:特定の食材や成分への過剰な反応
一方、アレルギー反応は「食べ物・成分」に免疫が過剰に反応してしまうことです。
私たちの体には、細菌やウイルスなどの“病気のもと”から身をまもる、「免疫」というしくみがあります。
本来、安全なはずの食べ物にまで反応してしまうのがアレルギーの特徴です。
見分け方のポイントは「症状の出方と持続時間」
副反応とアレルギー反応を見分けるカギは、症状の出方と持続時間です。
- 副反応
→ 時間が経つと自然に改善することが多い - アレルギー反応
→ 摂取後すぐに出やすく、放置すると重症化する可能性あり
赤ちゃんの症状がどちらか判断できない場合は、自己判断せず早めに小児科へ相談しましょう。
注意すべきはアレルギー反応
予防接種後に発熱や不機嫌があっても、多くは一時的な副反応です。
水分がとれていて元気があるようなら、慌てすぎなくても大丈夫です。
ただし、本当に注意が必要なのはアレルギー反応による症状です。
特に、全身に発疹が出たり、呼吸が苦しい場合は緊急対応が必要です。
離乳食でアレルギー反応が出たときの対応
基本の流れは次のとおりです。
- すぐに食事を中止する
- 軽い症状(湿疹・赤み程度)は日中に小児科を受診
- 嘔吐・下痢・呼吸困難・ぐったりなど重い症状は救急受診
- 顔色が悪い/呼吸が苦しい/意識がもうろう → 迷わず救急車を呼ぶ
(参照:食物アレルギー対応ブック)
事前に以下を確認しておくことで、いざというとき慌てずに行動できます。
特に注意が必要な食材は?

離乳食を進めるうえで気をつけたいのが、アレルギーを起こしやすい食材です。
一度強いアレルギー症状が出ると不安になりますし、パパやママにとっても心配ごとの一つです。
代表的なのは 鶏卵・小麦・乳製品。
これらは「三大アレルゲン」と呼ばれ、与え方やタイミングを誤ると強い症状が出ることもあります。
ここでは、安全に与えるためのポイントと、予防接種とのスケジュール調整について解説します。
鶏卵・小麦・乳製品はどう注意すべき?
鶏卵・小麦・乳製品は乳幼児期にアレルギーを起こしやすい食材です。
初めて与えるときは 必ずごく少量から スタートしましょう。
理由は、アレルギー反応が出た場合、大量摂取だと症状が強く出やすいためです。
いつから与えていいの?
以前は「1歳を過ぎてから」と言われていましたが、
現在は厚生労働省や日本小児科学会のガイドラインで「5〜6ヶ月ごろから少しずつ開始すること」が推奨されています。
早めに少量から試すことで、かえってアレルギーを起こしにくくなる可能性も示されています。
離乳食の開始時期は「5〜6ヶ月ごろ」と幅があります。
赤ちゃんの発達の状態を見ながら、パパやママの体調や生活リズムが落ち着いているときに始めると安心です。
「怖いからもっと遅らせよう」と自己判断で延ばすのはNG。
専門家が推奨する時期に、少しずつ安全に試していきましょう。
(参照:アレルギー予防の観点から離乳食のすすめ方)
予防接種と重ならないようにしよう
新しい食材を試す「タイミング」にも注意が必要です。予防接種のスケジュールと重ならない日を選びましょう。
こうした工夫で、赤ちゃんの安全を守りながら安心して離乳食を進められます。
安全な離乳食スケジュールの立て方

離乳食を安全に進めるには、食材を増やすことだけに意識を向けず、予防接種の予定や赤ちゃんの体調を見ながら計画することが大切です。
スケジュールを把握して進めれば、安心して赤ちゃんの「食べる第一歩」をサポートできます。
予防接種とのバランスを取るコツ
離乳食の予定を立てるときは、まず予防接種のスケジュールを確認しましょう。
接種がある週は無理に新しい食材を増やさず、食べ慣れたもの中心で進めるのがおすすめです。
数日遅れても成長には影響しないので、焦らず進めることが大切です。
新しい食材は「平日・午前中」が鉄則
新しい食材を試すなら、平日の午前中がベストです。
もしアレルギー症状が出ても、すぐに病院を受診できる時間帯だからです。
土日や祝日は病院が閉まっていることも多く、探すのに時間がかかってしまいます。

確かに、病院が開いている時間なら安心だね!
赤ちゃんの体調チェックリスト
新しい食材を与える前には、赤ちゃんの体調を必ず確認しましょう。
以下のポイントを目安にチェックしてみてください。
これらが揃っていれば、新しい食材に挑戦するサインです。
逆にひとつでも不安があれば、無理せず延期しましょう。
赤ちゃんにとっては「安全第一」が一番です。
(参照:食物アレルギーの栄養食事指導)
離乳食開始時期と予防接種の重なり

離乳食を始める目安は生後5〜6ヶ月ごろとされています。
ただし、実際にはこんな悩みを抱くパパやママも多いのではないでしょうか。
「成長が早いから、もう始めてもいい?」
「アレルギーが心配だから、もっと遅らせた方がいい?」
ここでは、開始時期ごとのメリットとリスクを整理し、安全にスタートするための考え方を紹介します。
5〜6ヶ月で始めるメリット
もっとも推奨されるのは、生後5〜6ヶ月ごろから。
赤ちゃんの発達や消化機能が整ってくる時期です。
母乳やミルクだけでは栄養が不足しやすい
この頃は急速に成長が進み、特に鉄分や亜鉛が不足しやすくなります。
もし不足すると、貧血や発達の遅れにつながる可能性があると指摘されています。
(参照:乳児期の鉄欠乏について)
消化機能が発達してくる
唾液や消化酵素が増え、やわらかい食べ物を消化できる力がついてきます。
飲み込む力が育ってくる
舌の動きや嚥下の機能が発達し、「ゴックン期」に差しかかります。
この時期に始めることで、自然に食べる力を育てることができます。
4ヶ月から始める場合のリスクと注意点
4ヶ月ごろから離乳食を始めるケースもありますが、消化機能や口の動きが未発達なことが多く、慎重に判断する必要があります。
周囲に合わせる必要はなく、「まだ母乳やミルクで十分」と考えても安心です。
7ヶ月以降に遅らせた場合のリスク
一方で、開始が遅すぎると、別のリスクが出てきます。
離乳食開始が遅れると、口から食べ物を受け入れ慣れていく機会が減るため、食物アレルギーの発症リスクが上がると報告する研究があります。
【事例】一気に与えて卵アレルギーを発症したケース
37歳・3人目を育てるママの体験談です。
赤ちゃんが生後7ヶ月のとき、初めて卵を少量与えたところ問題はありませんでした。

上の子も両親も卵アレルギーはないし、大丈夫そう。
そう思い安心していたママは、3ヶ月後に卵を半分一気に与えてしまいました。
すると赤ちゃんは1時間に5回ほど激しい嘔吐を繰り返し、一瞬意識を失うほどの強いアレルギー反応を起こし、救急搬送されたのです。
病院で治療を受けてすぐに回復しましたが、聞いただけでも身震いするような恐ろしい体験です。
医師によると、原因は次の2点でした。
- 急に摂取量を増やしたこと
- 一度試した後、長期間あけてしまったこと
卵を含むアレルゲンは、少量から・間隔をあけすぎず・継続的に与えることが大切です。
油断せず、慎重に少しずつ進めることが赤ちゃんの安全につながります。
まとめ|赤ちゃんのペースを大切に
離乳食を進めていくと、新しい食材を始めたい時期と予防接種の予定が重なることがあります。
そんなときは、無理に進めずタイミングを工夫することが大切です。
この3つを意識するだけで、離乳食の安全性はグッと高まります。
赤ちゃんの様子をよく観察しながら、少しずつ慣らしていきましょう。
不安に思ったときは、一人で抱え込まず、かかりつけの小児科に相談してください。
離乳食は赤ちゃんにとって「人生初の食体験」。
大切なのは、栄養だけでなく「食べるって楽しい!」と感じてもらうことです。
ミルクや母乳から、少しずつ食べ物へ移行していくこの時期は、成長に欠かせない大切なステップ。
焦らなくても大丈夫。赤ちゃんのペースに寄り添い、笑顔でゆったりと向き合ってください。
そして何より、赤ちゃんとの食事時間を一緒に楽しむ気持ちを大切にしましょう。