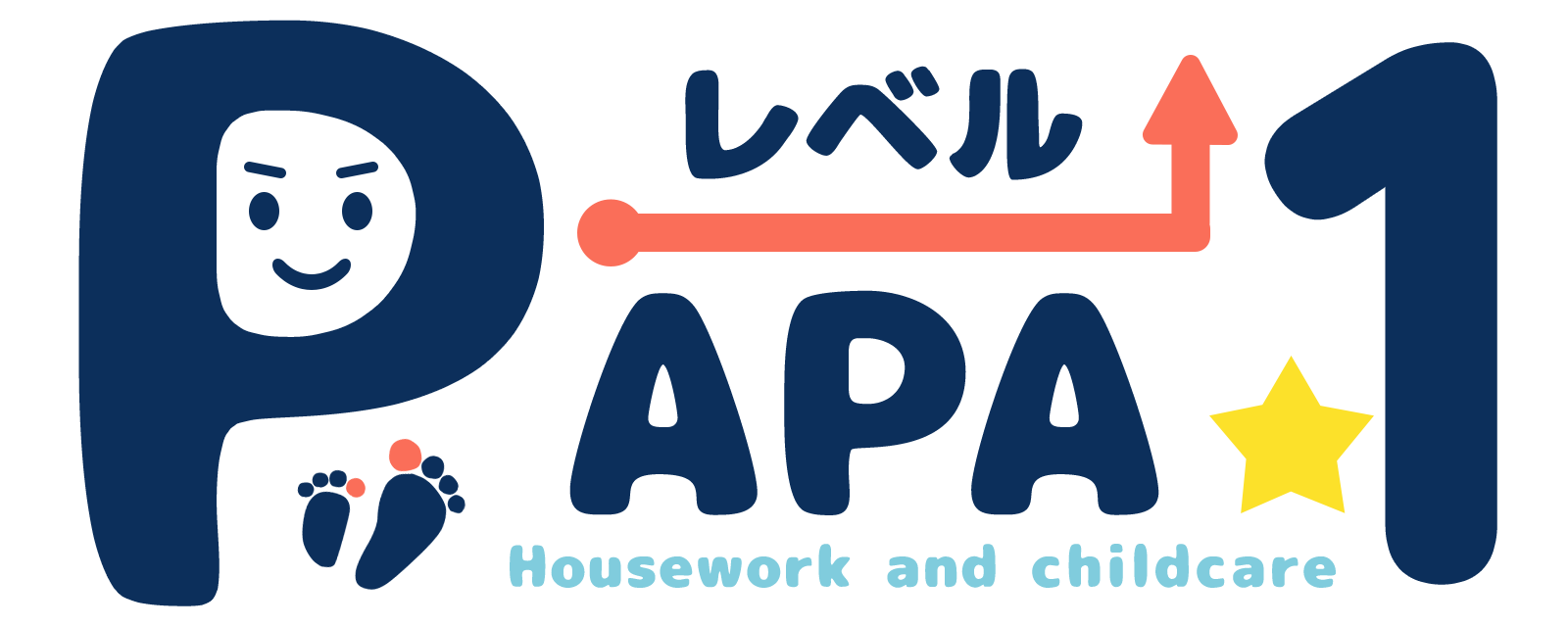【助産師解説】夜間授乳で眠すぎる!イライラの正体とパパが今すぐできる神対応
長かった妊娠期間を経て、ついに赤ちゃん誕生。

これから家族3人で幸せな毎日が始まる——。
そんなワクワクの気持ちでいっぱいだったはずです。
ところが、現実は想像以上にハード。
夜間授乳や夜泣きでママの睡眠は細切れになり、体力も気力もどんどん削られていきます。
今までぐっすり眠れていた夜が、何度も起こされる時間に変われば、疲れやイライラが募ってしまうのも当然です。
あなたの家庭でも、こんな状況があるのではないでしょうか。
- 夜間授乳でママがいつも疲れ切っている
- どうサポートすればいいのか分からない
- 気をつけたつもりなのに、何気ない一言でママを傷つけてしまった
実は、夜間授乳による負担や夫婦のすれ違いに悩む家庭は少なくありません。
この記事を読み終えるころには、ママの負担をやわらげる“頼れるパパ”になれるはず。
夫婦で一緒に乗り越えるための力を手に入れましょう!

助産師りず
助産師・12年以上の病院勤務経験をもつ3児の母。
4歳と2歳と0歳の子育て経験と助産師での経験を活かし、初心者パパの育児を全力でサポートします。
ママが夜間授乳でイライラしてしまう5つの理由

夜間授乳は、赤ちゃんが元気に育つために欠かせないものです。
しかし、ママにとっては心身に大きな負担がかかります。
ここでは、ママがイライラしてしまう主な原因を5つに分けてご紹介します。
パパが「なぜそうなるのか」を理解すれば、サポートの質はぐっと上がります。
1. 睡眠不足と眠りの分断
夜間授乳では、赤ちゃんの泣き声で何度も起きるため、睡眠は細切れ状態になります。
深く眠る前に起こされることが続くと、脳も体も回復できず、疲れが蓄積します。
特に産後すぐは授乳間隔が短く、1〜2時間おきに起きることも珍しくありません。
夜ぐっすり眠れるようになるのは数カ月先、という家庭も多いです。
赤ちゃんの睡眠リズムは、ママやパパの育児ストレスに関連するというデータもあります。
(参考資料:乳児の睡眠リズムと育児ストレスについて)
少しでも連続して眠れる時間をつくることが、ママの心と体を守ります。
2. 産後ホルモンの影響
出産後、女性ホルモンは急激に減少し、代わりに母乳を作るホルモンや、赤ちゃんを守ろうとするホルモンが活発になります。
この変化により感情の波が大きくなり、普段より敏感になりやすくなります。
特に産後1〜3カ月は「ガルガル期」と呼ばれ、些細なことでもイライラやピリピリを感じやすくなります。
3. 身体の痛みや不快感
授乳は同じ姿勢が続くため、肩・腰・首・手首などに負担がかかります。
さらに、帝王切開の傷や乳首の痛みなど、産後特有の不快感も加わります。
こうした痛みは睡眠の質を下げ、精神的疲労を増やします。
パパが授乳姿勢をサポートしたり、授乳後の片付けやおむつ替えを引き受けるだけでも、ママの負担は軽くなります。
4. 孤独感と「私だけ頑張ってる」感
夜中、真っ暗な部屋で起きているのは自分だけ…。
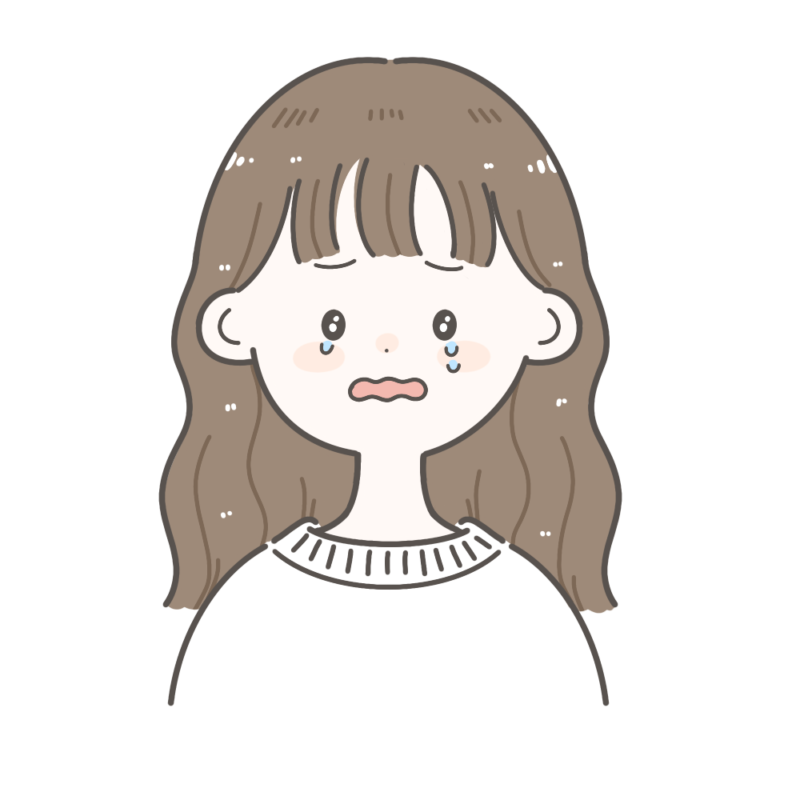
「なんで私だけこんなに頑張ってるの?」
そんな気持ちが続くと、ママは強い孤独感を抱きます。
隣でパパがぐっすり眠っていると、その感情は怒りや悲しみに変わることもあります。
二人の子どもだからこそ、「この大変さを共有してほしい」とママは願っています。
大変なときこそ、小さな共感や一言の声かけが夫婦の信頼関係を深めます。
5. 赤ちゃんが寝ない不安と自己否定
赤ちゃんが何度も起きると、自分を責めるママも少なくありません。
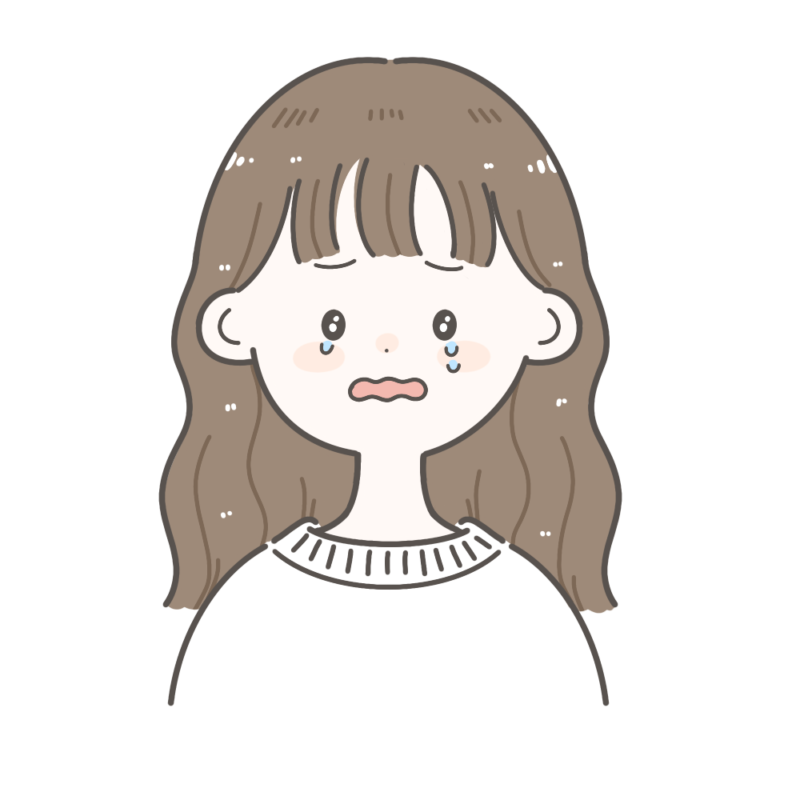
私のあやし方が悪いのかな…
母乳が足りてないのかも…
睡眠不足や疲労で心が弱ると、冷静な判断ができず、不安が膨らみます。
そんなときこそ、パパの励ましや「大丈夫、一緒にやっていこう」という言葉が支えになります。
30歳・初産ママの実例紹介
初めての出産を迎えたママ。
夫婦で話し合い、「仕事に支障が出ては困るから」と夜は別室で眠ることにしました。
ママも納得して始めたはずでしたが、夜中に一人で赤ちゃんを抱っこし、授乳し、おむつを替える日々。
夫は朝8時に出勤し、帰宅は夜9時。
実家は遠く、日中も家事と育児を一人でこなさなければなりません。
産後2週間、訪問したときにママはぽつりと言いました。
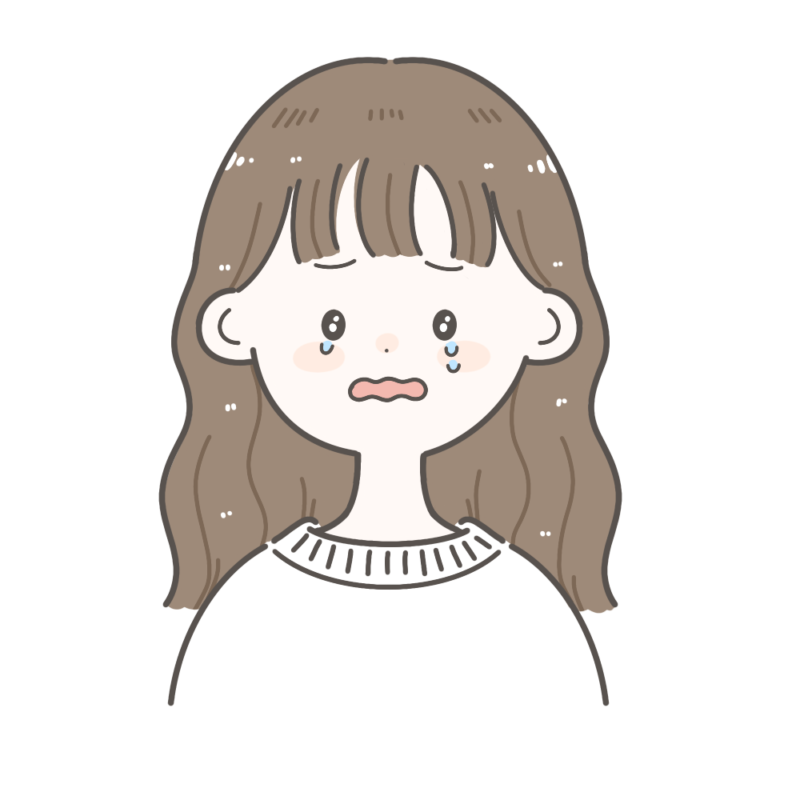
「育児のしんどさを分かってもらえなくて…朝からイライラが止まらないんです。
私は毎日ほとんど寝ていないのに、ねぎらいの言葉もなくて。」
このように「辛さに気がついてほしい」と思っているママは少なくありません。
「毎日ありがとう。育児も頑張ってるね」
「今日は少しお昼寝しておいで」
そんな一言や気遣いだけでも、ママの心は大きく救われます。
もちろんパパが仕事を頑張ってくれていることに、ママはとても感謝しています。
でも同じくらい、家で我が子を育てているママにも、感謝の気持ちを言葉で届けてください。
【神対応】パパのサポート術とNG対応

夜間授乳は、ママにとって体力も気力も大きく削られる時間です。
でも、パパのちょっとした行動や言葉が、その負担をぐっと軽くします。
ここでは、ママの心と体を確実にラクにする「神対応」と、絶対に避けたいNG対応をご紹介します。
今すぐできる!パパの神対応
オムツ替え・寝かしつけを担当
赤ちゃんのお世話を少しでも分担することで、ママの休息時間を確保できます。
「邪魔になるかも…」と思う必要はありません。
最初はぎこちなくても、練習で次第に慣れていきます。
赤ちゃんのおむつ替えについては、こちらで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
水や軽食を用意
授乳中はとても喉が渇き、お腹も減ります。
そっとお茶やお菓子を差し出すだけで、ママは泣きそうなくらい嬉しいもの。
手軽に食べられるグラノーラクッキーやバナナなどがおすすめです。
毛布をかける
授乳は肌の露出が多く、冬や夜中は特に冷えます。
授乳中や授乳後にそっと毛布をかけてあげると、体だけでなく心まで温まります。
肩や背中のマッサージ
授乳姿勢は前かがみになりやすく、肩や背中にコリがたまりがち。
授乳後に軽く肩をほぐすだけでも、血流が良くなりリラックスできます。
ママの睡眠を最優先
昼寝時間を作る、夜のオムツ替えを代わるなど、ママの休息を第一に。
休日は「今日は僕が見るから、少し寝たら?」と声をかけてみましょう。
「一緒にやる」姿勢を見せる
育児はうまくできなくても大丈夫。
大切なのは、一緒に赤ちゃんと向き合う姿勢です。
ママが得意に見えるのは、赤ちゃんと接する時間が長いから。
「僕にはムリ!」と思わずに、 赤ちゃんに向き合ってみてください。
パパも少しずつ慣れていけばOKです。
声かけのポイント
感謝と労いを言葉にする
赤ちゃんと二人きりで過ごす日々は、社会とのつながりが薄れ、孤独を感じやすくなります。
特に、産前はバリバリ働いていたママほど、そのギャップで孤独感が強まりやすいものです。
「いつもありがとう」「頑張ってくれてるね」など、感謝の言葉は何度でも伝えてください。
当たり前だと思わず、意識的に言葉にすることが大切です。
共感する
夜間授乳中のママは、眠気や疲労で心が沈みがち。
特に効果的なのは、共感と感謝を伝えることです。
「すごく眠いよね」「いつも助かるよ」など、ただ共感するだけでも「分かってくれている」という気持ちになり、心が少し軽くなります。
アドバイスより寄り添いを
アドバイスや解決策を急いで示すより、気持ちに寄り添うことが大切です。
まずは話を聞いて、理解する姿勢が信頼の土台になります。
絶対に避けたい!NGワード
パパに悪気がなくても、次のような言葉はママを傷つけ、「分かってもらえない」と感じさせます。その結果、心の距離が広がってしまうことも。
そんなに大変?
ママの気持ちを否定する言葉。
共感がないと、ママは孤立感を深めてしまいます。
俺も眠いんだけど
共感ではなく“疲れ比べ”になってしまい、気持ちがすれ違います。
手伝おうか?
育児はママの仕事という前提を感じさせる表現です。
代わりに「一緒にやろうか?」「今日は僕が抱っこするよ」と置き換えましょう。
35歳・3人目出産ママの実例紹介
35歳で3人目を出産したママ。
出産から1週間後、赤ちゃんの体重チェックに訪れたとき、彼女の表情は疲れ切っていました。
「休めていますか?」と声をかけると──
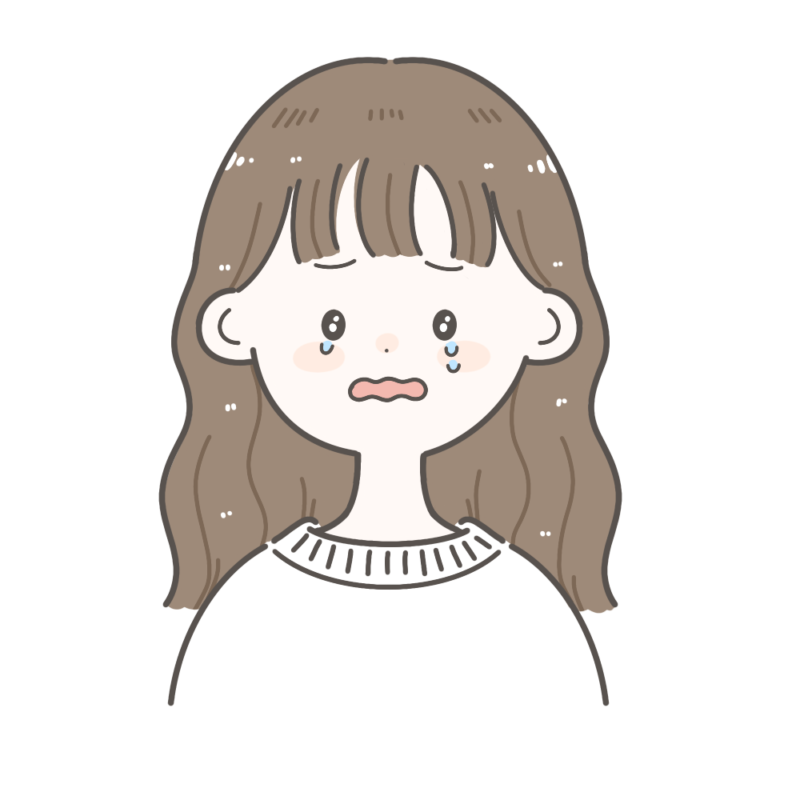
夫が何も手伝ってくれなくて…。
涙ながらにそう話してくれました。
このママは、上の2人の出産時は里帰りでサポートを受けていました。
しかし今回は、小学生と幼稚園児の生活があるため、自宅での産後生活。
身体の痛みや睡眠不足のなか、家事や食事作りも自分でこなしていました。
それでも土日、パパはソファで過ごし、子どもを外へ連れ出すこともなし。
辛い気持ちをパパに伝えることすらできずにいたそうです。
私はまず産後ケアの利用を提案。
ママが休める時間を確保し、パパにもサポートの必要性を伝えるよう勧めました。
その後、産後ケアを利用し始めたママは、少しずつ体調が回復。
1ヶ月健診では、以前よりも明るい笑顔を見せてくれました。

パパに手伝ってほしいことを伝えたら、少し気持ちが楽になりました。
実はパパは、「ママのほうが上手にできるから」と育児に消極的。
さらにこれまで里帰りが当たり前だったため、産後のママの辛さを実感したことがなかったのです。
ママは「わかってほしい」
パパは「わからない」
──そんなすれ違いは珍しくありません。
忙しくても、夫婦のコミュニケーションはとても大切。まずはシンプルに、「何かできることある?」と聞く一歩から始めてみましょう。
ぎこちなくても、一緒に悩み、関わろうとする姿勢こそが、ママの大きな支えになります。
夜間授乳が必要な理由と終わりのタイミング
夜間授乳は、ママにとって睡眠を削る大変な作業。
でも実は、赤ちゃんの成長を支える大切なゴールデンタイムでもあります。
パパがその理由を理解しておくと、「なぜ夜中も授乳が必要なのか」が納得でき、サポートの意欲も高まります。
赤ちゃんの胃はビー玉サイズ

生まれたばかりの赤ちゃんの胃は、たったビー玉ほどの大きさ。
一度にたくさん飲めないため、昼夜問わずこまめな授乳が必要です。
お腹が空けば夜中でも泣くのは自然なこと。
「夜に授乳するのは普通なんだ」と理解しておくと、ママへのサポート意識も変わります。
夜は母乳がよく出る時間帯
母乳分泌を促すホルモン「プロラクチン」は、夜〜明け方に多く分泌されます。
この時間帯に授乳すると、母乳の量と質が安定しやすく、母乳育児を軌道に乗せる助けになります。
成長と安心感を育てる
夜間の授乳は、脳や体の発達に欠かせません。
さらに、授乳による肌と肌の触れ合いは、赤ちゃんに安心感を与え、心の成長にもつながります。
夜間授乳が終わる目安
多くの赤ちゃんは、生後3〜6ヶ月ごろから授乳間隔が少しずつ延びてきます。
これは胃が大きくなり、1回で飲める量が増えるためです。
ただし、個人差は大きく、1歳近くまで夜間授乳が続くことも珍しくありません。
夜間授乳は、ただ「お腹を満たすため」ではなく、赤ちゃんの体と心を育てる時間。
そして、その時間にママは大きな体力を使っています。
短時間睡眠でも楽になる工夫6選

夜間授乳が続く時期は、まとまった睡眠が取れず、体力も気力も消耗しがちです。
そんな時期を少しでもラクに乗り切るには、短時間でも効率よく休む工夫がポイント。
ここでは、今日から試せる6つの方法をご紹介します。
1. 授乳後はすぐ横になる
授乳が終わったら、洗い物や料理よりもまず休憩を。
横になるだけでも筋肉の緊張がほぐれ、眠気が戻りやすくなります。
「まずは休む」が夜間育児を乗り切る基本です。
パパは授乳後のオムツ替えや寝かしつけを引き受けて、「すぐ休んでいいよ」と声をかけましょう。
2. 20〜30分の昼寝を取り入れる
夜の睡眠が短い分、日中の短時間仮眠で脳と体を回復。
最適な時間は20〜30分で、長く寝すぎると逆にだるくなります。
3. カフェインの摂り方を工夫
授乳直後にコーヒーやお茶を飲むと、次の授乳時までにカフェインが薄まりやすくなります。
夕方以降はカフェインレス飲料やハーブティーに切り替えるのがおすすめ。
(参考資料:食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~)
ママ用のカフェインレスコーヒーやハーブティーを常備しておきましょう。
4. スマホや強い光を避ける
夜間授乳中にスマホを見ると、ブルーライトで脳が覚醒し眠れなくなります。
間接照明や授乳ライトで、必要最低限の明るさにしましょう。
事前に授乳用のやさしい明かりをセットしておくと、ママの負担が減ります。
5. 温かい飲み物でリラックス
ホットミルクやカフェインレスのハーブティーは、体を温めてリラックス効果を高めます。
特にたんぽぽコーヒーは鉄分やカリウムが豊富で、母乳の分泌UPも期待できます。
夜間授乳後に「温かい飲み物いる?」と声をかけ、マグカップを差し出すだけで心も温まります。
6. 軽いストレッチ

授乳で同じ姿勢が続くと血行が悪くなり、肩こりや腰痛の原因に。
肩甲骨や骨盤まわりをゆっくりほぐすだけで、疲労感が和らぎます。
パパはリラックスタイムに動画を流して一緒にストレッチしたり、肩をもんであげたりしましょう。
赤ちゃんの生活リズムを整える習慣

赤ちゃんの生活リズムが整うと、夜間の授乳回数や夜泣きが減り、ママの負担もグッと軽くなります。
リズムは一気に変わるものではなく、毎日のちょっとした習慣の積み重ねで作られます。
ここでは、家庭で簡単に始められる習慣をご紹介します。
朝はカーテンを開けて日光浴
赤ちゃんの体内時計は光に敏感です。
朝起きたらまずカーテンを開け、自然光を浴びさせましょう。
日光は夜の眠りを促すホルモン「メラトニン」の分泌リズムを整え、昼夜の区別をつけやすくします。
これはママの気持ちも軽くし、一日のスタートを穏やかにします。
パパは「おはよう!カーテン開けるね」と声をかけながら光を取り入れると、朝の空気が一気に明るくなります。
昼間は遊びや声かけで活動量を増やす
昼間にたくさん遊ぶことで、赤ちゃんは夜ぐっすり眠りやすくなります。
歌を歌う、絵本を読む、あやす、お散歩など、無理のない範囲で刺激を与えましょう。
パパが帰宅後や休日に「赤ちゃんと遊ぶ時間」を作れば、赤ちゃんの活動量UP&ママの休憩にもなります。
0歳児(生後1ヶ月)外気浴のやり方はこちらで紹介していますので、あわせてご覧ください。
夜は暗く静かな環境にする
夕方以降は照明を落とし、テレビやスマホの音を控えめにして、落ち着いた空間を作りましょう。
こうすることで、赤ちゃんは「暗くなったら寝る時間」と覚えやすくなります。
寝かしつけに最適な寝室環境についてはこちらで詳しく解説しています。
お風呂の時間を毎日同じにする
「お風呂 → 授乳 → 就寝」という流れを毎日ほぼ同じ時間で繰り返すと、赤ちゃんに安心感が生まれます。
お風呂で体が温まり、その後体温が下がると自然な眠気が訪れます。
パパはお風呂係を担当したり、入浴後に照明を落として静かな雰囲気を演出すると効果的です。
生活リズムは1〜2日で整うものではありません。
家族で協力し、毎日少しずつ同じ流れを積み重ねていくことで、赤ちゃんの体内時計は少しずつ整っていきます。
月齢・年齢別の寝かしつけルーティンはこちらをご覧ください。
まとめ|パパの一歩がママの大きな支えに
夜間授乳は、赤ちゃんの成長に欠かせない大切な時間です。
でもその分、ママの体と心には大きな負担がかかります。
だからこそ、パパの一言やちょっとした行動が、ママにとって大きな支えになります。
「おつかれさま」「ゆっくり休んでね」
そんな短い言葉でも、ママの気持ちはふっと軽くなります。
長く感じる夜も、赤ちゃんの成長とともに少しずつ変わっていきます。
今は大変でも、この時期は必ず終わります。
大事なのは、ママと一緒に悩み、向き合う姿勢です。
その積み重ねが家族の絆を強くし、赤ちゃんにも安心を与えます。
これからも、ママと赤ちゃんが安心できる環境を、パパとママで一緒に作っていきましょう。