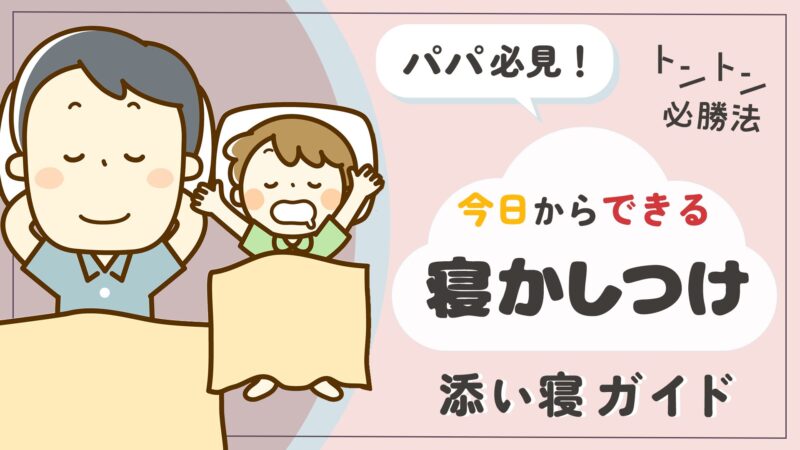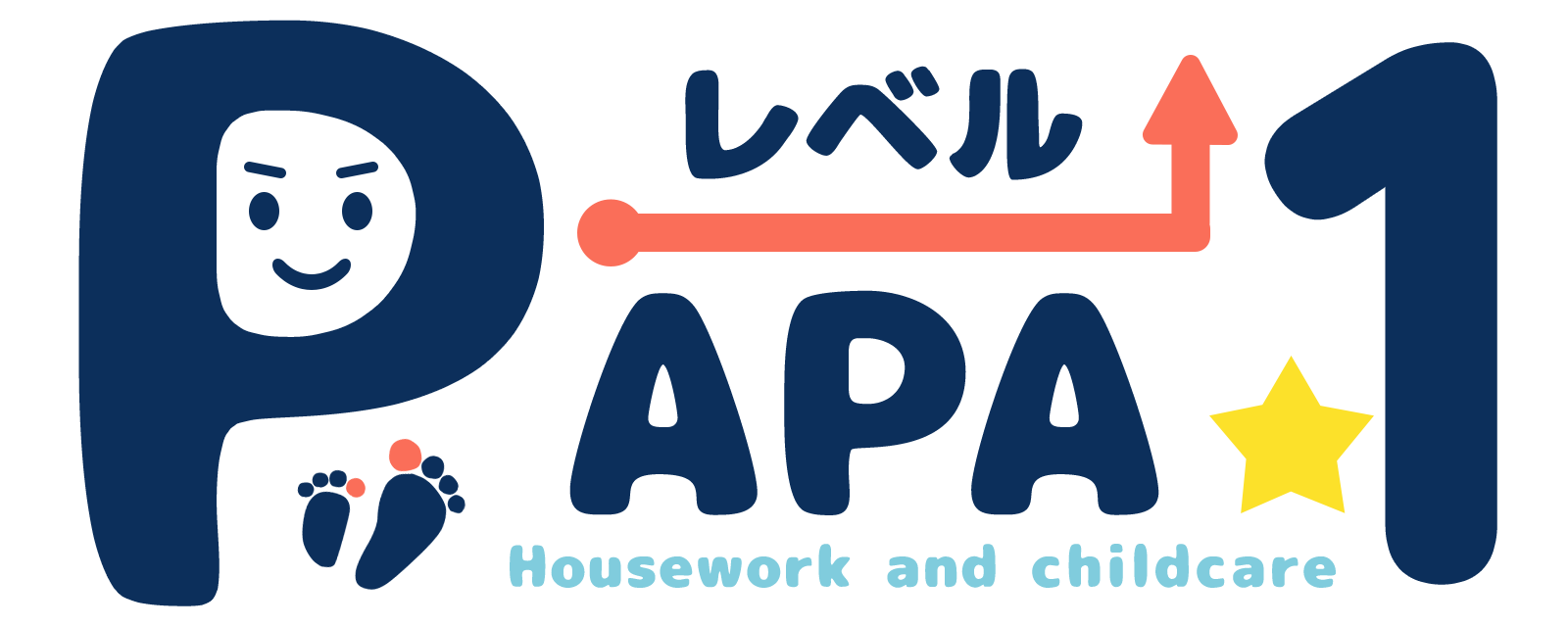【歯科衛生士解説】子どものお口ケア完全ガイド|乳歯の大切さ・歯磨き・虫歯予防の基本

待望のわが子が生まれて、気づけばもう生後半年。
毎日忙しく育児をこなすなかで「ん?…あれ?歯が生えてる!?」と、思わぬ成長に驚いたパパも多いのではないでしょうか。
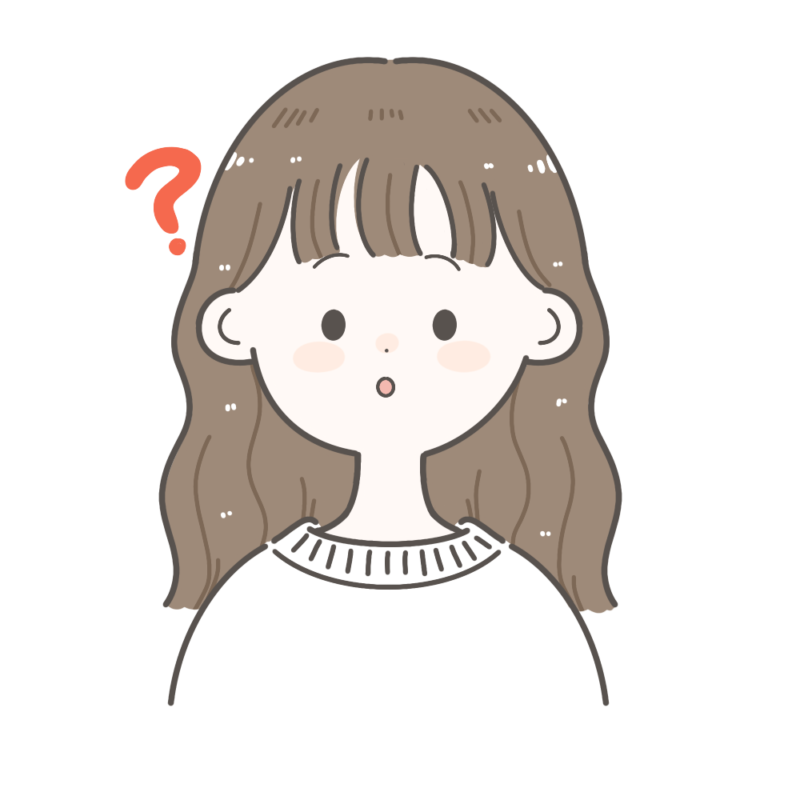
子どもの歯って、どうやってケアしたらいいの?

虫歯になったらどうしよう…?
そんなふうに、はじめての歯のケアに戸惑ったり、不安を感じたりしていませんか?
実は赤ちゃんの歯(乳歯)は、将来の歯並びや健康な体の土台をつくる大切な存在。
でもーー
「乳歯だし、すぐ抜けるから大丈夫でしょ?」
「正直、どうケアすればいいのか分からない…」
そう思って、つい後回しになってしまうこともありますよね。
筆者は歯科衛生士として15年以上、たくさんの親子のお口の健康をサポートしてきました。
一児のママとして、仕上げ磨きや“歯みがきイヤイヤ期”の苦労も、身をもって体験しています。
そんな私の経験をもとに、この記事では、育児初心者のパパでも今日から始められる「赤ちゃんの歯とお口のケア」について、やさしく解説します!
赤ちゃんの歯のケアは、「知ること」でぐっとラクになります。
一緒に、今日からできることを楽しく始めていきましょう!

藤 明日香(歯科衛生士)
歯科衛生士として15年以上、幅広い世代のお口の健康をサポートしてきました。現在は育児中のママとして、パパにも伝わる口腔ケア情報を発信しています。
なぜ、子どもの歯はそんなに大事なの?


小さな乳歯だから、そんなに気にしなくても大丈夫でしょ?
実は、子どもの歯には大切な役割がたくさんあります。
たとえば…
- 食べ物を噛んで、栄養をきちんと摂る
- きれいな発音で話す
- あごやお顔の成長をサポートする
つまり、乳歯は“ただの仮の歯”ではなく、子どもの体づくりの土台なんです。
そして、乳歯はこれから生えてくる永久歯の「道しるべ」にもなります。
だからこそ、今からのケアがとても大切なんです。
乳歯を放っておくと、どうなるの?

いずれ生え変わるし、虫歯になっても大丈夫なんじゃない?
乳歯の虫歯は、将来の歯や健康に大きな影響を与えることがあります。
たとえば、乳歯に虫歯があると…
- 虫歯があると、その下の永久歯が弱くなって生えてくることがある
- 虫歯で早く乳歯を失うと、永久歯の生える場所がずれて歯並びが悪くなる
- 噛む力が弱くなって、栄養の吸収や消化に影響する
- しっかり噛めないと、あごの発達が遅れてしまう
乳歯は“使い捨ての歯”ではありません。
だからこそ、毎日のケアが子どもの将来を守る第一歩になります。
「虫歯ゼロの子」に育てるために、今日からできること
虫歯は、きちんと対策すれば防げる病気です。
まずはこの3つの柱を意識してみましょう。
そしてなにより大切なのは、パパも一緒に取り組むこと。
パパが楽しそうに仕上げ磨きをしたり、「一緒に歯みがきしよう!」と声をかけたりするだけで、子どもにとって歯みがきは“当たり前の習慣”になります。
家族みんなで取り組むことが、子どもの歯と体を守る力になりますよ。
市販のおやつ、虫歯になりやすい?なりにくい?
おやつタイムは子どもにとって楽しみな時間。
でも、虫歯が心配…というパパも多いのではないでしょうか?

虫歯になりにくいおやつの選び方のコツを教えてほしい!
虫歯になりやすいおやつ【高リスク】
以下のおやつは、歯にくっつきやすい・歯のすき間に残りやすいため、虫歯のリスクが高めです。
- 飴、グミ、キャラメル
- チョコレート
- クッキーやビスケット
- 甘いスナック菓子
筆者の子どももグミやチョコが大好き。
でも虫歯が心配なので、「お出かけ中に1つだけ」「食べたらお茶を飲む」というルールを決めています。
無理に禁止するのではなく、あげるタイミングや量を工夫するのがポイントです。
虫歯になりにくいおやつ【低リスク】
一方で、虫歯になりにくい安心おやつもちゃんとあります。
市販品の中でも、以下のようなおやつはおすすめです。
- 干し芋
- チーズ
- かためのおせんべい
- 野菜チップス
共通点は、甘さ控えめで素材がシンプルなこと。
噛む力も育ちますし、毎日のおやつとして安心して取り入れられます。

特別な時には少しだけ甘いおやつをあげて、日常はシンプルなおやつをあげたいな!
そんな気持ちで、ゆるやかに選んでいくのが◎です。
虫歯ってうつるの? 知っておきたい大切なこと
意外かもしれませんが…虫歯菌はうつるって、知っていましたか?
赤ちゃんは生まれたとき、虫歯菌を持っていません。
でも、日々の食事やスキンシップを通じて、大人の口の中の菌がうつることがあります。
- パパやママが使ったスプーンで食べさせる
- 食べ物を口移しする
- ほっぺや口元にキスをする
とはいえ、赤ちゃんは大人の食べ物を欲しがりますし、スキンシップも大切な時間ですよね。
大事なのは、「うつらない工夫」と「うつっても虫歯にならない環境づくり」!
- スプーンや箸などの食器は分ける
- 口移しや“フーフー”で冷ます行為は控える
- パパ・ママ自身もお口の中を清潔に保つ(歯磨き&定期検診)
- 赤ちゃんの歯みがき習慣を大切にする
よくやってしまいがちな、食事を冷ますためのフーフーも実はNG。
筆者は、食事を冷ますときはミニ扇風機を使っていました。
虫歯菌を完全にシャットアウトするのは難しいですが、虫歯になりにくい環境づくりはできます!
できることから、家族みんなで少しずつ意識していきましょう。
(参考:8.各時期における歯科保健指導のポイント/クラブサンスター)
子どもの歯の基本を知ろう!

赤ちゃんの歯の生え方には個人差がありますが、全体の流れを知っておくと、「今、順調かな?」「歯医者さんに相談したほうがいいかな?」の判断がしやすくなります。
子どもの歯は何本あるの?
赤ちゃんの歯(乳歯)は全部で20本。
だいたい生後6〜8ヶ月頃から生え始めます。
| 月齢・年齢 | 生える場所 | 本数の目安 |
| 生後6ヶ月頃 | 下の前歯(2本) | 2本 |
| 生後10ヶ月頃 | 上の前歯(2本) | 4本 |
| 1歳頃 | 上下の前歯4本ずつ | 8本 |
| 1歳6ヶ月頃 | 第1乳臼歯(奥歯) | 12本 |
| 2歳頃 | 乳犬歯(犬歯) | 16本 |
| 2歳6ヶ月頃 | 第2乳臼歯(奥歯) | 20本 |
ただし、前後6ヶ月くらいの差はよくあります。
筆者の子どもは生後4ヶ月で歯が生えましたし、1歳を過ぎても下の前歯だけだった子もいます。

赤ちゃんの個人差って大きいんだね!
歯が少ない?ちょっと気になる場合は…
時には、歯の本数が少ないこともあります。
先天性欠如(せんてんせいけつじょ)
生まれつき歯の本数が少ない状態です。
乳歯では少ないですが、そのまま永久歯も生えてこないこともあるため注意が必要です。
癒合歯(ゆごうし)
隣同士の歯がくっついて、1本に見える歯です。
隙間が磨きにくく、虫歯のリスクが高くなります。
どちらの場合も、気になったら早めに歯医者さんに相談しましょう。
成長に応じた適切なアドバイスが受けられます。
6歳ごろからは「歯の生え変わり」もスタート!

乳歯から永久歯へ。
6歳頃からは「生え変わり期(混合歯列期)」に入ります。
| 歯の抜ける目安 | 抜けはじめる場所 |
| 6歳頃 | 下の前歯2本 |
| 7歳頃 | 上の前歯2本 |
| 7歳~9歳頃 | 側切歯(前から2番目) |
| 9歳~11歳頃 | 第1乳臼歯(奥歯) |
| 11歳~12歳頃 | 乳犬歯(犬歯) |
| 11歳~13歳頃 | 第2乳臼歯(奥の奥) |
生え変わりには個人差があります。
しかし、新しい歯がなかなか見えないときは、歯医者さんに相談してみてください。
生え変わりのとき、どう対応する?
歯がグラグラし始めたら、つい抜きたくなるかもしれませんが…
基本は自然に抜けるのを待つ!が鉄則です。
抜けたあとは、ガーゼで優しくふいてあげればOK。
出血が少しあっても、すぐ止まれば心配いりません。
「次はどこに生えるのかな?」と、親子で楽しみに待てるように声かけしてあげましょう。
よくある!子どものお口トラブルと対処法

小さな子どもは、「なんとなく痛い」「なんか変」など、はっきりと症状を伝えるのが苦手です。
だからこそ、パパの気づきと初期対応がとても大切!
ここでは、よくあるお口トラブルとその対策を、わかりやすく解説します。
子どもから「歯が痛い!」と言われたら
子どもが歯を痛がったら、まず落ち着いて以下をチェック!
痛みの原因は虫歯だけでなく、歯の生え変わりやぶつけたあとの場合もあります。
朝に落ち着いても、ぶり返すことがあるので、一度は歯医者さんで診てもらうのが安心です。
歯ぐきが赤い・腫れている・血が出る
これは「歯肉炎」のサインかも。
原因は、歯磨き不足や乳歯の生え始めの刺激などが考えられます。
- やさしく丁寧に歯を磨く
- うがいで清潔に保つ
- 栄養バランスの良い食事を心がける
たいていは歯磨きで改善しますが、ぷくっと腫れてきたり、長引いたりする場合は歯医者さんへ!
前歯をぶつけた!どうする?

元気いっぱいな子どもは、転んだりぶつけたりは日常茶飯事。
前歯をぶつけたときは、最初の対応がカギになります!
歯が折れてしまったとき
歯医者さんへすぐ電話し、状況を伝えてから向かいましょう。
- 小さなかけらでも捨てずに保管
- 牛乳に入れる or 濡れガーゼで包む(乾燥NG)
- 口の中の血や破片は、無理せず見える範囲だけそっと取り除く
- 頬を冷やして、腫れや痛みを軽減
歯がグラグラしているとき
必ず歯医者さんに診てもらいましょう。
気になって、動かしたり押したりすると、抜けてしまう可能性があります。
- 絶対に触らないこと!
- 食事は柔らかいものを、反対側で噛む
歯が抜けてしまったとき
できるだけ早く、電話してから歯医者さんに向かいましょう。
- 根元は触らず、歯の上部だけを持つ
- 牛乳に入れて持参(乾燥させない)
お口のにおいが気になるときは?
「なんだか口が臭う…?」そんなときの対策は以下の通り!
でも、多くの場合は歯磨き不足や舌のケア不足が原因です。
- 歯ブラシ+舌クリーナーでお口全体をやさしくケア
- 水分補給をこまめに(口の乾燥防止)
- 口呼吸のクセをチェック(口がいつも開いていないか?)
- 歯ごたえのある食事で唾液アップ
- 定期的な歯科健診
においが続くときは、虫歯や他のトラブルの可能性もあるので、歯医者さんで相談を!
歯が白い・茶色い・黒い…これって虫歯?
「歯の色が変わっている?」と気づいたら、つい心配になりますよね。
色の変化にはいくつか理由があります。
| 色の変化 | 考えられる理由 |
| 白い | 初期虫歯(脱灰)・エナメル質形成不全 |
| 茶色 | 食べ物による着色・虫歯初期 |
| 黒い | 食べ物による着色・進行した虫歯・歯の神経のトラブル |
「エナメル質形成不全」は歯の表面がうまくできていない状態で、虫歯になりやすいため注意が必要です。
見た目だけで判断せず、歯磨きをしてから観察。気になる場合は歯医者さんへ。
子どもなのに歯ぎしり?大丈夫?
夜寝ているとき、「ギリッ、ギリッ…」と音がすることもありますよね。
でも、子どもの歯ぎしりはよくあることで、ほとんどの場合は心配いりません。
- 歯並びが整う途中
- 生え変わりの違和感
- ストレスや緊張
- 口呼吸のクセ
多くは成長とともにおさまりますが、歯がすり減っていたり、あごに痛みがある場合は歯医者さんへ!

お口のトラブルは歯医者さんに相談するのが1番だね。
歯並びは毎日の習慣で決まる!今日から始める“口育(こういく)”のすすめ

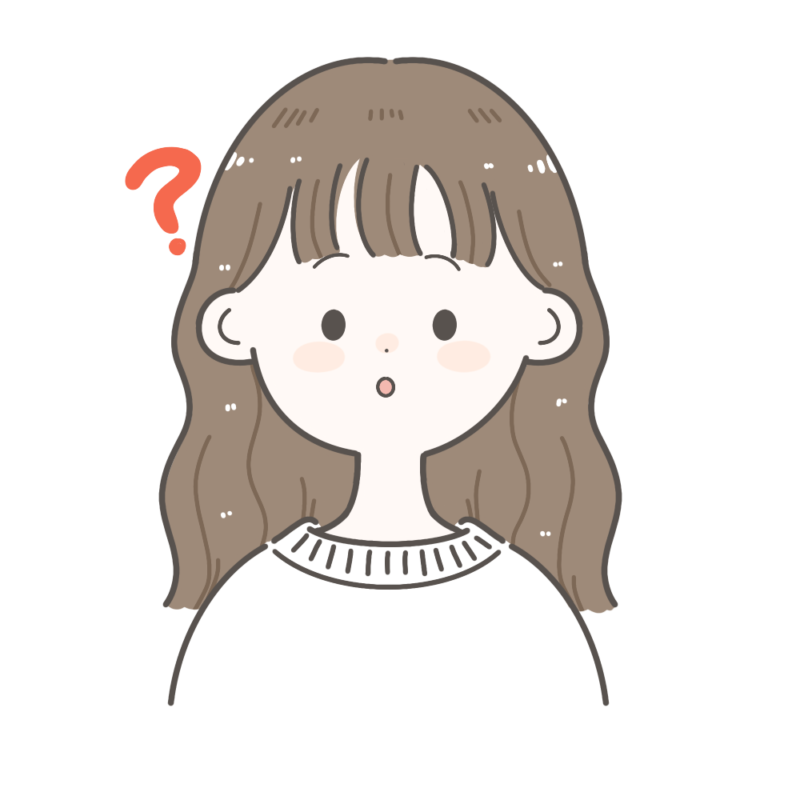
うちの子、すきっ歯だけど大丈夫?
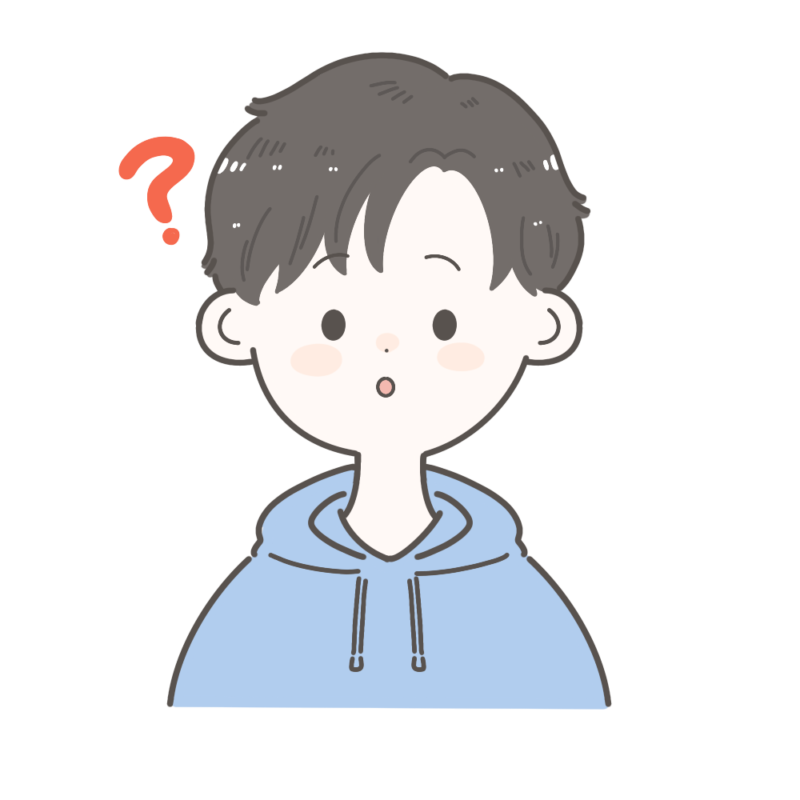
いつまでもやわらかい食事ばかりでいいのかな?
最近はやわらかい食事や便利グッズの影響で、噛む力やあごの発達が十分に育ちにくい環境になっています。
でも大丈夫!「ちょっとした習慣」が、お口の発達=口育につながります。
STEP1:離乳食で噛む力を育てよう
離乳食は、栄養補給だけでなく「噛む力」を育てる大切なステップです。
噛む力を育てる4つのコツ
「噛む力」をしっかり育てるには、積み重ねが大切です。
- 月齢に合った固さ・大きさの食材を選ぶ
- スプーンは水平にあてて、唇を使う
- 飲み込んだのを確認してから次の一口
- 硬さに変化のあるメニューで「もぐもぐ」習慣づけ
離乳食で「噛む練習」→ 唾液が増える → 虫歯予防にも!
月齢に合った離乳食の進め方も分かりやすく解説していますので、あわせてこちらの記事をご覧ください。
※正しい食べさせ方で、歯並びにも差がつく!
実は、離乳食の「食べさせ方」や「食べるときの習慣」は、将来の歯並びやあごの発達に大きく関係しています。
「とりあえず食べてくれればOK!」と思ってしまいがちな時期ですが、ほんのちょっとした工夫が、お口の成長をサポートしてくれるんです。
噛む力アップにおすすめの食材
噛む力を育てるには、あごの発達を促す食材を上手に取り入れるのがポイントです。
- 根菜(にんじん、ごぼう、かぼちゃ など)
- きのこ類(しめじ、えのき)
- 果物(りんご、梨など)
- やわらかく煮た豆類、わかめ、昆布 など
小さく刻んだり、煮たりして月齢に合わせればOK!
食事中に「もぐもぐしようね」と声をかけるのも効果的です。
手づかみ食べ用の離乳食「TEDEMOGU(てでもぐ)」についてはこちらで紹介していますので、合わせてお読みください。
離乳食で避けたいNG食材
一見よさそうでも、噛みにくい・丸呑みしやすい・酸性が強いなど、離乳食に不向きな食材もあります。
飲み物で流し込みさせるクセも要注意!「噛んで飲む」が基本です。
STEP2:正しい姿勢が歯並びを変える!

姿勢が崩れると、あごの位置もズレて、噛み合わせに悪影響が出ることもあります。
必要に応じて足台やクッションで高さ調整を。
イス・机・足台の高さを見直すだけで、噛む力・集中力もUP!
STEP3:コップ飲みで口の機能を育てよう
哺乳瓶やストローの長期使用は、舌の位置がズレる・口呼吸が増えるなどの原因に。
離乳食が始まる6ヶ月頃から、コップ飲みの練習を始めましょう!
- スプーンで水を少しずつ → 飲み込む感覚を覚える
- 小さめのコップに少量の水 → パパが手を添えて練習
- 自分の手でコップを持たせる → 「じょうずだね!」と声かけ
初めてのコップ飲みには、赤ちゃんが扱いやすい形や素材のものを選ぶのがポイントです。
はじめはむせても大丈夫。少しずつでOKです!1歳ごろまでに慣れてくる子が多いです。
筆者の子どもは生後5ヶ月から練習して、哺乳瓶を卒業した1歳過ぎにマスターしました。

赤ちゃんの水分補給は大切だから、根気強い練習が大切だね。
STEP4:楽しく遊んで口の筋トレ
お口周りの筋肉(口輪筋)を鍛えることで、鼻呼吸が定着しやすくなり、歯並びにもいい影響が出ます!
どれも遊び感覚でできるので、親子で楽しく続けられます!
指しゃぶりはどうする?目安は3歳ごろまで

乳児期の指しゃぶりは自然な行動。でも、3歳を過ぎても続く場合は、少しずつやめる工夫を。
指しゃぶりは「安心」のサイン。
無理に叱らず、環境づくりで自然な卒業をサポートしましょう。
毎日の歯磨きで虫歯ゼロへ!年齢別のケアとアイテム選びのコツ

赤ちゃんの歯が生え始めたら、いよいよお口のケアがスタート!
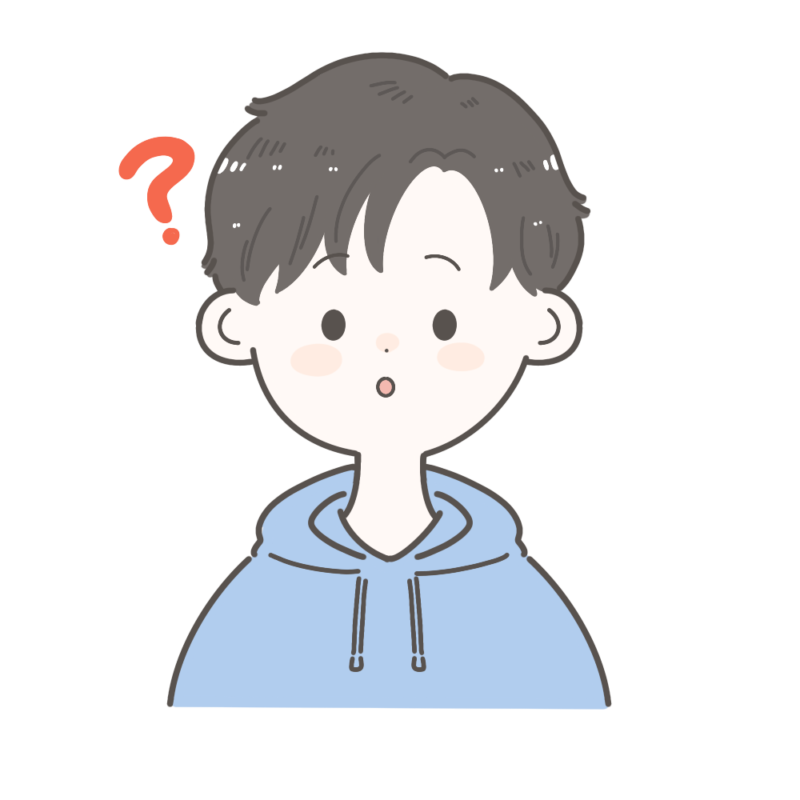
どの歯ブラシを使えばいい?
歯磨き粉っていつから?
仕上げ磨きってどうやるの?
そんな疑問をもつパパも多いはず。
ここでは、年齢別の歯磨き方法とアイテムの選び方を、やさしく解説します。
子どもの仕上げ磨きの大切さやコツなどを詳しく解説していますので、あわせてこちらの記事をご覧ください。
年齢に応じた歯磨き方法
子どもの歯磨きは、年齢や発達に応じて段階的にステップアップしていくことが大切です。
「まだ小さいし、自分でできないから…」と思わず、月齢や習慣に合わせた方法で、少しずつお口ケアの習慣を育てていきましょう。
0〜2歳:まずは慣れることが大切
赤ちゃんの歯が1本でも生えたら、歯磨きのスタート時期です。
最初はガーゼで優しく拭いてあげるだけでもOK!
- 仕上げ磨きは必ず大人が行う
- 歯ブラシより先に“口に触れること”に慣れる
- 歯磨き粉は基本不要 or フッ素500ppm以下を米粒大でOK
はじめは泣いてしまっても大丈夫!「毎日ちょっとずつ」が成功のカギです。
3〜5歳:自分で磨きたがる時期に仕上げ磨きをプラス
「じぶんでやりたい!」という気持ちが芽生えてくる年齢。
でも、まだまだ奥歯や歯の間の汚れは残りがちです。

イヤイヤ期の歯磨きは、正直しんどいな…
そう思うパパ・ママも多いはず。でも、ここが歯を守る分かれ道です!
6歳~小学生:永久歯が生える大切な時期
この頃は乳歯と永久歯が入り混じる「混合歯列期」。
歯の位置もバラバラで、とても磨きにくい時期です。
- 12歳くらいまでは1日1回、仕上げ磨きを継続
- フロスも取り入れて、歯と歯の間のケア
- 歯磨きの“習慣化”を目指そう!
歯磨きタイムが楽しくなる!アイテム選びのコツ

毎日のケアを「イヤな時間」にしないためには、アイテム選びが重要。
安全性と使いやすさ+ちょっと楽しい工夫を忘れずに。
歯ブラシの選び方
歯ブラシは1ヶ月に1回の交換が理想。毛先が開いたら、迷わずチェンジしましょう!
お気に入りの色やキャラクターを選ばせると、自分から進んで磨くようになります。
「これ、ぼくが選んだ!」「わたしの歯ブラシだよ!」とお子さんが自分で選んだ実感があると、歯磨きが楽しい時間になりますよ。
歯磨き粉の選び方
フッ素濃度は、子ども用は500~1,000ppm、年齢が上がってくると1,500ppmのものも選べるようになります。
「泡が多くて苦手」「味が嫌!」などの理由で歯磨きイヤイヤが起きやすいので、合うものをいくつか試してみて。
コップの選び方
コップもうがいも「自分専用!」という感覚が、習慣化につながります。
プラスαの補助アイテムも活用しよう
成長に応じて、歯ブラシ以外のケアも少しずつ取り入れていくと◎
- キシリトールタブレット
甘いのに虫歯予防に◎ おやつ代わりにもOK - デンタルフロス(子ども用持ち手付きのタイプがおすすめ)
歯ブラシが届きにくい歯間をカバー - 舌ブラシ
口臭やネバつきが気になる時に軽くなでるように使う - フッ素洗口剤(うがい薬)
うがいができるようになったら毎日のケアに
大人が「やらなきゃ…」と気負うより、子どもが「やってみよう!」と思える気持ちを育てるのがコツです。
子どもの虫歯はこうして防ぐ!初期サインの見分け方と毎日の予防法


歯が白く濁ってるけど、穴はない…これって虫歯?
お子さんの歯を見て「なんだか白っぽい…?」と気になったことはありませんか?
実はそれ、虫歯のはじまり=初期虫歯かもしれません。
でもご安心を。進行を止める方法はあるんです!
このページでは、見逃しがちな虫歯のサインや、家庭でできる予防法をやさしく解説します。
【虫歯のサイン】“白く濁る”ってどういうこと?
虫歯といえば「黒い穴」というイメージが強いかもしれませんが、それはすでにかなり進行した状態。
初期虫歯は、「ツヤのない白さ=白く濁った歯」がサインです。
痛みがなくても放っておくと、どんどん進行してしまいます。
「あれ?」と思ったら、まずは歯医者さんでチェック!
早期発見なら削らずに済む可能性が高いんです。
【初期虫歯】自然に治る?歯医者に行くべき?
一度虫歯になると、自然に元通りにはなりません。
けれど、進行を止める「再石灰化(さいせっかいか)」という力を活かせば、削らずに済むことも。
再石灰化を助けるためにできること
- フッ素塗布(歯科医院で)
- 毎日の正しい歯磨き
- 間食・食生活の見直し
ポイントは「穴があく前」に気づくこと!
反対に、黒くなっていたり穴があいていれば、すでに治療が必要な状態です。

歯を削るのは大人でもこわいから…
できるだけ早く気づいてあげたい!
食生活で虫歯予防!食べ方の工夫がカギ

虫歯になりやすいのは、「甘いもの」そのものよりも食べ方・タイミングです。
おやつの時間はメリハリが大事!
ダラダラ食べ続けると、虫歯菌が出す酸が歯をずっと攻撃し続けます。
食べた後は、唾液の力で「再石灰化」を働かせる時間が必要です。
だからこそ、おやつの時間にメリハリをつけることが大切です。
お口をリセットする時間をつくることが、お子さんの歯を守るカギなのです。
飲み物の選び方も重要!
虫歯予防のためには、飲み物の選び方も大切です。
- 基本は「水」「麦茶」などの無糖飲料を選ぶ
- ジュースやスポーツドリンクは糖分たっぷり
ジュースはできれば「特別な日だけ」のご褒美にするのがおすすめです!
寝る前のおやつはNG!
寝る前の食べ物は、虫歯になりやすい原因のひとつです。
- 寝ている間は唾液が減り、虫歯になりやすい状態
- 寝る前の食事や飲み物は、歯にとって大きな負担
理想は…「夕食後に歯磨き → もう食べない!」の習慣化です。
歯磨き+αで虫歯ゼロへ!補助アイテムを活用しよう


歯磨き嫌がるし…何か他にできることないかな?
そんなときは、キシリトールタブレットなどの補助アイテムをうまく取り入れてみましょう!
キシリトールは、「おやつ感覚」で食べられる上に、唾液の分泌を助け、虫歯菌の活動を抑えてくれます。
小さなお子さんには、タブレットは砕いて与えると安心です。
ただし、あくまでタブレットは“歯磨きの補助”。
「タブレットをあげたから歯磨きしなくていいや」ではなく、「歯磨き+フッ素+キシリトール」のトリプル予防で、虫歯知らずのお口を目指しましょう!

歯磨き後のご褒美にあげるといいかも!
定期健診で子どものお口をしっかりサポート


まだ虫歯はないし、歯医者さんはもう少し後でいいかな…
そう思っていませんか?
歯が1本でも生えたら、早めに歯医者さんとのお付き合いを始めるのがおすすめです。
乳歯は虫歯が進みやすく、またお子さんは痛みをうまく伝えられないことも多いからです。
だからこそ、「悪くなる前に行く」という予防の考え方がとっても大切!
定期健診では虫歯のチェックだけでなく、歯並びやあごの発達、噛む力なども専門的に見てもらえます。
小児歯科と一般歯科の違いって?
小児歯科は、子どものお口の健康を専門に診る歯医者さんです。
子どもの歯は虫歯の進行速度が速く、構造にも違いがあります。
子ども専門の知識と対応力が求められるので、小児歯科だと安心して受診できます。
「泣いてしまったらどうしよう…」と不安なパパも、小児歯科なら安心して通えますよ。
歯医者デビューの予約時に気をつけたいポイント
ちょっとした工夫で、歯医者さんを「楽しい場所」に変えられます。
- 家でごっこ遊びをして「お口を開ける練習」をしておく
- 「歯医者さんは怖くないよ」と優しく伝える
- 機嫌のいい時間帯(午前中やお昼寝前)を予約する
- 「初めて」「○歳です」「人見知りします」など事前に伝える
- 混雑していない時間帯を選び、ゆったり対応してもらう
最初のイメージが良ければ、その後も嫌がらずに通えるようになります。パパの声かけが、お子さんの安心につながりますよ。
かかりつけの歯科医院を持つと「気軽に相談できる場所」ができ、いざというときに心強い存在になります!
歯科検診では何をするの?

歯科検診って何をするんだろう?
不安なパパも多いですが、実際はとてもやさしい流れです。
- 親子で一緒に診療台に座ってお口をさっとチェック
- 歯科衛生士さんから年齢に合わせた歯磨きアドバイス
- 虫歯のチェックとフッ素塗布で予防ケア
- 6歳頃には奥歯の溝に「シーラント」をして虫歯予防
- 歯石の除去も(子どもでも歯石はつきます!)
お口の状態は数ヶ月で変わることも多いため、3~4ヶ月に1回の定期検診がおすすめです。
気になることは遠慮せず、気軽に質問しましょう。
例えば…
「仕上げ磨きはどうしたらいい?」「こんなときはどうすれば?」など、丁寧に教えてもらえますよ。
お口の健康は、親子で育てる一生の財産

お子さんのお口の健康は、単に「虫歯を防ぐこと」だけが目的ではありません。
体の健やかな成長、心の発達、そして毎日の生活習慣の土台にもつながる、大切な育ちの一部です。
この記事では、歯科衛生士であるママの目線から、パパにもわかりやすく、子どもの歯のケアについて丁寧にお伝えしてきました。

ちゃんと磨けてるかな…?
虫歯になったらどうしよう…
そんな不安を感じるのは、パパとしてしっかりお子さんに向き合っている証です。
でも、どうか肩の力を抜いてくださいね。
次の4つを、無理のない範囲でコツコツ続けていくだけで、お子さんの歯はしっかり守れます。
そして何より大切なのは、「パパが一緒にいてくれる」という安心感です。
子どもは、大好きな人がそばで応援してくれることで、歯磨きも、歯医者さんも、自然と前向きに受け入れていくようになります。
お口の健康は、親子で築く一生モノの宝物。
今日のひと手間が、未来の笑顔につながっていきます。
どうか、無理なく・楽しく・一緒に続けていってくださいね。